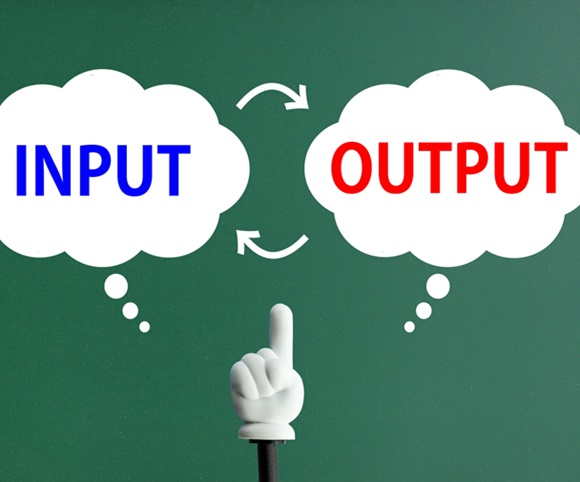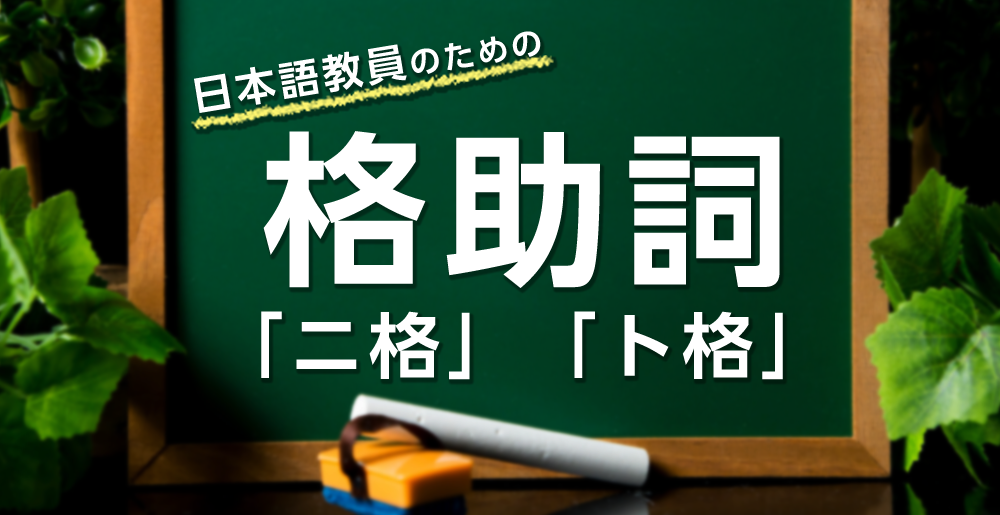
【保存版】格助詞・二格、ト格のポイント
この記事では、前回の『格助詞・ガ格、ヲ格のポイント』に引き続き、格助詞「二格」「ト格」の教え方について、わかりやすく説明します。
おさらい!格助詞とは何か?
格助詞とは、「が」「に」「より」など、主に名詞の後ろにくっついて、その名詞がどのような働きをするのかを示す語のことを言います。語順の自由度が高い日本語にとって、言いたいことを正しく伝えるために、格助詞はなくてはならない存在です。今日は資格試験で狙われやすく、日本語教師としても必須アイテムの「二格」「ト格」を詳しく見ていきましょう。
格助詞「に」の教え方
「7時に起きた」「会社に行った」など、日常的にもよく使う格助詞「に」ですが、その用法の多さは格助詞の中でもトップクラス!分類方法は研究者によって異なりますが、ここでは13種類(※)を紹介します。初級クラスの学習者からは「また別の「に」が出てきた…」なんて言われてしまうこともありますが、日本語教師として教壇に立つ上で、格助詞「に」はマスター不可欠!ひとつずつ、しっかりおさえていきましょう。
※日本語記述文法研究会(2009)を参考に筆者が再構成
【二格】格助詞「に」の用法は、主に13個です。
1. 着点
2. 変化の結果
3. 相手
4. 場所
5. 主体
6. 起因・根拠
7. 対象
8. 手段
9. 時
10. 領域
11. 目的
12. 役割
13. 割合
1. 着点/Point of Arrival
「行く」「来る」など、移動動詞の到着点を表します。
(例)・会社に行きます。
・家に帰ります。
「捨てる」「送る」など、位置が変化する動詞の到着点も表せます。
(例)・缶をゴミ箱に捨てます。
・荷物を空港に送ります。
2. 変化の結果/Result of Change
「変わる」「なる」など、変化を表す動詞を取るとき、変化した結果を表します。
変化が行き着いた先、と捉えると、着点の用法とも言えるでしょう。
(例)・春になります。
・この文章を日本語にしてください。
3. 相手/Recipient
ざっくり言うと「誰に?」の「に」です。
⚫︎動作の相手:「会う」「頼む」「相談する」などの動詞を取るとき、動作が向かう相手を表します。
(例)・友だちに会います。
・母に電話をかけます。
⚫︎授与の相手:「あげる」「くれる」「貸す」などの動詞を取るとき、動作の受け手を表します。
(例)・犬にえさをやります。
・銀行にお金を預けます。
⚫︎受身的動作の相手:「もらう」「つかまる」「教わる」などの動詞を取るとき、主体に行為を与える相手を表します。また、受身文の動作主も表します。
(例)・友だちにプレゼントをもらいました。
・私は祖母に育てられました。
⚫︎基準としての相手:「似ている」「まさる」「劣る」などの動詞を取るとき、基準となる相手を表します。
(例)・妹は母にそっくりです。
・ホテルもいいが、家にまさる場所はない。
4. 場所/Location of Existence
ざっくり言うと「どこに?」の「に」です。
「ある」「ない」「住む」などの述語を取るとき、主体の存在する場所を表します。
(例)・今、カフェにいます。
・東京に住んでいます。
何かが出現し、その後、存在する場所も表せます。
(例)・手に汗をかきました。
・システムにエラーが発生しています。
5. 主体/Experiencer
⚫︎所有の主体:「ある」「ない」など存在を表す述語を取るとき、主体を表します。また、多い少ないを表す述語の主体も表します。前述した「場所」の用法と似ていますが、この用法では主体が物ではなく、人間や動物など感情を持つ生き物となります。
(例)・私には夢があります。
・妹には、彼氏がいます。
・彼には、悩みが少ないです。
⚫︎能力の主体:可能動詞や「できる」「見える」「聞こえる」などの動詞を取るとき、主体を表します。
(例)・私にはわかりません。
・彼にこの漢字は読めないでしょう。
⚫︎心的状態の主体:知覚や感情、感覚を表す述語を取るとき、主体を表します。
(例)・このケーキ、日本人には甘すぎます。
・私には、この部屋は寒いです。
6. 起因・根拠/Cause or Reason
感情や感覚を表す述語を取るとき、その状態になった起因や根拠を表します。
(例)・上司に悩んでいます。
・親友の言葉に励まされました。
動作の起因となった自然現象も表します。
(例)・旗が風になびいています。
7. 対象/Target
ざっくり言うと「何に?」の「に」です。
⚫︎動作の対象:「勝つ」「負ける」「賛成する」「合格する」などの動詞を取るとき、動作の対象を表します。
(例)・日本語能力試験に合格しました。
・親にさからって、しかられました。
⚫︎心的活動の対象:「あこがれる」「困る」「満足する」などの心情を表す動詞を取るとき、対象を表します。
(例)・練習するのに飽きました。
・テストの結果に満足しました。
8. 手段/Filled with or Covered with
⚫︎内容物:「満ちる」などの充満を意味する動詞を取るとき、主語を器として捉え、その器を満たす内容物を表します。
(例)・留学生の顔は、希望に満ちあふれています。
・スタジアムは、観客の興奮に満ちています。
⚫︎付着物:「まみれる」などの状態変化を意味する動詞を取るとき、主語に付着する物を表します。
(例)・その部屋は、ほこりにまみれていました。
・道は、落ち葉に覆われています。
9. 時/Point in Time
「午後3時」「月曜日」「3月」など、絶対的な時点が決まる名詞について、時を表します。
(例)・朝7時に起きます。
・2004年に大学を卒業しました。
10. 領域/Field
「難しい」「重要だ」「必要だ」など、認識に関わる形容詞などを取るとき、認識が成り立つ領域を表します。
(例)・私にはこの問題は難しいです。
・気候変動対策には、各国の協力が不可欠です。
11. 目的/Purpose
「行く」「来る」など移動を表す動詞を取るとき、移動の目的を表します。
(例)・買い物に行きます。
・昼ごはんを食べに帰ります。
12. 役割/Role
行為の役割や意味を表します。
(例)・お礼にこの本をプレゼントします。
・旅行の思い出に、キーホルダーを買いました。
13. 割合/Proportion
割合や頻度を表します。
(例)・3人に1人は、運動不足です。
・週に2回、日本語を勉強しています。
⚪︎教え方のコツ
「時」の用法に関する、初級学習者によくある以下の間違い。あなたならどう教えますか。
正:2024年に日本に来ました。
誤:去年に日本に来ました。→この場合「去年に」の「に」は不要。
時の「に」は、発話したタイミングに左右されることがない、絶対的な時点を指し示す名詞につきます。
【に・必要】3時、3日、3月、2025年、21世紀、日曜日、誕生日、クリスマス、春
逆に、発話したタイミングに左右されてしまう名詞には「に」をつけません。
【に・不要】今日、明日、あさって、今週、来週、今月、来月、今年、来年、今、昔
私の初級クラスでは「カレンダーや時計でいつでもここ!と示せる言葉だ」と指差しアクション付きで教えています。この教え方を使えば、「誕生日」など、数字を伴わない言葉であっても具体的に指し示せるから「に」が必要だ、とすっきり理解してくれますよ。
格助詞「と」の教え方
【ト格】格助詞「と」の用法は、主に3つです。
1. 相手
2. 変化の結果
3. 内容
1. 相手/Companion or Partner or Standard
⚫︎共同動作の相手:行為を共にする相手を表します。
(例)・姉と映画に行きます。
・友だちとサッカーをしました。
⚫︎相互動作の相手:「結婚する」「つきあう」「戦う」など一人ではできない行為の動詞を取るとき、その相手を表します。
(例)・子どものとき、よく弟とけんかしました。
・友だちは、アメリカ人と結婚しました。
⚫︎基準としての相手:「違う」「間違える」「同じだ」「近い」などの述語を取るとき、基準となる相手を表します。
(例)・姉は母とそっくりです。
・カタカナのンをカタカナのソと間違えてしまいました。
2. 変化の結果/Result of Change
変化を表す動詞を取るとき、変化した結果を表します。
(例)・試合は雨で、中止となります。
・雪がとけて春となる。
この用法では「に」に書きかえ可能ですが、印象が少し異なります。
・午後から雨となりました。(と→書き言葉的)
・午後から雨になりました。(に→話し言葉的)
3. 内容/Content
「呼ぶ」「言う」「みなす」などの動詞を取るとき、内容を表します。
(例)イエローカード3枚で、失格とみなします。
モーツァルトは神童と呼ばれた。
⚪︎教え方のコツ
以下の中で、用法が異なるものはどれでしょうか。
(1) 友だちと散歩する。
(2) 友だちと喧嘩する。
(3) 友だちと料理する。
答えは(2)。これは「相互動作の相手」の用法で、(1)と(3)は、「共同動作の相手」の用法です。見分け方は簡単。共同動作の相手の用法の場合、「〜といっしょに」に置きかえ可能です。指導時はもちろん、資格試験対策としてもしっかりおさえておきましょう。
まとめ
格助詞「に」については、用法の多さに圧倒されてしまった方もいるかもしれませんが、それは学習者も同じこと。私のクラスでは、「助詞の「に」は、とっても働き者だね」なんて言いながら、「に」が登場する度に用法名を確認するようにしています。用法の分類方法や名称は、書籍や専門家によって異なることもありますが、現場で活躍する日本語教師としては、自分にとってしっくり来て、学習者にとっても理解しやすい名称を選ぶことも大切です。この記事がそのお役に立てば幸いです。
参考
庵 功雄, 高梨 信乃, 中西 久実子, 山田 敏弘 (2000)『初級を教える人のための日本語文法ハンドブック』松岡弘監修, スリーエーネットワーク
大阪YWCA, 氏原 庸子, 清島 千春, 井関 幸, 影島 充紀, 佐伯 玲子 (2023)『くらべてわかるてにをは日本語助詞辞典』Jリサーチ出版
日本語記述文法研究会編 (2009)『現代日本語文法2 第3部格と構文 第4部ヴォイス』くろしお出版

【日本語教員試験対策】「日本語教育の参照枠」の「全体的な尺度」とは?日本語能力の6レベルを分かりやすくご紹介!
日本語のレベルを判断する際の基準として役立つ「日本語教育の参照枠」の中から、最もおおまかな尺度である「全体的な尺度」について解説します。「初級」「中級」などと言っても、レベルの定義は実はあいまい。そんなときに活用できるのが、今回解説する「全体的な尺度」です。「日本語教員試験」にも出てくる重要キーワードで、教師デビューした後も活用できるものですので、理解を深めてみてください。

ピジン、クレオール、リンガ・フランカの違い
日本語教育能力検定試験に必ず出てくる最重要ワード「ピジン、クレオール、リンガフランカ」について説明します!