

あなたの考えるビジネス日本語とは
概要
みなさんは「ビジネス日本語」についてどのように考えますか。職場で、生活している環境の中で、「働く外国人」の姿を多く見かけるようになったと感じることはありませんか。厚生労働省の調査によると、2023年10月末現在で外国人就労者の数は204万8675人、前年の同じ時期に比べると12.4%も増加し、過去最高の人数となっています。増加し続ける外国人就労者が日本で能力を発揮し、ストレスを感じず、よりよい仕事をしていくために必要なことのひとつが日本語の習得です。その、外国人就労者が働く上で必要な日本語の習得をお手伝いすることも日本語教師の仕事の一つです。外国人就労者の増加とともにビジネス日本語を教えることは今後日本語教師の仕事の大きな柱になっていくと思います。
ビジネス日本語とは何ですか
「ビジネス日本語」という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。では、「ビジネス日本語」ではどんな内容を扱うのだと思われますか。「挨拶」「敬語」「ビジネスマナー」「電話のやりとり」「紹介する」という内容が頭に浮かぶ方が多いのではないでしょうか。もちろんこれらの内容は重要です。ビジネス日本語のテキストを見ても、必ずといっていいほど扱われている内容です。「ビジネス日本語を勉強したい」と言う学習者に何を勉強したいかと問うと、「敬語」という方も多いです。ですが、「ビジネス日本語」を学ぶということは単にビジネスシーンで使うフレーズや語彙を学ぶだけのことでしょうか。これを読んでくださる皆さんと「ビジネス日本語」を学ぶとは何かを考えてみたいと思います。
学習者が「ビジネス日本語」を学ぶ最大の理由は、「日本語が分かる、使えるようになることで、仕事ができるようになる、あるいは仕事上での課題を解決する」ことではないでしょうか。
学習者が抱える業務上の課題は人によって全く異なります。
例えば、
「会社のミーティングの際、日本語で意見が言える」
「仕事の報告書を日本語で書ける」
「自分が考えたシステム設計について人に理解してもらう」
「お客様の注文を聞いて調理担当者に正しく伝えられる」
「手順通りに野菜の加工作業ができる」
「介護施設利用者さんの異変を的確に素早く周囲の人に伝えられる」
等、これらのことができるようになるためにどうすればいいのかを考えたときに、仕事の技術や知識は十分にあるのに、日本語力が足りないために業務に支障をきたしているという人も中にはいるかもしれません。業務の内容は問題ないけれど、日本語がわからないから業務がすすめられない、という学習者が望んでいるのは「日本語ができるようになること」なのか「仕事ができるようになること」なのかを考えてみる必要があると思います。
就労場面で必要な日本語能力の目標設定ツール
学習者の「できるようになりたいこと」を把握したあとで、そのためにどのような日本語の習得が必要になるかを選択し、学習のプランを立てていくのですが、そこで参考になるツールを紹介しましょう。
厚生労働省が「就労場面で必要な日本語能力の目標ツール」として「就労can do(目安)」を公表しています。この目標設定のツールには、3つの柱が掲げられています。
1.日本語学習者を社会的存在として捉える
学習が目的ではなく、より深く社会に参加し、より多くの場面で自分らしさを発揮できる
2.言語を使って「できること」に注目する
言語知識を持っていることよりも、その知識を使って何ができるかに注目する
3.多様な日本語使用を尊重する
就労can doでは、レベルをA1~B2の7レベルに分けており、また言語活動を
聞くこと
読むこと
話すこと(やりとり)
話すこと(発表)
書くこと
オンライン
仲介
の7項目に分けられています。
レベル7×言語活動7の49項目に分かれているので、学習者の「何がどれだけできるか」「不足している所は何か」を測るための参考にすることができます。
ビジネス日本語の評価に使われるテスト
就職試験や職場で日本語の能力を客観的に評価するために使われる試験はいくつかありますが、そのうちの2つを紹介しましょう。
1).JLPT(日本語能力試験)
国際交流基金、日本国債教育支援協会が実施している日本語を母語としない人の日本語能力を測定し、認定する試験です。1年に2回(7月・12月)日本国内、海外で実施されています。初級から上級までN5、N4、N3、N2、N1の5段階に分かれています。
外国人就労者では特定技能の資格で就労する場合はN4~N3が必要とされています。また、「技術・人文知識・国際業務」、外国人が専門的技術や知識を活かし、即戦力として高度な業務につくことのできる「技人国」と呼ばれる在留資格で就職する場合、N2を取得していることが求められることが多いです。
2).BJT(ビジネス日本語能力テスト)
日本漢字能力検定が実施しています。「在留資格認定証明書交付申請」に日本語能力の証明としてBJTスコアを明記できます(300点以上でJLPTのN5以上)。テストのスコアからJ5ーJ1+の6段階で評価されます。試験は頻繁に実施されており、受験会場も多いので受験しやすい試験です。日本ビジネス社会で必要な日本語コミュニケーション能力を測る試験です。
誰に教える、どこで教える
「ビジネス日本語」を学ぶ学習者の背景は実に様々です。企業で働く方、自営業の方、特定の産業分野で仕事をする特定技能ビザで働く方、特定の産業で働きながら技能を身に付ける技能実習生の方(技能実習制度は2027年から育成就労制度になります)などです。また、留学生の中にも就職を目指す人が増えてきていますので、留学生に対するビジネス日本語の教育も必要性が増しています。近年は働き方も多様化してきており、リモートワーク中心の働き方、派遣業で働く先が変わる人、スペシャリストからブジッリ人材にポジションが変わるなど学習者の背景は様々です。外国人が就労する職種の多様化も進んでいます。ビジネス日本語に携わる教師の働く現場も多岐にわたります。プライベートレッスン、企業派遣、日本語学校や大学などのビジネス日本語講座やグループレッスンの他、最近では専属の日本語教師を置き社員の言語教育を行う企業も現れています。また、地域のボランティア日本語教室でも外国人就労者を対象にしたところもありますし、日本語学校の留学生に対するビジネス日本語の予備教育に携わっている教師もいます。教育の方法も対面授業、オンライン授業、対面とオンラインを同時に行うハイブリッド形式の授業など学習者のニーズに合わせた方法がとられています。
学習者の背景も目標も様々、教え方も様々な中で最も大切なことは、学習者やビジネス日本語の教育を依頼するクライアントの満足度がどこにあるかを見出すことではないかと思います。
私はどんな場合でも、
1).職場の中でのコミュニケーション力を上げる。特に「職場で一緒に仕事をする人や周囲の人に相談したり質問できる関係を築く」ことを目指す。
2).学習者が必要なこと、知りたいことをレベルや難易度に関わらず教える。
3).続ける、続けられるための工夫をする。レッスンプランの変更などにも柔軟に対応していく。
ことを心がけています。
これを読んでくださっている皆さんは「ビジネス日本語」の教育についてどのように考えられますか。
TCJ日本語教員養成講座で学びませんか
つい最近まで、日本語教師=主に日本語学校や専門学校、大学等で留学生に日本語を教える仕事、あるいは海外で日本語学習者に日本語を教える仕事というイメージがありました。しかし、日本語を教える仕事のフィールドは急激に広がっています。ビジネス日本語もその一つです。それでも、養成講座で学ぶことはどの分野で教える場合でもゆるぎない基礎になると思います。養成講座で学んだことは、その時にはピンと来なくても、仕事を初めた後で何度も思い出したり、急に理解できたりとみなさんの仕事を支えるものになるはずです。養成講座で学ぶ時間、そして講師や他の受講者、現役日本語教師との濃いコミュニケーションは大きな財産になると思います。
参考
就労場面で必要な日本語能力の目標設定ツール/厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000773360.pdf
参考
「外国人雇用状況」の届け出状況まとめ(令和5年10月末時点)/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/001195787.pdf
外国人就労・定着支援研修標準モデルカリキュラムー厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000881320.pdf
日本語能力試験
https://www.jlpt.jp/
BJTビジネス日本語能力テスト
https://www.kanken.or.jp/bjt/
ビジネス日本語教え方&働き方ガイド
小山暁子・武田聡子・長崎清美 著
アルク発行(2023年 初版)
にほんごで働く!ビジネス日本語30時間」
宮崎道子・郷司幸子 著
スリーエーネットワーク発行(2023年 13版)
「BJTビジネス日本語能力テスト入門」
わかるビジネス日本語
加藤清方 監修
島田めぐみ 瀧川晶 小川茂夫 共著
アスク出版 発行
国家試験対策が必要な方へ
TCJ日本語教師養成講座では、日本語教員試験の学習に特化したeラーニング教材を開発しました。
令和6年度日本語教員試験での合格率(当社調べ)
・基礎、応用試験 合格率44% (全国平均8.7%)
・応用試験のみ 合格率71%(全国平均 60.8%)
試験ルートの合格率が全国平均の約5倍となっています。
【こんな方におススメ】
・試験ルートで登録・日本語教員の資格取得を検討している方
・現在日本語教師として活躍中で経過措置に国家資格への移行が必要な方
・養成講座受講中で国家試験対策に不安がある方
詳しくは公式サイトでご確認ください。↓のリンクをクリック。
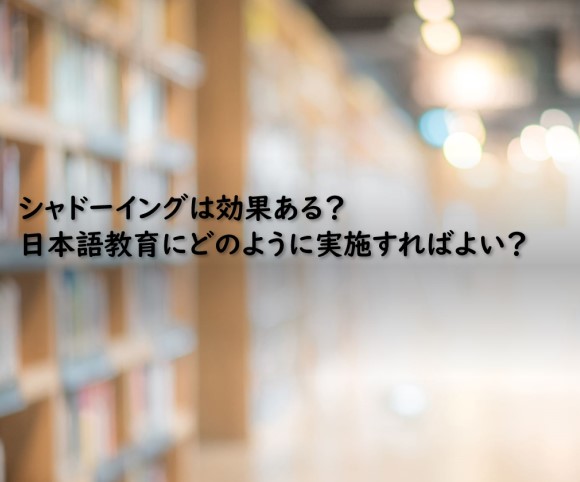
シャドーイングは効果ある?日本語教育にどのように実施すればよい?
シャドーイングは、音声を聞きながら同時に発生する練習です。 日本では英語学習の際に実施した人は多いのではないでしょうか? 日本語学習においても同様に効果的であるため、日本語教育の現場 において、どのようシャドーイングを導入していくかを解説します。

学習ストラテジーで日本語学習をより楽しく効果的に!
「外国語教師が知っておかなければならない」でお馴染みの学習ストラテジー。もちろん、日本語教師だって知っておかなきゃです。この記事では、言語学習を効果的で楽しくする学習ストラテジーをわかりやすく解説いたします!






