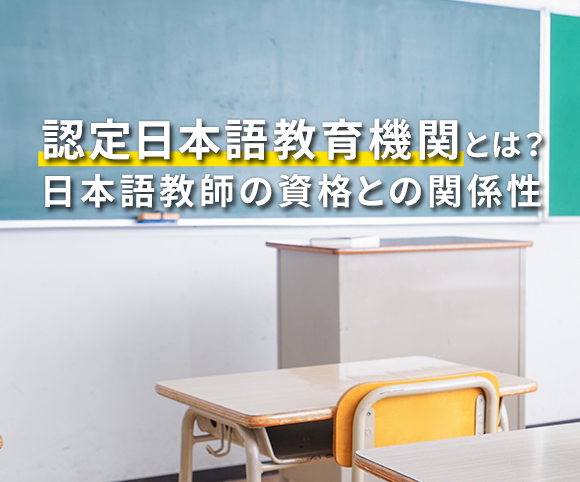インプット仮説(i+1)を改めて考えてみよう
概要
今回は、インプット仮説(i+1)を改めて考えてみようと思います。まず、インプット仮説(i+1)が何かについて解説していきます。そして、インプット仮説(i+1)の問題点について説明していきます。さらに、実際の授業でやっている例を紹介します。その後、i+1やインプット仮説というワードが日本語教育能力検定試験に出るかということについても述べていきます。
インプット仮説(i+1)とは何か
i+1(アイ・プラス・ワン)とは、米国の言語学者Steven Krashen(スティーブン・クラッシェン)教授が提唱した「インプット仮説」のことです。ここで言う「i」とは、「学習者がすでに至っている言語レベル」です。これに「+1」をする、つまりそれを少し上回るように学習しよう、という方法です。
「インプット仮説」(Krashen 1982)は、人が言語を学ぶ方法は主にメッセージを「理解する」 ことによると主張するものです。「理解可能なインプット」が十分与えられれば、それだけで習得は十分可能であり、アウトプットや意識的学習、誤用訂正などはごく限定的な役割を果たすに過ぎないとしています。
インプット仮説の有効性
ここではインプット仮説の有効性について考えていきたいと思います。
Krashen(1982)によれば、「理解可能」なインプットを大量に得た時に効率的な言語習得が可能である、ということですが、この「理解可能である」ということが重要なようです。
木村(2012)では、3週間の英語圏への海外短期研修で、英語ライティングの流暢さが1.8倍になったという結果が出ています。ここでは、期間が短くても、海外研修に参加した学生の何らかの英語力が伸びるのは、やはりシャワーを浴びるように、英語のインプットを大量に受けてくることが大きな要因ではないかと述べられています。
このように、言語教育において、「理解可能なインプット」というインプット仮説の有効性が見られます。
インプット仮説の実践例を紹介
では、インプット仮説の日本語教育における実際の授業での実践例、その効果について見ていきましょう。
横山(2004)では、日本語の動詞単語を対象に、次の過程の中で、(a) インプットのみを与えられた場合と (b) インプットに加えてアウトプットの機会があった場合について、習得の効果を比べています。北京外国語大学日本語学科 1 年生29 名、中国海洋大学日本語学科 2 年生21 名の計 50 名を対象に、以下の過程の調査を行いました。
- プリテスト(4 種):4 種のテストを、①形式の生成、②形式の認識、③意味の生成、④意味の認識の順番で行った。(30分)
- 1回目の聴解:物語のテープを段落ごとに30秒のポーズを置いて、先を予測しながら聞い た。これは、テープで与えられるインプットが習得に結びつく可能性を高めるために、聞い た内容を各自が反芻する時間を確保するためである。(10分)
- 理解確認の質問用紙記入:2回目の聴解で聞くべきポイントを意識させるために、物語の展開のポイントを問う質問に答えた。母語での解答も認めた。(5分)
- 2 回目の聴解:ポーズを置かずに聞く。(5分)
- 理解確認の質問用紙加筆修正:再度加筆修正の機会を与えることで内容の理解を徹底する目的で行った。(5分)
- スクリプトの空白記入:テープのスクリプト(対象語はひらがな表記、その他の漢字はルビつき)に空白をあけたものを配布し、空白に単語を記入した。空白部分はOW(インプットに加えてアウトプットの機会があった語)である。1700 字程度のスクリプトで、各7 語の OW および IW (インプットのみを受けた語)がそれぞれ 2 回ずつ使われている。空白の 箇所は 18 箇所で、7 語の OW が各 2 回ずつ含まれるほか、残り 4 箇所の空白は測定対象外の単語である。また、動詞が「て形」で使われる場合もあることから、空白は「 て (で)」とした。(15 分)
- 3 回目の聴解:再度テープを聞き、空白部分の単語について自己チェックをした。(10 分)
- ポストテスト(4 種):1週間後にプリテストと同じ順番で行った。記入済みプリテストのコピーを配り、自己修正を加える形で習得を調べた。(30分)
調査の結果、インプットのみによる処方も、アウトプットを含む処方も、意味、形式の両面において明らかな習得が確認できました。ただ、意味の習得においてアウトプットの優位が確認されたのです。この結果を踏まえ、横山(2004)は、教育実践における提言を行っています。それは、形式の習得にも及ぶインプットの安定した効果が確認できたため、人数の多いクラスでは、アウトプットに多くの時間をかけるよりも、インプットの効果を最大限に生かし、習得を狙う言語項目の出現頻度や出現範囲(異なる文脈での出現を確保すること)などにも気を配ることが有効であろうと述べています。
つまり、日本語教育に関して、日本語の語彙の意味においては、教師による意味の説明等が有効ではあるが、形式の定着にはそこまでの説明がなくても、ひたすらインプットを行うことができそうです。
日本語教育関連ワードでインプット仮説(i+1)と併記されるワードについて、簡単に解説
日本語教育能力検定試験において、インプット仮説は出てきやすいワードの1つです。よく、アウトプット仮説(第二言語習得においてはインプットだけでは十分ではなく、「話す」「書く」といったアウトプットも必要であるというもの)やインターアクション仮説(学習者が目標言語の母語話者とやりとりする際に生じる意味交渉が習得に貢献するという仮説)と共に出題されることが多いです。例えば、「インプット仮説」で習得につながるとされているインプットとは?」という問題が出ています。ちなみにこちらの問題は、インプット仮説で、習得につながるとされているインプットは、現在の言語レベルより少し高いレベルのインプット(i+1のインプット)が正解となっています。
まとめ
今回、「インプット仮説(i+1)」について、解説をしてきました。普段の授業における、動詞の活用の定着等において活用してみてください。
参考文献
木村啓子(2012)「ライティング力の変化とその情意的要因を探る試みー海外短期語学研修参加者の場合」『関東甲信越英語教育学会誌』26, pp.53-65
Krashen, S. (1982) PrinciPles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford : Pergamon.
Hatch, E. (1983). Simplified input and second language acquisition. In R. Anderson. (ed.). Pidginization and Creolization as Language Acquisition. Newbury House. pp.64-86
横山紀子(2004)「言語習得におけるインプットとアウトプットの果たす役割:単語の習得調査の分析から」国際交流基金日本語国際センター紀要14, pp.1-12.
国家試験対策が必要な方へ
TCJ日本語教師養成講座では、日本語教員試験の学習に特化したeラーニング教材を開発しました。
令和6年度日本語教員試験での合格率(当社調べ)
・基礎、応用試験 合格率44% (全国平均8.7%)
・応用試験のみ 合格率71%(全国平均 60.8%)
試験ルートの合格率が全国平均の約5倍となっています。
【こんな方におススメ】
・試験ルートで登録・日本語教員の資格取得を検討している方
・現在日本語教師として活躍中で経過措置に国家資格への移行が必要な方
・養成講座受講中で国家試験対策に不安がある方
詳しくは公式サイトでご確認ください。↓のリンクをクリック。