
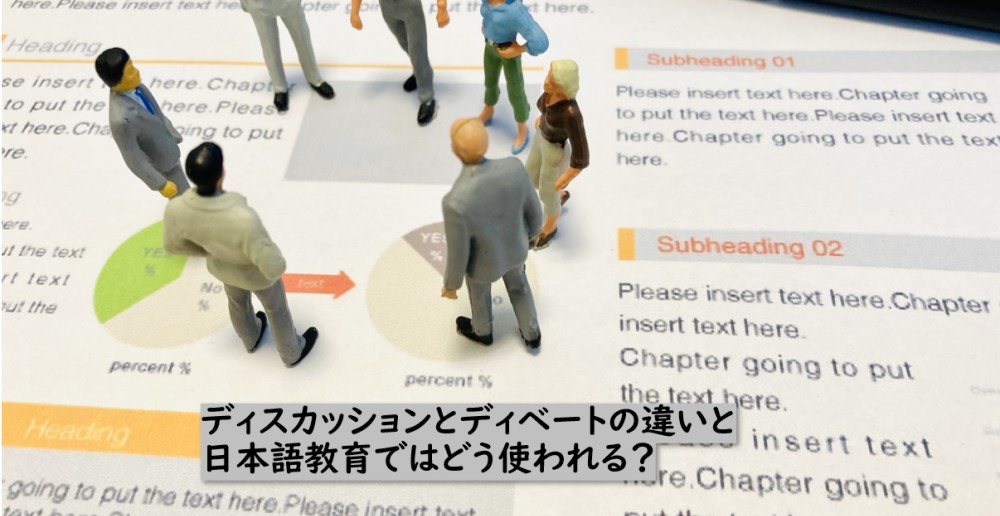
ディスカッションとディベートの違いと日本語教育ではどう使われる?
ディスカッションとは
複数人(4名程度)に一つのテーマを与え、お互いにアイデアや意見を出し合い、最終的に全員が納得できる結論に到達できるように話し合いを進めていきます。しっかりメンバーの意見を聞き、受け止めたうえで自分の意見を述べる、意見を述べていないメンバーには発言を促すなど、事前に参加者には留意点を伝えたうえで始めます。テーマと制限時間を与えた後は、参加者同士で時間管理や役割等を決めてから話し合いをスタートさせます。
昨今、「面接では見えない学生の個性・能力が発見できる」として、採用選考方法の一つとして実施している企業も増えてきました(グループ・ディスカッション)。全員で一つの結論に到達させる(=合意形成)までのプロセスの中に学生の仕事におけるポテンシャルを見いだせると考えているからです。
テーマ例:「日本の外国人観光客を増やすためには?」「居酒屋の売り上げを伸ばす方法」
ディベートとは
1つのテーマについて「肯定・否定」「賛成・反対」「A・B」等相反する立場に分かれ、第3者を納得させるためにお互いの意見を主張し合い、どちらが説得力のある意見であったかを判定し勝敗を決める知的ゲーム(以下、試合)です。参加者(1チーム:3~4名)は、事前にテーマについて資料を集め、自分たちの意見の客観的な裏付けをとり、説得力のある意見を準備してから試合に臨みます。客観性の高い説得力がある意見を構築させるためにはロジカルな考え、分かりやすい発表が求められます。試合の流れですが、まずお互いの意見を述べる「立論」があり、次に相手の意見をしっかり受け止めたうえで、さらに自分たちの意見に説得力を持たせるために話し合った後、「反駁」します。最後に自分たちの主張を、試合の流れを踏まえて「まとめ」で発表します。判定は試合の流れを見ていた第3者が行います。
誤解をしている人も多いかもしれませんが、ディベートは決して言い負かせば勝ちというものではありません。
テーマ例:「死刑制度の是非」「学校制服の是非」「住むなら田舎vs都会」
ディスカッションとディベートの目的
実は、上手にディスカッションやディベートができるようになるということだけが目的ではありません。どちらにも共通していることは、「論理的思考」「傾聴力」「協調性」を身に着けるということです。ディスカッションは話し合いの中に、ディベートは試合の中にそれぞれ学びがあります。特にディベートは準備段階の中にも大切な学びがあると言えます。
あなたの周りに「何を言ってるかよくわからないよ」と感じる人はいませんか。このタイプの人は、言いたいことを分かりやすく述べる方法を知らないのです。こういう人がディベートやディスカッションを学ぶと、論理的に話すことができるようになり、分かりやすい物言いになります。また、周りに人の話を聞かず、自分の意見を押し付けてくる人も少なからずいるのではないでしょうか。こういう人にもオススメしたいです。相手の話をよく聞かなければ話し合いにも試合にも参加できないからです。また、ディベートは一見「協調性」は必要ないように見えますが、同じチームの人たちと、同じ方向を向いて戦うわけですから、協調性は大切な要素と言えます。
このように、ルールを知り、滑らかに自分の意見を述べることも大切ですが、それ以外にも学びが多いのがディスカッションとディベートなのです。
ディスカッションとディベートの評価基準
ディスカッションとディベートはそれぞれ評価観点が異なります。
ディスカッションの評価基準:話し合いの中における個人の活躍ぶりを評価する
・積極的に発言できているか(積極性)
・根拠を示し、分かりやすく話せているか(論理的思考)
・他者の意見をよく聞き、それに的確に反応できているか(傾聴力)
・自分の意見を押し付けていないか、他者へ発話のターンを回せているか(協調性)
ディベートの評価基準:どちらのチームの意見に納得したかで評価する
・資料を示し、客観的な意見が述べられているか(論理的思考)
・相手チームの意見を踏まえたうえで意見を構築できているか(傾聴力)
・チームメンバーと協力し合い、自分たちに有利な意見が述べられているか(協調性)
主な評価基準を挙げてみました。ほかにも、日本語教育現場では、日本語の正確性や運用能力なども評価の対象にします。
評価方法ですが、全て数値化します。ディスカッションでは個人評価、ディベートはグループ評価になります。数値化することで評価者も採点しやすくなります。そして、同じ評価基準で聴衆(参加していないその他の学生)にも評価させます。何となくこの人がすごい、このチームが勝ちではなく、しっかりと根拠を示すためにも評価の数値化は大切です。
ディスカッションとディベートの有効活用方法
私は是非、母語以外の言語で行うことをお勧めしたいと思います。話し方を整えるには、限られた語彙数、表現の中で行ったほうが効果的だと考えるからです。例えば、日頃から延々とダラダラ喋れるわりに、結局何を言っているかわからない学生が日本語学校には時々います。そういう学生は「先生、こいつ、母語でも何言ってるかよくわからないんだよ」なんて友だちに必ず言われています。このような学生がディベートの授業を受け続けた結果、母語の話し方まで整った例があります。
日本語学校では、ディスカッションとディベートはどのように使われるか?
私は以前、日本語学校でディベートの授業を担当していました。そこでは、作文・会話・聴解など技能別授業の1つとして扱われていました。学校にもよると思いますが、ぜひ積極的に授業に組み込んでほしいと思います。また、ディスカッションも会話の1つとして扱っている学校は多いと思いますが、しっかり評価基準を決めて扱っている学校は少ないかもしれません。どちらも、やりっぱなしではなく、必ず数値化して評価をすることが大切ではないかと思います。
まとめ
ここでは、ディスカッションとディベートの違い、そして日本語教育現場での活用方法をご紹介いたしました。
最後に一つ、私から皆さんにお伝えしたいことがあります。それは、指導する人間は自分自身も実際にこれらを体験しておくべきだということです。調べれば、指導方法などは簡単に検索できる世の中になりました。しかし、頭でシミュレーションした内容で指導しようとしても、学生には何の説得力もなく、伝わりません。私はディベートセミナーに参加したり、ディベートの試合を積極的に見学に行ったりと、自分自身もいいディベータ―になる努力をしました。また、ディスカッションも就活生向けの動画などを何度も観たりしましたが、どんなものなのかは実際に体験しないとわかりませんでした。
実際にできない人間が評価など絶対にしてはいけないと思います。また、学生が楽しく参加していたからよかったで終わらせてもいけません。何のために授業でディスカッションやディベートを行っているのか、学生は何を身に着けたのか、どう成長したのかをしっかり伝えられる教師でありたいものです。
参考資料
松本茂『日本語ディベートの技法』(七寶出版)
占部礼二『面接とGD(グループディスカッション)をひとつひとつ。』(Gakken)

日本語初心者にひらがなの指導をするには? 書き取り練習?
文字を覚えるとはそもそもどういうことか。このようなことを考えたことがあるでしょうか。学校教育で習うものですが、体系的に教えてもらったという記憶が曖昧ではないでしょうか。字を自然に習得し、いつのまにか覚え、自分なりに規則性を見つけて獲得して来ました。そのため、「字を教える」ということを明確に説明できるは人なかなかいないと思います。日本語教師になっても字の教え方ってどうなっているの?となりがちです。字を教えるためのスキルやノウハウ、教材などがあふれています。それが字を覚えるということの一連の流れの、どのような位置づけにあるのかをまとめていきたいと思います。






