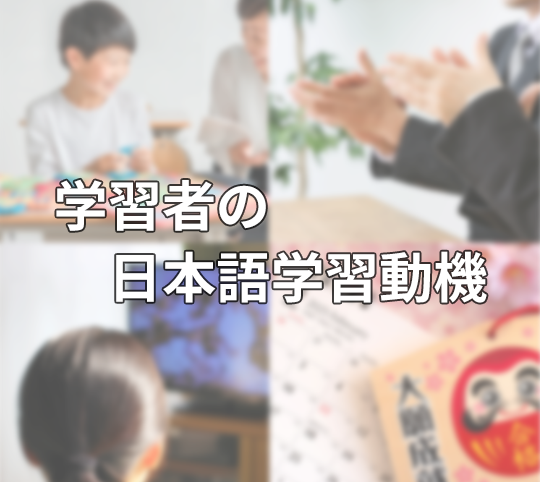ピジン、クレオール、リンガ・フランカの違い
ピジン、クレオール、リンガ・フランカの共通点とは?
ピジン、クレオール、リンガ・フランカはあまり馴染みのない言葉ですが、日本語教師なら知っていなくてはならない用語です。この記事では、この3つの言葉について説明します。
いきなり質問ですが、
ピジン、クレオール、リンガ・フランカの共通点とはなんでしょうか。
それは、どれも「言語接触」と関係があることです。
言語接触というのは、ふたつ以上の言語が接触して影響を与えあうことです。日本語にはあまり関係のないように思えますが、じつはこれはとてもありふれたことです。たとえば、日本語にたくさんの英語の語彙があるのは、日本語が英語と接触しているからです。
ですが、日本語と英語の接触は主として語彙の借用にかぎられる部分的なものです。そうではなく、異なる言語どうしが全面的に接触する場合もあります。そうした場合、人間は言語の壁を乗り越えコミュニケーションを取ろうと努力します。このとき生まれるのが、ピジン・クレオールであり、またリンガ・フランカです。
ピジンとは
大昔から、異なる言語の話者どうしで接触し、コミュニケーションをとる事態がたびたびあったことは疑いありません。そうしたとき、無言で物々交換していたというケースもあるでしょうが、多くは両方の言語に通じた「通訳」が仲立ちとなっていたものと考えられます。
ですが、そのような「通訳」もおらず、なおかつ強制的にコミュニケーションを取らざるをえない状況も、やはりいくども生じてきました。たとえば、交易・農作業・兵役・航海などの目的で多様な人々が一か所に労働力として集められる場合がそれです。
こうした場合、人々は、なんとか意思疎通を図ろうと、手持ちの語彙や文法を使ってありあわせの言語を作り上げたものでした。この間に合わせの言語が「ピジン(pidgin)」です。ピジンは一説には英語の「business」に由来するそうですが、まさしくその場の「ビジネス(取り引き)」のために生みだされた補助的な言語です。
ピジンはその場の用を足すためだけの言語ですから、習得に容易でなくてはならず、文法・語彙ともに非常に簡略化されています。また、ピジンを用いるのは、すでになんらかの言語を母語として習得している話者であるため、このピジンを母語とする話者はいません。さらに書き言葉としても用いられません。言語的には、動詞や名詞などの文法的活用がないという特徴をもちます。
歴史上、さまざまなピジンのあったことが知られています。とくに近代の植民地化にともなってアフリカ、中南米、カリブ海、太平洋諸島、アジアの各地でピジン英語やピジン・フランス語が生まれました。それらの多くは消滅しましたが、なかにはクレオールに発展してハイチ・クレオール(ハイチ)やトク・ピシン(パプアニューギニア)のように公用語にまでなった言語もあります。
日本語もまたピジンとは無縁ではありません。明治時代の横浜外国人居留地で用いられた横浜ピジンや、ハワイの日系移民の間で用いられたハワイ・ピジン英語などが知られています。
クレオールとは
ピジンはその場限りの交渉を目的として発生した言語でしたが、異なる言語話者どうしの交流が常態化する場合もありました。そうするとピジンの使用環境の中で、子どもが生まれ、成長することとなりました。
ピジンを母語とする話者はいないと書きましたが、これらの新しい世代にとってはピジンは母語です。子どもたちがピジンを母語として用いるようになると、ピジンは単なる補助的な言語を脱し、豊かな語彙を獲得し、十分な文法をもつ「普通の言語」へと発展します。クレオール(creole)とは、このように、ピジンから新しい世代の母語へと進化した言語を指す言葉です。
クレオールは日常生活のあらゆる場面の使用に耐える言語です。また文章語としても用いられ、国家の公用語の地位を得る場合もあります。
多くのピジンは植民地化の過程によって発生したため、各地のクレオールは当時の植民地支配国の言語(英語、フランス語、ポルトガル語など)の影響を強く受けています。たとえばパプア・ニューギニアのトク・ピシン(Tok Pisin)は、talk と Pidgin から成るその名の通り、英語をベースとするピジンの発展したクレオールです。語彙の 80 % が英語に由来し、文法にも英語の影響が強く見られます。“buk bilong mi” は「私の本」という意味ですが、英語の動詞 belong (〜に属す)がトク・ピシンでは所有(〜の)を表す前置詞として用いられています。
クレオールには、上に挙げたトク・ピシンのほか、ハイチのハイチ・クレオール(フランス語ベース)がよく知られています。また、日本語の八丈方言と英語から生まれた小笠原クレオール(小笠原諸島)や、日本統治下の台湾で生まれた宜蘭クレオール(ぎらんクレオール)も存在します。宜蘭クレオールは、台湾のアタヤル語とセデック語の話者たちが日本語をベースに発展させたものです。
ピジンとクレオールの研究は、言語の研究に大きな影響を与えています。クレオールはお互い無関係に成立したにもかかわらず共通点が多いといわれており、人間の言語能力の謎を解き明かすヒントがあると考えられています。また、日本語の起源や、アラビア語の方言の形成過程を論ずるさいにもピジンとクレオールが引き合いに出されることもあります。
リンガ・フランカとは?
現代世界では、英語は非常に広い地域で用いられており、その話者には英語を母語とする人もいますが、そうでない人も多いです。リンガ・フランカ(lingua franca)とは、英語のように、広範囲に広がり、また、さまざまな言語を母語とする話者が用いている共通言語のことです。(リングワ・フランカとも)。
似たような共通言語に、標準語や公用語があります。これらは多くの場合、国家や特定の組織などが定めたものです。これに対して、リンガ・フランカは国境に限定されません。ですので、国家の枠を超えて広がる場合もあります。このリンガ・フランカとなるのは、その地域で経済的にも文化的にも有力な言語であることがほとんどです。
リンガ・フランカとはそもそも「フランク人のことば」という意味で、近世以前の地中海世界の交易の共通語として用いられていたことに由来しています。このことからも分かるように、リンガ・フランカは交易や市場で重要な役割を果たしているため「通商語」と呼ばれることもあります。
古くは古代中東世界に広がったアラム語(セム語族、イエスが話した言語)や、中央アジアの交易に用いられたソグド語(インド・ヨーロッパ語族)がその好例です。
また現在でも、東アフリカのスワヒリ語(バントゥー諸語)、西アフリカ、中央アフリカのハウサ語(アフロ・アジア語族)、ミャンマー・中国で話されているカチン語(シナ・チベット語族)などのように、単なる通商目的だけでなく、さまざまな民族をつなぐ文化語として活発に機能しているリンガ・フランカもあります。
ピジン・クレオール、リンガ・フランカの簡単比較表

その他関連語
さて、ピジン、クレオール、リンガ・フランカ以外に、言語接触に関わる用語をいくつか見ていきましょう。
「言語の消滅」:言語接触の結果、話者数が激減し、言語が消滅することがあります。
「危機言語」:消滅の危機にある言語を危機言語と呼びます。日本ではアイヌ語、八重山語(八重山方言)、与那国語(与那国方言)などが危機言語とされています。
「言語圏」:言語接触の結果、類似した言語特徴を持つようになった言語群を言語圏と呼びなす。アルバニア語、ギリシア語、ブルガリア語、セルビア語、クロアチア語、ルーマニア語などが共通の特徴を持つバルカン言語連合がよく知られています。
まとめ
今回はピジン、クレオール、リンガフランカについて説明しました。ピジンは必要最低限の語彙と文法からなる補助言語、クレオールはピジンが本格的な言語に発展したもの、リンガフランカはさまざまな言語の話者が用いる共通語です。いずれも言語接触が原因となって生まれました。
ピジン、クレオール、リンガフランカからは、言語接触という困難の中、互いになんとかコミュニケーションをとろうとする人々の姿が浮かび上がってくるようですね。
参考文献
亀井孝他編『言語学大辞典第6巻 術語編』(三省堂、1996)
近藤安月子他編『研究社日本語教育辞典』(研究社、2012)
斎藤純男他編『明解言語学辞典』(三省堂、2015)
スザーン・ロメイン『社会のなかの言語―現代社会言語学入門』(三省堂、1997)
東京中央日本語学院日本語教員養成講座『日本語教師のための理論 社会・心理』(東京中央日本語学院、2019)
東照二『社会言語学入門―生きた言葉のおもしろさにせまる』(研究社出版、2009)
ヒューマンアカデミー『日本語教育能力検定試験完全攻略ガイド』(翔泳社、2021)
森山卓郎他編『明解日本語学辞典』(三省堂、2020)

あなたの考えるビジネス日本語とは
みなさんは「ビジネス日本語」についてどのように考えますか。職場で、生活している環境の中で、「働く外国人」の姿を多く見かけるようになったと感じることはありませんか。厚生労働省の調査によると、2023年10月末現在で外国人就労者の数は204万8675人、前年の同じ時期に比べると12.4%も増加し、過去最高の人数となっています。増加し続ける外国人就労者が日本で能力を発揮し、ストレスを感じず、よりよい仕事をしていくために必要なことのひとつが日本語の習得です。その、外国人就労者が働く上で必要な日本語の習得をお手伝いすることも日本語教師の仕事の一つです。外国人就労者の増加とともにビジネス日本語を教えることは今後日本語教師の仕事の大きな柱になっていくと思います。