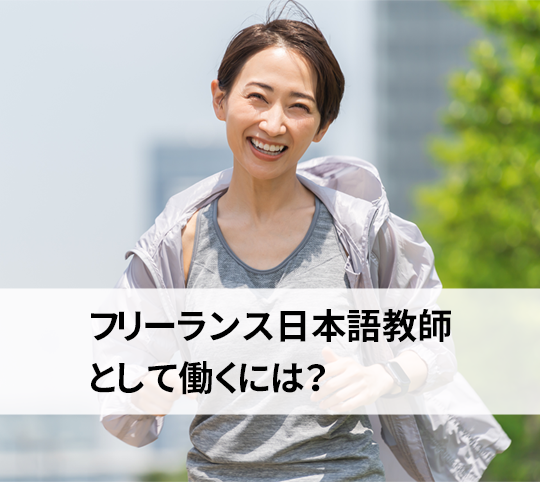受身形の教え方 なぜ受身形は教えるのが難しいのか
概要
今回のテーマは「受身形」。初級後半で学習することが多い項目ですが、活用を覚えれば使えるようになるかというと、そうでもありません。この記事では、受身形の種類と意味、また受身形が難しいと言われる理由や教え方のポイントについて解説します。
日本語教育における受身形とは
受身形はヴォイスの一種です。ヴォイスとは、出来事を述べるときの視点・立場を表現する言い方のこと。日本語教育では受け身、使役、使役受け身、授受表現などがあります。
例えば「ニンジンを食べる」という文を、異なるヴォイスで表現してみます。
(自分が食べようと思っていたのに、他の人に)ニンジンを食べられた。
(親が子どもに)ニンジンを食べさせた。
(野菜が嫌いなのに、母に)ニンジンを食べさせられた。
(野菜が嫌いなので、友達に)ニンジンを食べてもらった。
(野菜が嫌いな友達が残した)ニンジンを食べてあげた。
「にんじんを食べる」という行動を表しているのはどの文も同じですが、誰の視点から述べるかによって言い方が違いますね。
また、それぞれの表現で、中立的な事実描写から、被害や感謝を表現するものまであり、気持ちやニュアンスも異なります。
この中でも今回扱うのは「受身形」。受け身形にはどのような特徴やニュアンスがあるのでしょうか。まず、下の2つの文を比べてみましょう。
・AチームがBチームを倒した。(能動文)
・BチームがAチームに倒された。(受け身文)
前者が能動文、後者が受け身文です。「~された・~られた」などの形になるのが受身文ですね。
2つの文のニュアンスの違いはどうでしょうか。
両方とも述べている出来事は同じものですが、①はAチームの視点あるいは中立的に事実を述べている印象なのに対し、②の文では負けた側のBチームの視点から描写しているようです。おそらく話し手がBチームを応援していた場合には、②を使うことが多いのではないかと思います。
別の例も見てみましょう。
・冷蔵庫に入れておいたプリンを誰かが食べた。(能動文)
・冷蔵庫に入れておいたプリンを誰かに食べられた。(受身文)
こちらは後者の方が、残念だと感じている感情が伝わりやすいのではないかと思います。
・母が私を褒めました。(能動文)
・(私は)母に褒められました。(受け身文)
こちらは、どちらが自然に感じるでしょうか。どちらのほうが嬉しいと思っているように聞こえますか?
このように、受身文は単に能動文と形や語順が異なるだけでなく、特定のニュアンスや感情を伝えることがあります。具体的には、残念な感情や被害意識、あるいは何かをしてもらって嬉しいという感謝、動作の受け手に対する共感的態度などがあります。
受身形の種類とは
それでは具体的に、受身の種類について見ていきましょう。
1)直接受け身(他動詞のみ)
能動文の動作主(主語)と受け手(目的語)が入れ替わり、受け手が主語になる形です。
シンプルで分かりやすいので、文型の導入によく使われます。
例:娘が私を呼びました。
→私は娘に呼ばれました。
先生が山田君を叱りました。
→山田君は先生に叱られました。
2)間接受け身(自動詞・他動詞)
【自動詞の文】
・子どもが泣いた
→(私は)子どもに泣かれた。
・雨が降った
→雨に降られた。
これらの文は、対応する能動文にもともとヲ格がありません。
受身にするときに主語の「私は」が現れます。
【他動詞の文】
直接受け身と同じ他動詞の文(「AがBをV」の文)ですが、動作主と受け手が入れ替わるわけではありません。例えば、
・誰かが金庫のカギを壊した。
→(私は・私たちは)誰かに金庫のカギを壊された。
動作主をニ格にし、動詞が受身形に変わります。
※この文は直接受け身に書き換えることも可能です。その場合には、「金庫のカギが誰かに壊された」となります。
3)所有の受け身(足を踏まれた、スマホを見られた、財布を取られた)
間接受け身の一種で、主語と目的語の間に所有関係がある場合にこのような呼び方をします。
自分の体や所有物、自分と近しい関係の人などを動作の受け手として表現します。例えば、
能動文:誰かが私の足を踏みました。
→受身文:私はだれかに足を踏まれました。
能動文:隣の人が(私の)スマホを見ました。
→受身文:隣の人にスマホを見られました。
能動文:誰かが私の財布を取りました。
→受身文:私は誰かに財布を取られました。
というような文です。
4)迷惑受け身
特に他者の行為によって話者が迷惑を被ったときに使われる言い方を「迷惑受け身」といいます。③で紹介した例文も迷惑受け身の意味的要素がありますが、それ以外にも
・自分が買おうと思っていた最後の一つを、他の客に先に買われた
・一方的に電話を切られた
などの例が挙げられます。
5)それ以外(動作主が特定できない受け身)
史実やイベント・建造物などについて話すときにも受身形がよく使われます。
・オリンピックが開かれる
・東京タワーが建てられた
など。こちらは中立的な言い方で、感情が含まれない場合が多いです。
学習者への教え方
学習者への教え方の一般的な流れは、導入(受け身文の提示と意味の理解)→動詞の活用→文の作り方の導入と練習→会話などの応用練習です。
1)導入
まずは分かりやすい直接受け身の短い文を使って、受身形の基本の意味と形を導入します。
2)動詞のグループごとの活用を覚える
受身形の正しい活用が作れるように練習を行います。動詞のグループ分けの復習をしつつ、グループごとの活用の仕方を、視覚教材も用いながら理解します。
3)文の作り方
受身形の活用ができるようになったら、文の作り方に入ります。まずはシンプルな直接受け身の文から入れるとスムーズです。助詞の使い方に注目してもらいながら導入します。
先生は 私を 叱りました。
→私は 先生に 叱られました。
受身文では、能動文でハ格(もしくはガ格)で表していた動作主が、ニ格に変わります(先生は→先生に)。この語順と助詞の変化が混乱しやすいので、たくさん例文を作って慣れてもらう必要があります。例文は音読させるだけでなく、「誰がしますか?」と質問をして、動作主と受け手が誰なのか学習者に考えてもらうと良いでしょう。
また、ホワイトボードやパワーポイントを活用して語順の変化を矢印で示したり、教師が自ら動いて誰の立場から言っているのか視覚的に理解させながら例文を読んでいくと、理解してもらいやすくなります。
受身形の難しいポイント
学習者にとって、受身形のどこが特に難しいと感じられるのでしょうか。
受身形の難しさのひとつは、「誰が誰に」したのかが分かりにくいという点です。受身文では助詞や語順が変わるだけでなく、主語が省略されることもあります。「図書館に行ったら欲しい本が借りられていた」のような「誰が誰に」が明示されていない文は、受身文を学習したばかりの学習者には難しく感じられることがあります。
次に、「そもそも、いつ受け身を使うのかが分からない」というケースもあります。言語圏によっては、受身文自体をあまり使いません。例えば、日本語では「~って言われた」という場面でも、英語では”She told me..”や”He said..”のように能動文で表現するのが自然です。
日本語では自分が受け手になる場合、話者の視点を中心に描写する傾向があるため、「誰かが私に~をする」という能動文は使わず、自分を主語にして受身文で表現することが好まれます。
学習者の母語に似たような言い方や受け身文を使う習慣がない場合、そもそもどうして受け身を使うのかが分かりにくいことがあります。「理屈は分かったけど、結局いつ使うの?」ということにならないよう、いろいろな例文で話者の感情や状況を理解し、パターンを掴んでもらいましょう。
とはいえ、受身形は使い過ぎに注意が必要。特に迷惑受け身は他責的に聞こえることもあるため、どのような感情を伝える表現なのかよく理解してもらう必要があるでしょう。
・他の表現との使い分け
日本語では話者を受け手とした受身文がよく使われる点を前述しましたが、自分が受け手の時はいつでも受け身にすればいいかというと、そうでもありません。
△先生に日本語を教えられました
→○先生に日本語を教えてもらいました/教えていただきました
というように、自分が恩恵を受けた場合は通常「授受表現」を使います。実際の授業ではここまで細かく触れる必要はありませんが、講師が知識として知っておくとフィードバックに役立ちます。学習者が「子どもの時、母に絵本を読まれました」のような文を作った場合、なぜ不自然に聞こえるのかなど、説明できると良いですね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は、受身形について解説してきました。
今回のポイントは、
・受け身形はヴォイスの一種。誰の立場で言っているかを表す表現である。
・活用形を教えるだけでなく、助詞の変化に注目させる。
・そもそもなぜ受け身を使うのか、その文が伝える感情や、使う場面をよく理解してもらう。
という点でした。
実際の初級の授業では、受身形→使役形→使役受身形の順番で導入することが多いため、受身形がその後の導入事項の基本になります。しっかり受身形の内容をマスターして、授業に臨んでいきましょう。
参考
日本語教員養成講座教材チーム著(2019)『日本語講師養成講座 日本語教師のための理論 文法』.東京中央日本語学院
原沢伊都夫(2010)『考えて、解いて、学ぶ 日本語教育の文法』、スリーエーネットワーク