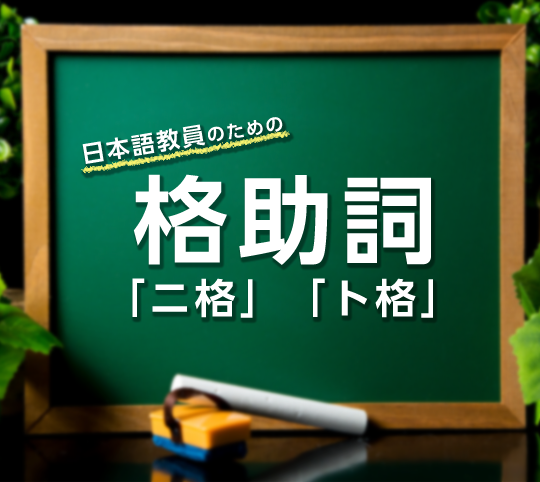日本語教師が教える!漢字指導のポイント「形・音・義」
概要
現代の日本で普通に生活するのに必要な漢字は約三千。その漢字を外国の人に教えるのはとても大変なことですよね。しかし、一つ一つの漢字が形・音(読み)・義(意味)という三つの要素をすべて持っていますので、目(形)、耳と口(音)、脳(義)と、人間の認知機能をフルに活用しながら学習することを考えてみましょう。
様々な国籍の学生がいる日本語学校で指導をしてきた、現役日本語教師が漢字指導のポイントを解説します。
漢字はおもしろい!
まずは単純な字の成り立ち(形)や意味(義)から始めて、「漢字はおもしろい!」と思ってもらうのが一番でしょう。それには、たとえば一・二・三や、上・中・下などの指事文字を紹介するところから始めてはどうでしょうか。ちょっと抽象的ですが、「なるほど!」と思ってくれるはずです。
また象形文字としての漢字も学生が興味を持つものなので木、山、川、月、日、目などの単純なものを教えるのもいいと思います。これらの字は構成要素としての利用価値も大きいので初期から教えるべきでしょうが、馬とか象・鳥・亀など意外と字形が複雑なものが多く、話題にする程度にとどめたほうがいいでしょう。
また「木」は象形文字で一本の木ですが、「林」は木がたくさん生えているところ、「森」は木が密集しているところ、と会意文字を紹介すると笑いをとることができるかもしれません。「木」が出たついでに「末」「本」も紹介しましょう。「火」から「炎」など、他におもしろいものを探せば、明・品などの例が見つかるでしょう。
漢字の三要素「形」「音」「義」
どんな漢字も「形」と「音(読み)」と「義(意味)」を持っていますので、「形」を知らないと書けない、「音」を知らないと声にだして読めない、「義」を知らないと意味が分からない、ということになります。したがって、どのような漢字でも、勉強するときはつねに「形」「音」「義」を意識して勉強させるようにするのが理想です。特に日本の漢字には、もともとの中国の音からきた「音読み」と、その漢字の日本語の意味からきた「訓読み」があるために、「音」と「義」とは深い関係にあります。
「販」という漢字を例に考えてみましょう。「販」は、形からいうと左が「貝」、右が「反」からできています。「貝」はまず象形文字で、子安貝。昔は貨幣として通用したことから、単独でお金や商業、経済などの意味を持っていて、右の「反」は「ハン」という音(読み)で、全体で”trade(あきない・うる)”を意味する漢字ですよね。多くの漢字が、このように左右や上下に分けられ、システマティックにできていることに興味をもつ学習者は非常に多いので、これを利用しない手はありません。読、銅、草、露などたくさんの例が挙げられますが これらは主として意味や属性を表す部分(偏など)と音を表す部分(旁など)からできているので形声文字と言われます。漢字の8割が形成文字といわれるほど多いので、まず形をみて、上下左右に分けて考えることができるか、そしてその構成要素から意味・属性、さらに音と類推していく力を養成すること、これが将来の応用のためにも非常に重要だと思います。
少し漢字の力がついてきたら、ある漢字の構成要素に注目させ、形・音・義のそれぞれが分かるかどうか訓練をすることで、さらに漢字力を複合的にアップさせていくことができます。簡単な漢字から始めて、他の漢字の構成要素となるような基本的な字(あるいは単漢字の中の構成要素)を覚えさせ、ひいては部首という概念を理解させて、最終的には自主的に漢字の辞書を引かせるところまで発展させていきます。
なお、筆順や画数については、黒板に実際に書いてみせるのが基本ですが、今ではZOOMやVoovなどに付属するホワイト・ボードを使いながら、先生と学生が同時に書く授業が可能になっています。
熟語の構成を考える
漢字は一字で使われるだけでなく、二字、三字の熟語として使われることが多いので、単漢字の前後の関係から、熟語全体の意味を類推する(演繹)の訓練、全体から単漢字の意味や用法を考える(帰納)の訓練も有効です。こうした双方向からの熟語の学習は、応用力をつけるためには極めて重要です。
参考までに二字熟語の構成について、例を確認しながら考えてみましょう。
・似た意味の漢字を重ねたもの(救助、善良、減少、学習 寒冷etc.)
・対になる意味の漢字を続けたもの(上下、強弱、進退、断続、売買etc.)
・主語、述語の関係にあるもの(骨折、雷鳴、音響、官製、腹痛etc.)
・前の漢字が動詞、後ろの漢字が目的語(消火、登山、読書、唱歌etc.)
・前の漢字が後の漢字を修飾するもの(高価、軽傷、牛肉、花束、厳禁etc.)
・前の漢字が後の漢字の意味を打ち消すもの(不満、未定、否認、非常etc.)
さらに三字の熟語、四字熟語へと学習が進めば、学生の漢字の世界が大きく広がることでしょう。ただ、熟語は当然ながら漢文(古い中国語)の文法構造をもっているわけで、中国人から見れば、「音」は違っても、「形」「義」は中国語として理解できるでしょう。その点、他の国から来た人への配慮が必要といえます。
漢字文化圏と「形」「音」「義」
もともと文字を持たなかった日本人は、当時先進的な文明をもっていた隣国・中国から文字(漢字)を仕入れ、長い時間をかけて、自分たちの言語(日本語)を表記するのにふさわしい方法を編み出し、現在の「漢字かな交じり文」を作り出しました。つい最近まで学校でも漢文(中国の古典・古語を日本語の語順に置き換えてよむ訓読法)を教え、大学の入学試験にも出題されていたことを覚えている方も多いと思います。
日本語学校の教室には、まったく漢字を使わない欧米や東南アジアなどの国から来た人々、中国のように「漢字の本家」から来た人、さらに昔は漢字を使っていたが今はまったく使わなくなった国々から来た人など、漢字に関してだけでも多種多様な人々がいます。
中国から来た学生に象形文字や形声文字の説明をする人はいないように、できるだけ、それぞれの学生の出身に応じた漢字指導をするほうが効果的です。そのために漢字入門の特別授業をしたり、個別に取り出し授業をやったりしますが、入門期が終わって一緒に授業をするようになっても、出身国の母語によって漢字の理解に大きく違いがあることを頭の隅に置いておく必要があります。
中国・香港・台湾からの学生
日本人は中国語の新聞の漢字をみて、なにが話題かぐらいはだいたいわかりますね。中国の人も日本の新聞をみて、同様に思うでしょう。それは漢字の「形」と「義」がおおむね共通しているからですが、新中国になってから大陸では識字率向上のために「簡体字(簡略化された字体)」を制定し、それを徹底的に通行させました。日本の漢字にも略字体がありますが、それとはまったく別のルールで簡略化されていますので「形」はかなり違います。台湾は第二次大戦後、北京にあった国民党政府が台湾に移ったために、「音」は大陸の普通話(共通語)とほぼ同じですが、漢字の「形」は日本でいう「旧字・繁体字」が使われています。香港は「音」は広東語、「形」は台湾とほぼ同じ「旧字・繁体字」です。
中国・香港・台湾から来た人は、日本の漢字と「形」「義」が近いために学習に有利ですが、その分「音」に悩まされます。なぜかというと、中国では基本的に漢字一字の「音」は一つです(二つ、まれに三つある場合もありますが、それは「多音字」といって例外的です)。それに比べて日本の漢字は漢音、呉音、訓読みなど、一つの漢字の「音」が非常に多い。そのためひどく複雑に感じるのです(実際、複雑ですよね)。
もう一つ、中国・香港・台湾からの学生には「同形異義語」に注意させるようにしてください。日本語と中国語で、漢字の「形」は同じでも、「義」がまったく違ったり、微妙にズレがあったりする言葉があります。「湯」「手紙」「大家」「愛人」「百姓」などは有名ですが、「勉強」「迷惑」「約束」「工作」「小心」などなど、日中双方で気をつけなければならない言葉が意外に多いので注意が必要です。作文や読解の時にその差が現れやすいので、うっかり通してしまわないで、そのつど指導するようにします。語感の鋭い学生は、なんか変だな、と気がつくかもしれませんが、ちゃんとした指導が必要なところです。
さらに日本語としてはかなり難しい漢字のために、必要以上に丁寧に語義(意味)を説明したりすることもあります。たとえば「拘泥」「躊躇」「範疇」などがそうです。中国人なら「形」をみて「義」がわかりますので、こういう言葉は、「こうでい」「ちゅうちょ」「はんちゅう」と読みます、と「音」を教えておしまいです。
韓国、ベトナムからの学生
朝鮮半島の国々は中国、漢字文化の影響が大きく、知識層を中心に長い間、漢字を使っていましたが、15世紀になって民族固有の文字・ハングルが作られ、次第に「漢字ハングル交じり」の文章が書かれるようになりました。ですから新聞に書かれた文章も、日本人なら漢字を拾い読みしてテーマぐらいは分かったものですが、1970年、朴正煕大統領が漢字廃止宣言を出し漢字教育を全廃したため、以後まったく漢字が使われなくなり、現在では自分の姓の李・金・朴などの漢字すら書けない若者が多くなっています。
しかし、言葉としては漢字語(漢字の熟語)が多く残っているために、韓国語ができない私でも、彼らの会話の中から、トショグァン(図書館)、コーソクトロ(高速道路)、チュモク(注目)などの韓国語の「音」を容易に聞き分けることができます。韓国語の単語の7割は漢字語で構成されていると言われていますので、韓国の学生は、漢字の「形」は分からなくても、日本語の「音」から意味(義)を類推することがある程度可能です。ですから単語によりますが、その言葉の「音」と「義」から、漢字の「形」へと指導すると効果的なことがあるので、そのことを頭に入れておきましょう。
ベトナムも古くから中国文化の影響が強く、長らく漢文が正式な文章として使われていました。その後民族意識が高まり、漢字をもとに独自の文字・字喃(チュノム)が作られましたが、あまり長続きしませんでした。そしてフランスの植民地化とともに、ベトナム語をローマ字化したものが「クオックグー(国語)」と呼ばれて普及し、次第に漢字は使われなくなり、現在に至っています。
しかし韓国語と同じように、言葉としては漢字語(漢字の熟語)が多く残っていて(辞書に載っている単語の半分以上が漢語系の語彙と言われている)、ルェンアイ(恋愛)、ケヤク(契約) 、タイドゥ(態度)、クアンリー(管理)など、日本語に似ているものもかなり見られます。ベトナムからの学習者も、日本語の熟語の「音」を聞いて、ベトナム語に近いものがあることを意識するでしょうし、またそのように指導すると進歩が早いでしょう。
まとめ
漢字は中国が「本家」ですが、その本家自体、時代や地域の影響で形・音・義に変化が起こっています。もちろん「分家」の日本、朝鮮半島、ベトナムの漢字も時代とともに独自に変化してきているわけです。本来、残りやすいはずの文字(形)は、その国の政策で大きく変わり、言葉そのもの、つまり変わりやすいはずの「音」と「義」が意外と残って、共通であったり、似ていたりしているものがあります。
日本語を教える際に以上のことを頭に置いておくと、学生たちの理解を容易にしたり、思わぬ共感を呼び起こしたりすることがあるに違いありません。中国音を知っている指導者なら、さらに多くの共通点を発見できることでしょう。
参考
『漢語林』鎌田正/米山寅太郎著 大修館書店
『日中同形異義語辞典』王永全/小玉新次郎/許昌福編著 東方書店
『漢語と日本人』鈴木修次著 みすず書房
『漢字民族の決断』橋本萬太郎/鈴木孝夫/山田尚勇編著 大修館書店
『1日15分の漢字練習 初中級』KCP地球市民日本語学校編 アルク
TCJ日本語教員養成講座
TJCでは、上記で述べたような多様な学習者に対応できる優秀な日本語教師を育成するために、充実した養成講座を開設しています。420時間コースの受講生は、併設の日本語学校の授業見学、ディスカッション型ワークショップ、現役日本語教師による特別講演会やセミナーなどに参加して、指導者としての実力をつけることができます。
毎週、現役日本語教師による特別講演会やセミナーなどのイベントも実施しているので、日本語教員養成講座を検討されている方はぜひ参加してみてください。

インプット仮説(i+1)を改めて考えてみよう
今回は、インプット仮説(i+1)を改めて考えてみようと思います。まず、インプット仮説(i+1)が何かについて解説し、問題点について説明していきます。さらに、実際の授業でやっている例を紹介します。その後、i+1やインプット仮説というワードが日本語教育能力検定試験に出るかということについても述べていきます。