

【保存版】格助詞とは?格助詞・ガ格、ヲ格のポイント
そもそも「格助詞」とは、一体何でしょうか。この記事では、資格試験の頻出事項であり、日本語教師としてもマスターすべき格助詞とは何か、10種類の格助詞の覚え方、そして「ガ格」と「ヲ格」について、わかりやすく説明します。
格助詞とは、ズバリ何か?
国語辞典によると、格助詞とは体言または体言に準ずる語に付き、その語が他の語に対してどのような関係に立つかを示すもの。わかりやすく言えば、格助詞とは、主に名詞の後ろにくっついて、その名詞がどのような働きをするのかを示す語のことを言います。例としては、「が」「を」「に」などが挙げられます。
英語と比較してみましょう。”I eat fish.”という文では、語順のおかげでI が主語、fish が目的語だと簡単にわかります。でも、日本語で「私 魚 食べる」と言っただけでは、「私が 魚を 食べる」なのか、「私を 魚が 食べる」なのか、意味が曖昧です。
この違いを明確にするのが、格助詞「が」や「を」です。語順の自由度が高い日本語にとって、文の意味を理解するために、格助詞は必須アイテムなんです。
格助詞は全部で10個。覚え方を伝授!
日本語の格助詞は、全部で10個あります。具体的にどんな格助詞があるのか、代表的な用法と共に見ていきましょう。※注意:用法は代表的なものを紹介しています。詳細はそれぞれの記事でご確認ください。
1. が:主体を示す
(例)子どもが歩く。
2. を:動作の対象を示す
(例)音楽を聞く。
3. に:時間、方向、目的を示す
(例)図書館に3時に、勉強しに行く。
4. で:場所、手段を示す
(例)車で行く。
5. へ:方向を示す
(例)学校へ行く。
6. から:起点を示す
(例)朝から勉強する。
7. まで:到達点を示す
(例)夜まで仕事をする。
8. の:所有・連帯修飾を示す
(例)先生のかばんです。
9. と:共同・並列を示す
(例)母と話す。
10. より:比較・基準を示す
(例)大阪より、京都のほうが寒いです。
さて、この10個の格助詞、日本語教員試験や日本語教育能力検定試験などでは暗記必須!今日は、私が実際に使った「格助詞の覚え方」を2つご紹介します。
まず1つ目は…
「鬼が戸より出、空の部屋」
(ヲ・ニ・ガ・ト・ヨリ・デ・カラ・ノ・ヘ・ヤ)
想像してください。鬼がドアから出て、その後、空っぽになった部屋を。
これは私が日本語教師養成講座の受講中に、担当の先生から教わった語呂合わせです。格助詞の覚え方の王道です。
そしてもう1つ…
「鬼が夜からデートやの!」
(ヲ・ニ・ガ・ヨリ(夜)・カラ・デ・ヘ・ト・ヤ・ノ)
ウキウキわくわく嬉しそうな赤鬼が鏡の前でメイク中…。聞いてみると、今晩デートだそうです!
格助詞「ヨリ」が「夜(よる)」となっていたり、「デ」「へ」「ト」で「デート」だったり、最後もなんとなく関西弁っぽかったり、あれこれ無理はあるのですが、何よりインパクトがあって頭に残りやすい!こちらもおすすめの格助詞の覚え方です。
格助詞「が」の教え方
外国人学習者にとって、助詞のマスターは大きな壁。現在、私は日本語教師として日々教壇に立っていますが、指導レベルを問わず、助詞について触れない日はありません。だからこそ、教える側には、わかりやすい例文と共に、用法を明確に指導できる能力が求められるのです。それでは、格助詞の代表選手、ガ格とヲ格を詳しく見ていきましょう。
【ガ格】格助詞「が」の用法は、主に2つです。
1. 主体
2. 対象
1. 主体/Subject
述語が示す動きが、誰によって(もしくは何によって)行われているかを明確にします。通常は文の主語を表します。
○動きの主体
(例)・雨がふります。
・友だちが家に来ます。
○状態や性質の主体
動きだけでなく、述語の状態や性質が何によってもたらされているかも示します。
(例)・パソコンがあります。
・日本人の友だちがいます。
・部屋がきれいです。
2. 対象/Object
述語が感情や感覚を表すとき、どんな対象によってその感情や感覚がもたらされているのかを示します。また、願望「ほしい/〜たい」、能力「できます/可能形」の対象も「が」を使って表せます。
(例)・旅行が好きです。(感情/感覚)
・地震が怖いです。(感情/感覚)
・頭が痛いです。(感情/感覚)
・新しいスマホがほしいです。(願望)
・新しい映画が見たいです。(願望)
・英語ができます。(能力)
・英語が話せます。(能力)
○教え方のコツ
初級文法の「あります」「います」「好きです」「ほしいです」などを教える際は、動詞や形容詞などの述語を単独で教えるのではなく、「〜があります」「〜が好きです」など、格助詞をセットにして教えましょう。学習者が助詞を間違えることが、グッと少なくなりますよ!
格助詞「を」の教え方
【ヲ格】格助詞「を」の用法は、主に3つです。
1. 対象
2. 起点
3. 経過域
1. 対象/Object
他動詞の動作の対象を表します。動詞「食べる」の場合、「何を?」の部分です。
(例)・日本語を話します。
・漢字を書きます。
2. 起点/Starting Point
移動動詞の出発点を表します。
(例)・家を出ます。
・日本を出発します。
なお、卒業や退職なども意味を拡張させた「出発」だと捉え、起点の「を」を使います。
(例)・大学を卒業します。
・会社を辞めます。
3. 経過域/Route of Action
移動動詞の通過する場所や経路を表します。また空間的な経過だけでなく、時間的な経過でも使えます。
(例)・橋を渡ります。
・公園を散歩します。
・夏休みをスペインで過ごします。
○教え方のコツ
学習者が混乱しやすいのは「起点」と「経過域」の用法。日本語教師としては、格助詞「を」と結びつく以下のような移動動詞を、パッと紹介できるようにしておくと便利でしょう。
【移動動詞/起点】 出る、出発する、去る、離れる、など
【移動動詞/経過域】 歩く、走る、通る、渡る、曲がる、進む、泳ぐ、飛ぶ、散歩する、ドライブする、など
ちなみに、初級クラスの学習者から「公園を 散歩します」と「公園で 散歩します」はどちらが正しいですか?と質問を受けることがあります。
質問に対する答えはどちらも正解!ただ、違いはあります。
「散歩する」「泳ぐ」「走る」などの動詞は、移動と共に、動作も表します。ですから、移動している場所を言いたいときは「を」、動作が行われている場所を言いたいときは、格助詞「で」が適切なんです。
格助詞じゃない「が」もある?! 4つの助詞のカテゴリー
「が」「を」以外の格助詞については別記事でご紹介するとして、格助詞の他に、そもそも助詞には、どんなカテゴリーがあるのかチェックしましょう。日本語の助詞のカテゴリーは全部で4つ。「格助詞」以外には「接続助詞」「副助詞」「終助詞」があります。
でも、日本語教師養成講座で「接続助詞」や「副助詞」という言葉をあまり耳にしたことがないな、と思われた方がいるかもしれません。実は、この4つの分類は国語文法の分類。外国人学習者に教える日本語文法では、「接続助詞」と「副助詞」は文型として学習するんです。今回はそれを踏まえて、ざっくり中身を見てみましょう。(以下、定義は国語辞典『大辞林4.0』三省堂 より)
接続助詞:用言・助動詞に付いて、それより前の語句を後の語句に接続し、前後の語句の意味上の関係を示すはたらきをするもの。
(例)・まっすぐ行くと、デパートがあります。
・少し高いけれど、買います。
・遠いですが、問題ありません。
副助詞:種々の語に付いて、下の用言や活用連語の意味を限定するはたらきをもつもの。
(例)・あなたさえいれば、私は幸せです。
・息子は、ゲームばかりしています。
・3日間だけ、運動をしました。
終助詞:文の終わりにあってその文を成立させ、疑問・詠嘆・感動・禁止などの意を表すもの。
(例)・週末、どこに行きましたか。
・ろうかを走るな。
・この本、おもしろかったよ。
お気付きの通り、助詞「が」は、格助詞だけでなく、接続助詞でもあり、接続助詞「が」の中にも複数の用法があります。こういったものは、学習者が意味を取り違えやすく、日本語教員試験などでも狙われやすいポイント!日本語教師としては、カテゴリーを正しく見極められるのはもちろん、それぞれの細かな用法の違いまで識別できる必要があるのです。
まとめ
資格試験合格はもちろん、日本語教師としても必須の助詞。学習者から突然質問されても、適切に指導できるよう、それぞれの助詞の用法と典型的でシンプルな例文を、頭にしっかりインプットしておきたいですね。この記事が、みなさんの日本語指導のお役に立てば幸いです。
参考
庵 功雄, 高梨 信乃, 中西 久実子, 山田 敏弘 (2000)『初級を教える人のための日本語文法ハンドブック』松岡弘監修, スリーエーネットワーク
日本語記述文法研究会編 (2009)『現代日本語文法2 第3部格と構文 第4部ヴォイス』くろしお出版

わかりにくいでお馴染み、モダリティの基本を解説!
「日常生活で聞いたことない日本語教育関連用語 No. 1」といえば「モダリティ」でしょう。この記事では、そんな「モダリティ」というムズカシげな用語を取り上げ、モダリティの意味、分類、日本語教育との関連などについてまとめました。

助数詞は日本語だけ? 広がる助数詞の世界!
この記事では、助数詞を取り上げます。分類や文法的特徴、世界の助数詞について日本語教育の観点からまとめました。
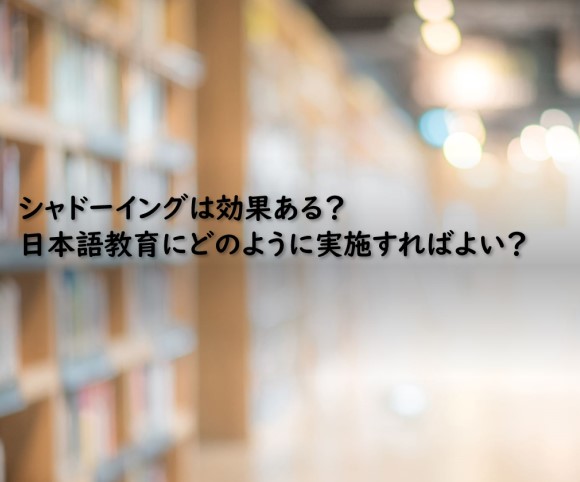
シャドーイングは効果ある?日本語教育にどのように実施すればよい?
シャドーイングは、音声を聞きながら同時に発生する練習です。 日本では英語学習の際に実施した人は多いのではないでしょうか? 日本語学習においても同様に効果的であるため、日本語教育の現場 において、どのようシャドーイングを導入していくかを解説します。





