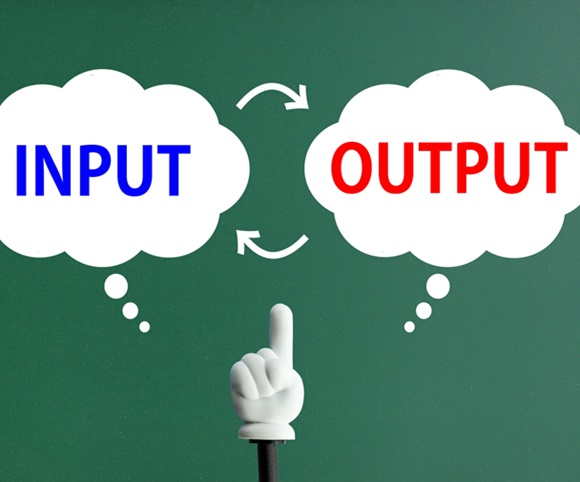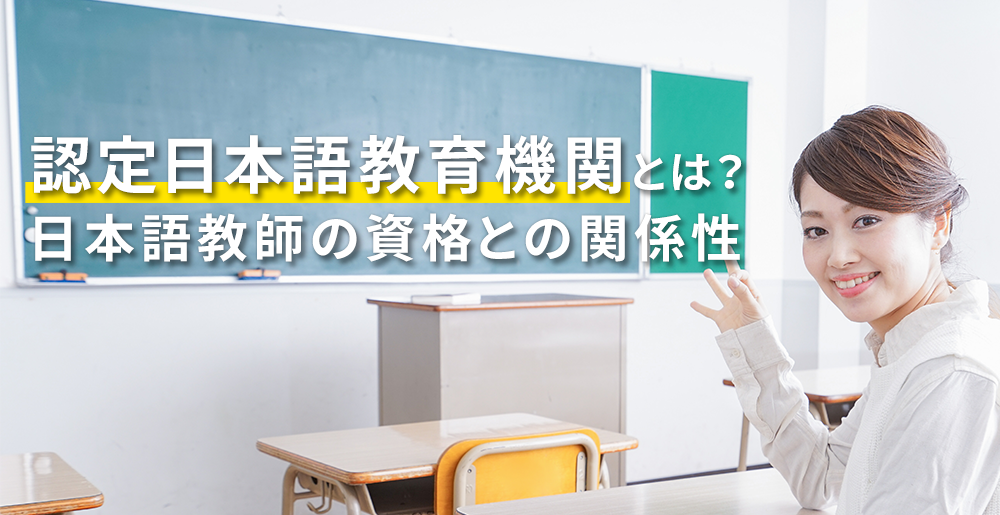
認定日本語教育機関とは?新制度のキーワードを解説
概要
2024年、日本語教師の国家資格化とともに「日本語教育機関認定法」という新法案が施行され、日本語教育機関にも新たな認定制度が設けられることとなりました。この記事では、認定日本語教育機関とは何か、これまでとどのような点が異なるのか、また、日本語教師の資格との関係性について解説します。
認定日本語教育機関とは?
2023年、「日本語教育機関認定法」が成立し、2024年4月に施行されました。この法案によってこれまで民間資格だった日本語教師は国家資格となり、留学生を受け入れる日本語学校などの日本語教育機関についても、新たな認定要件が定められることになりました。
これまでの日本語学校の認定制度は「法務省告示校」と呼ばれるもので、主に留学の在留資格で来日する留学生を受け入れる機関を認定する制度でした。
しかし今回の新法案では法務省から文部科学省に管轄が変わり、内容も「日本語に通じない外国人が我が国において生活するために必要な日本語を理解し、使用する能力を習得させるための教育」を目的とした認定制度になりました。
新制度では、様々な目的で来日した外国人の教育を包括できるよう、「留学」「就労」「生活」の3分野で認定が行われます。日本語教育機関はこの3つのうちいずれか、あるいは複数の分野で認定申請をすることができ、認定を受けた教育機関は「認定日本語教育機関(以下「認定校」)」となります。
留学生を受け入れられるのは、「留学」の分野で認定を受けた認定校だけです。既に旧制度の「告示校」として認定を受けている機関については法施行から5年間(2029年3月まで)の移行措置期間が設けられていますが、この時点を過ぎて認定日本語教育機関になっていない教育機関は、留学生の受け入れができなくなります。
留学生の場合、ビザの発給に所属先の学校が関わるため、国の認定を受けた機関でなければ留学生の引受人となることはできません。
一方、就労者や生活者については、認定校であるかないかにかかわらず受け入れが可能です。これは、就労・生活分野で日本語教育を受けるのは主に社会人で、就労ビザや家族滞在などのビザで来日する人たちだからです。社会人の日本語教育は習い事のような扱いであり、来日の主たる目的ではないため、ビザの発給に日本語学校が関与しません。そのため、日本語教育機関が留学生を受け入れるには認定を取ることが必須ですが、就労・生活の分野では認定がなくても外国人の受け入れができるのです。
とはいえ、就労・生活の分野では認定が全く不要というわけではありません。認定をとることで学校の信頼性が高まり、学生を集めやすくなったり就職支援がしやすくなったりするというメリットもありますから、いずれの分野でも認定を受けることが教育機関にとって望ましいと言えます。
※なお、この新法案の適用範囲は主に国内。海外の日本語教育機関は認定の対象ではありません。
・登録日本語教員との関係
これらの認定校で就労する日本語教師は、雇用形態に関わらず「登録日本語教員」の資格を持っていなければなりません。教師資格に関しても5年間の移行措置期間があり、2029年までは現行のまま就労することが可能です。しかし2029年以降に認定校で就労する場合には国家資格の取得が必須になります。
なお、個人事業として日本語を教える場合や、地域の日本語教室・学校の支援員として教えるなどの場合には登録日本語教員の資格取得は義務付けられていません。
海外在住の日本語教師で、海外からオンライン授業などの担当をメインに日本国内の学校で働きたいという場合もあるかと思いますが、「留学のための課程」では海外の教員を配置することが認められていません。つまり、教師が海外在住の場合、登録日本語教員の資格を持っていたとしても、国内の認定校で留学生を教えることはできません。ただし、「生活」「就労」の分野では一部オンラインによる実施が認められるため、海外からでも就労が可能な場合があります。
「留学」の認定基準
認定校になるには、どのような認定基準が設けられているのでしょうか。
まずは「留学のための課程」について見ていきましょう。
(参照:留学のための課程を置く認定日本語教育機関等の認定等について)
【組織体制】
・校長・主任教員を置くこと
・教員数は、収容定員20名につき1人以上、本務等教員(いわゆる専任)は定員40人につき1人以上
・教員1人あたりの担当授業時間数は週25単位時間以内(指導歴や他の業務量によって適切な時間数を定める)
・事務の担当職員がいること
・情報公開・自己点検・研修などの制度を整えること
【校舎環境】
・校地・校舎の近くに風俗店などがなく、教育・保健衛生上適切な環境であること
・校地・校舎が自己所有かそれに相当するものであること
・教室・教員室・事務室・図書室・保健室等を置く
・校舎面積は、115㎡以上かつ同時に授業を行う生徒1人当たり2.3㎡以上
・定員に対し必要な教室数・環境がある。机・椅子・黒板等を備え、授業を行う生徒1人当たり1.5㎡以上の面積であること
【日本語教育課程】
・修業期間は1年以上、原則35週にわたること。
・授業時数は1週間20単位時間以上、年間760単位時間以上(1単位時間は45分以上)で、卒業要件として760単位時間以上×修業期間の年数以上の授業科目の履修に加え、試験などの要件を設けること。
・B2以上を目標とし、課程の中に、話す・聞く・読む・書くの4技能を含めること
・同時に授業を行うのは20人以下
・生徒数は教員数、施設・設備等の条件に応じた適切な数(開設時は100 名以内)とし、課程全体の定員を超えて生徒を受け入れない
・授業は、講義、演習、実習もしくは実技のいずれか、または併用により行う
・日本語教育課程以外にも、アカデミック・ジャパニーズや学部・学科の学修につながる内容を取り入れることができる
【支援体制】
・母語支援等、学習に必要なサポート体制を整備すること
・生活指導担当者を置き生活や進路の指導を行うとともに、地方公共団体等の公的機関との連携を行う
・健康診断などを行うこと
・在留継続のためのサポートを行う
【自己評価・点検】
・自己評価の実施・公表をしなければならない
・審議会による実地視察を実施し、努力義務として第三者評価を行う
・毎年教育の実施状況について定期報告を行う
「就労」「生活」の認定基準
次は「就労のための課程」「生活のための課程」です。
(参照:留学のための課程を置く認定日本語教育機関の認定等について)
【組織体制】
・主任教員を一人配置すること
・同時に授業を行う生徒20人につき教員が1人以上(最低3人)、同時に授業を行う生徒40人につき常勤1人以上(最低2人)を置く
【校舎環境】
・校地・校舎が自己所有またはそれに準じたものである
・教室、教員室、事務室、図書室、保健室等を備えること。ただし図書室と保健室は条件付で不要
・同時に授業を行う生徒1人当たり面積1.5㎡
・机、椅子、黒板、視聴覚教育機器、図書等を備える
【日本語教育課程】
・B1以上の目標課程を1つ以上置くこと
・B1は350時間、A2は200時間、A1は100時間以上の授業時間数を確保すること
・4分の3を上限にオンライン授業を実施可能
・一定の基準を満たし、企業や地方公共団体等の他者と連携して授業を行う場合、校舎以外での授業実施が可能
・生徒数は教員数、施設・設備等の条件に応じた適切な数とし、同時に授業を受ける生徒数は原則20人以下
・課程の中に、話す・聞く・読む・書くの4技能を含めること
・授業は、講義、演習、実習もしくは実技のいずれか、または併用により行う
・各課程の目的及び目標に応じ、生徒の日本語能力に応じて適切な授業科目を体系的に開設
・上記授業時数以上の日本語教育に加え、日本語教育課程に支障のない範囲内で専門教育等の科目を開設可能
【支援体制】
・情報提供や他機関との連携をして生活支援を行う体制を整える
・「就労」→外国人を雇用する事業主等との連携、「生活」→地方公共団体等との連携体制をつくること
【自己評価・点検】
・自己評価の実施・公表をしなければならない
・審議会による実地視察を実施し、努力義務として第三者評価を行う
・毎年教育の実施状況について定期報告を行う
抜粋して記載していますが、概ねの体制は「留学のための課程」と同じです。しかし、勉強を主たる目的として来日する留学生のための課程と比べると、就労・生活では求められる日本語レベル・時間数が異なり、学習内容についても幅を持たせられるようになっています。また、学習場所についてもオンラインや学校外の場所での実施が認められているなど、社会人の生活に合わせたものとなっています。
24年度の認定結果について
昨年2024年(令和6年)に、第一回目の日本語教育機関の審査が行われました。日本語教育機関認定法のもとで初めて行われた今回の審査で、国に申請があったのは合計72件。しかしながら、そのうち認定されたのは「留学のための課程」の22件のみでした。そのほかは不認定が3件、継続審査(※)が11件、審査中の取り下げが36件で、7割近くが不認定という結果になりました。今回認められた機関は「留学のための課程」のみで、それ以外の「就労」「生活」での認定はゼロでした。
(※認定可能とするには不足があるものの、短期間でいくつかの項目の是正が可能であると期待されるため、申請者が希望すれば当該申請期間に申請があったものとして継続して審査を受けられる機関。)
審査を行った中央教育審議会日本語教育部会の所見によれば、申請した機関の多くで、新制度で求められている教育内容を十分にカバーできていなかったことが原因だとのこと。校地・校舎が設置者の自己所有でないという環境面や債務過多などの経済面で不十分と見なされたものもあったようで、日本語学校の準備不足が指摘されていました。
2024年7月現在の文科省のデータでは、国内の日本語教育機関は2,764機関。30年前の1990年(平成2年)の821機関と比べると、実に3倍以上に増えています。
今後も留学生の増加とともに教育機関の数も増えていくことが予想されます。新制度の移行措置期間である2029年までに認定日本語教育機関にならなければ、日本語学校は留学生の受け入れができなくなります。今回の厳しい結果を受け、今後申請する機関もなお一層の教育内容の充実、教員配置や校地・校舎、金銭面などあらゆる部分において準備が求められるでしょう。
まとめ
いかがでしたか?今回は新制度下での日本語教育機関の認定基準や現状について解説してきました。まだ始まったばかりの制度ですので、今後さらに日本語教育機関を取り巻く状況が変化していくことと思われます。今後の動向について、こちらのコラムでは引き続き、今後の日本語教育業界の動向について発信していく予定です。ぜひ、他の記事も合わせてご覧いただけたらと思います。