
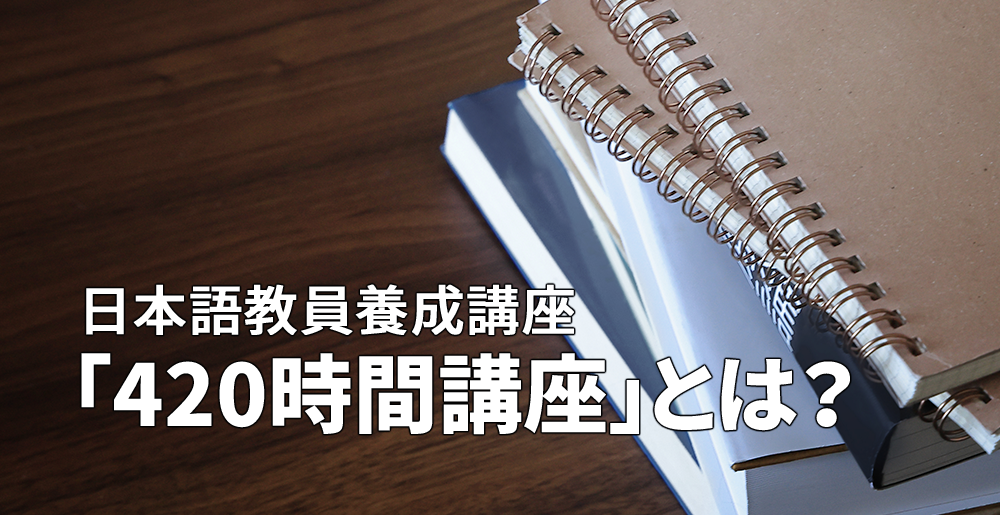
420時間とは…?日本語教員になるための勉強内容をご紹介!
概要
日本語を教える専門職として注目を集めている「日本語教員」。関心を持ち始めたら、日本語教員について調べているとよく出てくる「420時間」ってどんなもの?と疑問を持った方もいるのではないでしょうか。この記事では、この420時間という数字は一体何なのか?どんなことを勉強するのか?について解説していきたいと思います。
420時間って何…?
1)「420時間養成講座」とは
「420時間」というのは、日本語教員の国家資格化に関する法改正が行われる前の制度(文化庁届け出受理講座)で定められていた、日本語教員になるために必要な学習時間数です。
この時間数は新制度(登録日本語教員養成機関・登録実践研修機関)でも基本的に踏襲されています。新制度での養成講座は、375時間以上の理論学習と、45時間の実践研修(=420時間)で構成されるのが一般的です。
理論ではまず一般的な言語学・日本語学に関する知識と教育・社会・心理・異文化理解などの周辺知識を学び、その後に具体的な教え方や授業計画など、教壇に立つための実践的な内容を学びます。
2)養成講座を受けると、資格が得られるの?
これまでの制度では日本語教師は民間の資格であり、420時間の養成講座の受講・修了だけで日本語教師の資格が取得できました。しかし2023年の法改正(「日本語教育機関認定法」の成立)によって日本語教師が国家資格(登録日本語教員)になり、2024年度以降は国家試験「日本語教員試験」の受験と合格が必須となりました。したがって、養成講座を受講する場合でも、それと並行して国家試験を受験しなければ資格が取得できません。
しかし、養成講座を受講・修了することで国家試験の一部が免除になる(※)ため、やはり養成講座を受講するメリットは大きいと言えるでしょう。
※国の認可を受けた養成講座を受講し講座内で実践研修(教育実習)までを修了すると、国家試験(「日本語教員試験」)のうち基礎試験と実践研修が免除になり、応用試験のみの受験・合格で資格取得が可能になります(修了した機関や時期により条件が異なります)。
資格取得の方法についてはこちらの記事や動画でも詳しく説明していますので、ご参考ください。
日本語教員になるためにはどんな勉強が必要?
それでは、養成講座では実際にどんなことを学ぶのか詳しく見ていきましょう。
先ほども紹介した通り、学習内容は大きく分けて「理論」と「実践」の2つがあります。
文科省が定める登録日本語教員養成機関・登録実践研修機関のコアカリキュラムでは、日本語教員養成における必須の教育内容と目標を定めています。養成講座のカリキュラムは、基本的にこのコアカリキュラムに則って作られています。
【理論科目の学習項目】
1)社会・文化・地域
・世界と日本(国際社会情勢と日本との関係、多様な国・地域の社会文化)
・異文化接触(外国人に関する施策と多文化共生)
・日本語教育の歴史と現状(日本語教育史と言語政策、日本語の試験、日本語教育事情)
2)言語と社会
・言語と社会の関係(社会言語学、言語政策や社会文化と言語の関係性)
・言語使用と社会(コミュニケーションストラテジー、待遇表現、言語・非言語行動)
・異文化コミュニケーションと社会(多文化・多言語主義)
3)言語と心理
・言語理解の課程(談話理解・言語学習)
・言語習得・発達(第一言語と第二言語の習得過程、学習ストラテジー)
・異文化理解と心理(異文化受容・適応、日本語学習・教育の心理的側面)
4)言語と教育
・言語教育法(日本語教員の資質・能力、日本語教育プログラムの理解と実践、教室・言語環境の設定、コースデザイン、教授法、教材分析・作成・開発、評価法、授業計画と授業分析、誤用とフィードバック、目的・対象別日本語教育法)
・異文化間教育とコミュニケーション教育(異文化間教育、異文化コミュニケーション、コミュニケーション教育)
・言語教育と情報(ICTの活用と著作権)
5)言語
・言語の構造一般(一般言語学、対象言語学)
・日本語の構造(日本語の文法・音韻・文字表記・文法など)
・コミュニケーション能力(学習者の受容・理解能力、言語運用能力、社会・文化能力を向上させる方法や、教師自らの対人関係・異文化調整能力の向上の方法)
日本語教員はこれらについての包括的な知識を持ち、実践と結び付けて考えられるようになることが求められています。
理論だけでも、幅広い知識を学ぶことがわかるかと思います。言葉そのものや教え方の理論だけでなく、心理・異文化コミュニケーションや言語を取り巻く社会、政策、歴史などについても学び、学習者との接し方や仕事の位置づけを理解します。
【実践研修(模擬授業・教壇実習)】
文科省のコアカリキュラムでは実践研修の実施についても定められています。実践研修では、「模擬授業」や、45分×2回の「教壇実習」を行います(ただし法改正前の内容を採用している養成講座では20分×2回の場合もあります)。内容は教育機関によって様々ですが、初級~上級の文型の中から課題の文型が出され、それについての導入から練習までの計画を作成するのが一般的。まずはクラスメイトである受講生を相手に模擬授業を行い、そのあと実際の外国人学習者の前で教壇実習を行うという流れになります。
・実践研修の流れ
1)まずは授業見学などを通して実際の授業を見て学ぶ
2)授業で扱う文法項目や教材についての分析を行う
3)課題の文型・文法項目が割り当てられ、個人やグループで「教案(授業の計画書)」や教材を作成
4)順番に模擬授業を行う。他の受講生は学生役となって授業を受ける。
5)他の受講生や講師からフィードバックを受ける
6)実際の学習者を相手に教壇実習を行う
7)他の受講生や講師からフィードバックを受ける
8)6と7をもう一度行う
9)最後に全体での振り返りを行う
実際にやってみると、思ったようにいかないところややり方が分からないところが出てきて、色々な発見があると思います。周囲のフィードバックで自分の癖がわかることもあるので、模擬授業は自分の授業を客観的に見られる貴重な機会です。また、予想外の質問や突っ込みがきて対応に戸惑ったりすることもありますが、やってみて初めて出てくる疑問や課題に取り組んでいくことで、現場での対応力が身に着きます。
授業内容そのものだけでなく、教室内での立ち位置や身の振り方、IT機器の操作など、授業内容以外の部分も重要です。最近はパワーポイントやオンラインツールを使った授業づくりが主流になってきたため、そうしたツールを使う練習の機会にもなるのではないかと思います。
独学でも可能?
日本語教師になるためには必ず養成講座を受けなければならないのかというと、そうではありません。市販の教材等を利用して、独学で学んで国家試験を受験することも可能です。
しかしながら、試験は範囲が広く内容も専門的であるため、一人で学習を進めるのが難しい場合もあります。
実際に第一回の国家試験では、養成機関を経て受験した人の合格率は60%であったのに対し、独学で試験を受験した受験者では8.4%と、合格率に開きが出る結果となりました。
養成講座では、質問したいときにいつでも質問ができ、試験内容だけでなく受験ノウハウも教えてもらえます。手厚いサポートが受けながら確実に合格を目指したい場合には、養成講座がおすすめです。
【養成講座のメリットは?】
・常に生の現場の情報が得られ、テキストと現場の橋渡しができる
当然ながら理論だけでは、現場に立つことはできません。養成講座では実際の現場を知っている講師が授業を担当しているため、「理論ではこうだけど、実際のところはどうなの?」という疑問に対し、現場の実践例を聞くことができます。
・日本語教師を目指す仲間ができる
養成講座では同じ日本語教師の資格取得を目指す仲間と出会えます。色々な情報共有ができるため、心強い環境と言えるでしょう。就職後に同じ養成講座の仲間が同僚になることも、珍しくありません。
・模擬授業で実際の教室を使わせてもらえる
さらに、当校のように日本語学校に併設されている養成講座の場合は、模擬授業で実際の教室を使わせてもらえるケースが多いです。勉強の段階から現場の空気に触れることができるので、就職後のイメージを持つのに役立ちます。
またそれ以外にも、大学の日本語教師養成課程や日本語教育の専攻・副専攻でも、同様の内容を学ぶことができ、国家試験の一部が免除されることがあります。
・学問としての日本語に関心がある、費用・時間が確保できる→大学・大学院
・講師や仲間のサポートを受けながら確実に合格を目指したい→養成講座
・自分のペースで学習を進めたい、費用を押さえながら合格を目指したい→独学
など、自分に合った方法を検討してみてください。
TCJの日本語教員養成講座がおすすめ!
今年から新制度の下で登録日本語教員養成機関・登録実践研修機関の登録が始まり、今後現行の420時間養成講座から新制度の養成講座へ移行する学校が増えていくと考えられます。いずれは全ての養成講座が登録を受ける必要がありますが、2025年2月現在はまだ経過措置期間中です。当面の間は、登録を受けている機関とそうでない機関が併存していることになります。
学士の学位をお持ちの場合は、登録機関でも、そうでない機関でも同様に国家試験の一部免除が受けられます。一方、学士をお持ちでない場合は、登録機関での受講が近道になります。
どちらにせよ最終的には国家試験(応用試験)に合格する必要があるため、国家試験対策でしっかり面倒を見てくれるところを選ぶ必要があります。
TCJは、標準で国家試験対策が付属しており、合格率も全国平均より15%以上高いのが強み。これから受講を検討されている方に向けた説明会や相談会も行っておりますので、ご検討中の方はぜひお気軽にご相談ください。
経験豊富な講師陣とスタッフが、皆様の日本語教員デビューを全力でサポートいたします!
まとめ
今回は「420時間って何?」という疑問にこたえるべく、420時間で行う学習項目や養成講座の内容について解説しました。日本語教員になるための勉強について、少し具体的なイメージを持っていただければ幸いに思います。
他の記事でも国家試験や教え方、具体的な日本語の文法などについて解説していますので、そちらも合わせてご覧ください。それでは今回はこのへんで!
参考
・文部科学省「令和6年度日本語教員試験実施結果をお知らせします」
https://www.mext.go.jp/content/20241220-mxt_nihongo02-000039332_1.pdf
・文部科学省「登録日本語教員 実践研修・養成課程コアカリキュラム 」
https://www.mext.go.jp/content/20241220-mxt_nihongo02-000039332_1.pdf







