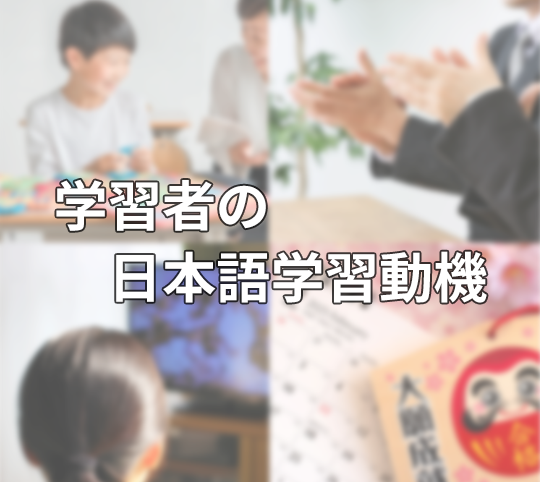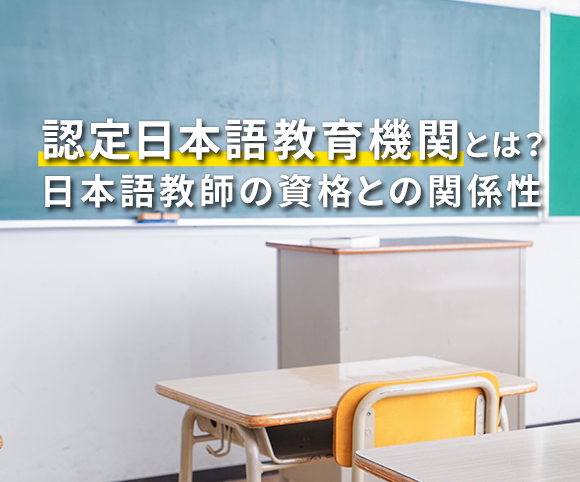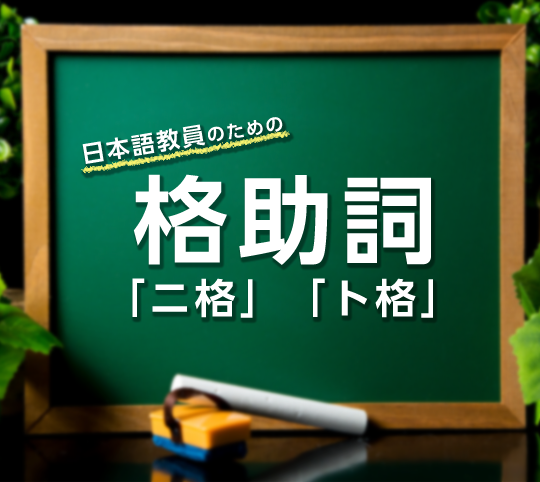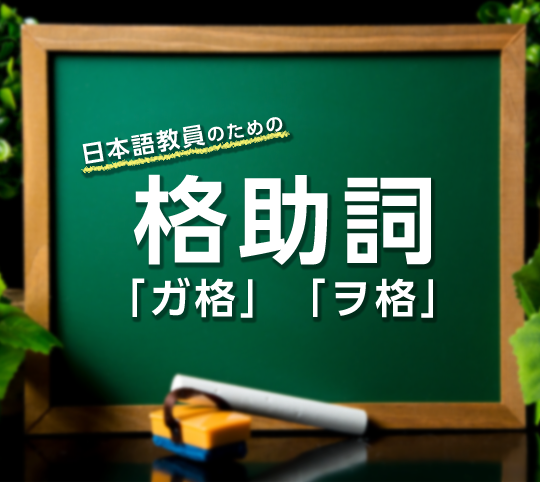TCJコラム

【日本語教員試験対策】「日本語教育の参照枠」の「全体的な尺度」とは?日本語能力の6レベルを分かりやすくご紹介!
日本語のレベルを判断する際の基準として役立つ「日本語教育の参照枠」の中から、最もおおまかな尺度である「全体的な尺度」について解説します。「初級」「中級」などと言っても、レベルの定義は実はあいまい。そんなときに活用できるのが、今回解説する「全体的な尺度」です。「日本語教員試験」にも出てくる重要キーワードで、教師デビューした後も活用できるものですので、理解を深めてみてください。
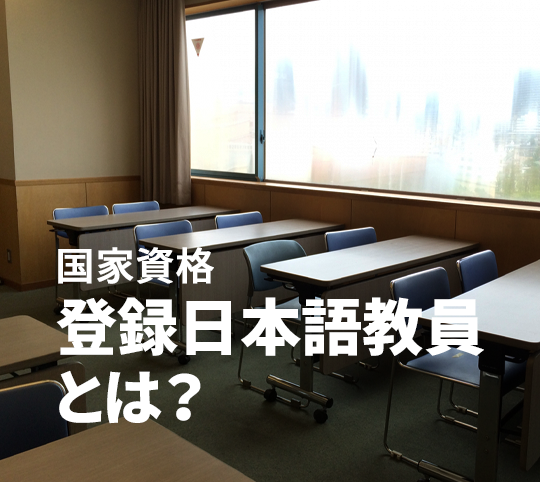
登録日本語教員とは?国家資格になってどう変わった?資格取得ルートを解説
日本語を教える専門職である日本語教師。これまでは民間の資格でしたが、法改正によって国家資格化され、「登録日本語教員」という名称に変わりました。本記事では、法改正によって変わった点や、資格取得の方法について解説します。

「〇抜き言葉」「〇入れ言葉」いくつ知っていますか?
日本語教育に携わっていない方でも「〇抜き言葉」と言ったら「ら抜き言葉」が頭に浮かぶのではないでしょうか。 「ら抜き言葉」とは、「食べられる」→「食べれる」 「来られる」→「来れる」 のような本来「ら」が入るべきところに「ら」の抜けた言葉のことで、話し言葉で使われることが多いです。 今回は「ら抜き言葉」を含め、〇抜き言葉、〇入れ言葉と呼ばれている言葉遣いを、日本語話者が日常的に使っている表現と日本語教育の現場での扱いについてまとめました。

ピア・ラーニングって何?日本語教育現場における活用方法も紹介
この記事では、 「そもそもピア・ラーニングとはなんだろう?」という方や、 「養成講座で聞いたことのある言葉のような気がするけど詳しくは分からない」という方へ、 ピア・ラーニングの意味や、実践例についてまとめました。 用語の意味理解の促進や、実際のクラス活動にお役立ていただけたら嬉しいです。
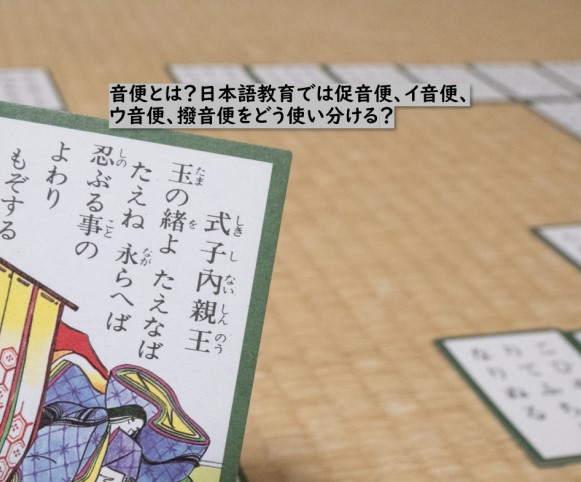
音便とは?日本語教育では促音便、イ音便、ウ音便、撥音便をどう使い分ける?
日本語には音便という変音現象があります。これは、いつ頃起こったのでしょうか。また、日本語学習者にとって、この現象はどう捉えられているのでしょうか。ここでは音便について、その歴史と現場での扱い方・留意点などをご紹介していきます。