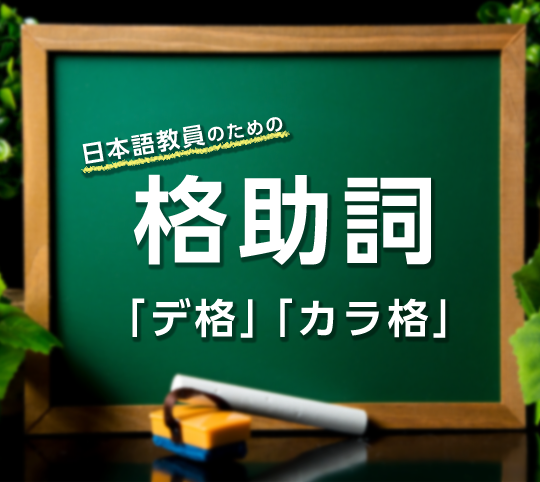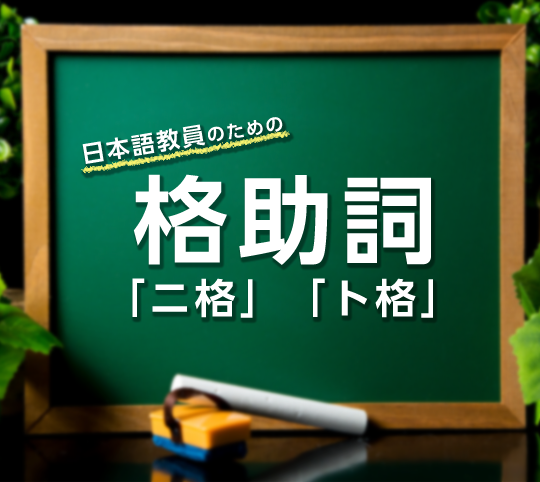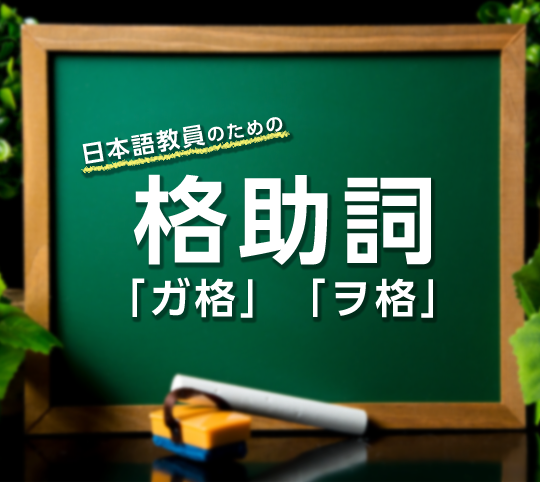TCJコラム

「〇抜き言葉」「〇入れ言葉」いくつ知っていますか?
日本語教育に携わっていない方でも「〇抜き言葉」と言ったら「ら抜き言葉」が頭に浮かぶのではないでしょうか。 「ら抜き言葉」とは、「食べられる」→「食べれる」 「来られる」→「来れる」 のような本来「ら」が入るべきところに「ら」の抜けた言葉のことで、話し言葉で使われることが多いです。 今回は「ら抜き言葉」を含め、〇抜き言葉、〇入れ言葉と呼ばれている言葉遣いを、日本語話者が日常的に使っている表現と日本語教育の現場での扱いについてまとめました。