
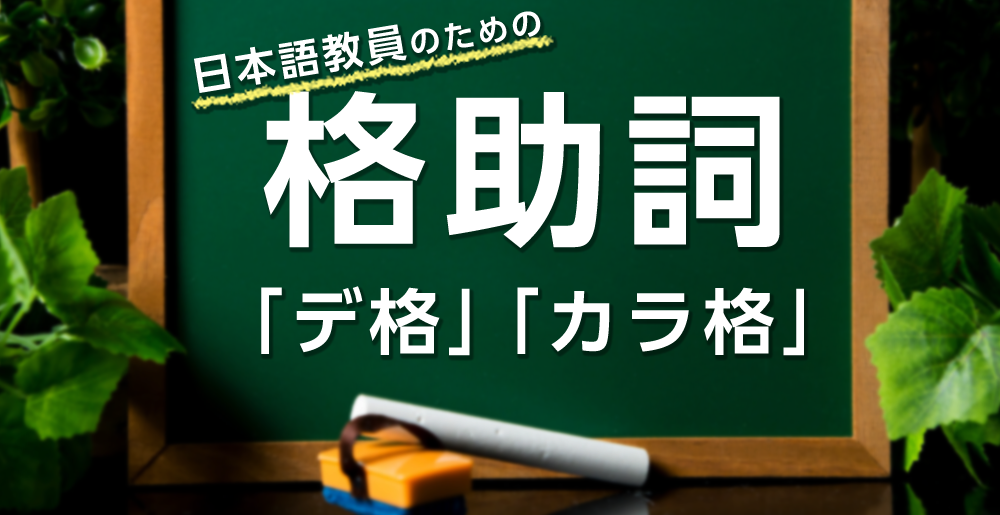
【保存版】格助詞・デ格、カラ格のポイント
この記事では、10種類ある格助詞の中でも、日本語教師として、きっちりマスターしておきたい「デ格」「カラ格」の教え方について、わかりやすく説明します。
ズバリ!格助詞とは何か?
格助詞とは「が」「に」「より」など、主に名詞の後ろにくっついて、その名詞がどのような働きをするのかを示す語のことを言います。日本語は語順の自由度が高い言語で、言いたいことを正しく伝えるために、格助詞はなくてはならない存在です。これまでに、10種類の格助詞の覚え方、そして「ガ格」や「ニ格」など、7つの格助詞について具体的に見てきましたが、シリーズ第4弾となる今回の記事では、「デ格」「カラ格」について詳しく解説していきたいと思います。
格助詞「で」の教え方
「学校で勉強する」「カタカナで書く」など、格助詞「で」は初級クラスでもすぐに教える格助詞の一つですが、用法がたくさんあり、学習者が間違えやすい格助詞でもあります。ひとつずつ、しっかり確認していきましょう。
【デ格】格助詞「で」の用法は、主に8つです。
- 場所
- 手段
- 起因・根拠
- 主体
- 限界
- 領域
- 目的
- 様態
1. 場所/Location of Action
「食べる」「見る」など、動作を表す述語を取るとき、その動作が行われる場所を表します。
(例)・家で勉強します。
・レストランで食事をします。
また動詞「ある」を使って、イベント(出来事)があることを述べる場合、「で」を使って場所を表します。
(例)・この公園でコンサートがあります。
・その部屋で会議があります。
2. 手段/Means
格助詞「で」の中心的な用法で、動作や出来事の成立のために用いられるものをさします。道具・方法・材料・構成要素・内容物・付着物に、細かく分けることができます。
⚫︎道具:目的を達成するために使う道具を表します。
(例)・はさみで切ります。
・スマホで写真を撮ります。
⚫︎方法:方法や形式などを表します。
(例)・漢字で書いてください。
・インターネットで注文します。
⚫︎材料:「作る」「できている」など、生産を表す述語と共に使われ、材料を表します。
(例)・ごはんと野菜でチャーハンを作ります。
・このテーブルは、木でできています。
⚫︎構成要素:ある事物を成り立たせるために必要な要素を表します。
(例)・このチームは、全員日本人で構成されています。
・この薬の半分は、やさしさでできているそうだ。
⚫︎内容物:「満たされる」のような充満を意味する述語と共に使われ、何で満たされるかを表します。
(例)・コンサート会場はファンで満員御礼だ。
・うれしい気持ちでいっぱいです。
⚫︎付着物:「汚れる」など状態変化を表す述語と共に使われ、その状態を引き起こす物を表します。
(例)・スカートが雨で濡れる。
・くつが泥で汚れてしまった。
3. 起因・根拠/Cause or Reason
ある事態が起こった原因や、行動・感情・判断の理由などを表します。
(例)・雪で電車が止まりました。
・出張で授業を休みます。
・家族のことで悩んでいます。
・彼の話し方でそれが深刻だとわかった。
4. 主体/Experiencer
ある物事をどのように行うかについて述べるとき、その行動の主体を表します。
(例)・家族で旅行をしました。
・山田さんと私でこの件を担当します。
・一人で住んでいます。
5.限界/Limit
数量的・時間的・空間的な範囲の上限や終点を表します。
(例)・5時で締め切ります。
・ケーキは1つで十分です。
6.領域/Extent
主に何かを順位付けして評価する際、その領域を表します。「いちばん」「もっとも」などと使われることが多いです。
(例)・琵琶湖は、日本でもっとも大きい湖です。
・人生で一番、今が幸せです。
7. 目的/Purpose
意志動詞が述語のとき、その動作の目的を表します。
(例)・観光で京都に来ました。
・買い物で大阪まで行きます。
8. 様態/Manner
動作がどのような様子で行われるかを表します。
(例)・小さい声で話してください。
・はだしで砂浜を歩きたい。
■教え方のコツ
実際に教える中で、最も多いと感じる間違いが、場所の用法の「に」と「で」の混乱。学習者の母語によっては、使い分けをしないケースが多いからです。私のクラスでは以下のように教えています。
①注目するのは、場所ではなく「動詞」!
□に:動詞が「存在」グループのとき。例:あります、います、住んでいます
□で:動詞が「アクション」グループのとき。例:食べます、見ます、勉強します
②シンプルな練習問題にトライ!「動詞」が大切だということに気づかせる。
1. 今、マクドナルド( )います。
2. マクドナルド( )食べます。
3. 家( )テレビが あります。
4. 家( )テレビを 見ます。
[答え]1. に 2. で 3. に 4. で
③「イベントがあります」のパターンに要注意!動詞が「あります」であっても、イベントの場合は「に」ではなく「で」!
1.この公園( )、コンサートがあります。
2.この公園( )、桜の木があります。
[答え]1. で 2. に
イベントがありますの「あります」は「アクショングループ」です。私は学習者が興味を持っているイベント名を具体的に使い、「ほら、アクションを感じるでしょ?だから、存在グループの「に」じゃなくて、アクショングループの「で」ですよ!」と言いながら教えています。
学習者が誤った際に、繰り返し同じ例を使って教えれば、だんだん正しい助詞が導き出せるようになりますよ!
格助詞「から」の教え方
【カラ格】格助詞「から」の用法は、主に5つです。
- 起点
- 主体
- 起因・根拠
- 経過域
- 手段
1. 起点/Starting Point
「起点」は、格助詞「から」の中心的な用法です。移動や方向の起点、範囲の始点、変化前の状態を表します。
(例)・家から行きます。
・財布からお金を出します。
・ここから私の学校が見えます。
・9時から6時まで仕事をします。
・信号が、赤から青に変わった。
2. 主体/Experiencer
「言う」「渡す」など、伝達や提供に関する述語を取るとき、主体を表します。「起点」の用法の発展形だと言えるでしょう。
(例)・私から伝えます。
・上司から渡されました。
なお、この用法は「より」で置きかえられますが、「より」のほうが改まった印象があります。
・私から伝えます。(一般的)
・私より伝えます。(改まった印象)
3. 起因・根拠/Cause or Reason
出来事や考えの起因や根拠を表します。これも「起点」の用法の発展形だと言えるでしょう。
(例)・ストレスから病気になってしまった。
・銀行の破綻から、世界恐慌が始まった。
4. 経過域/Route of Action
「入る」「出る」など位置変化を表す述語を取るとき、経由する場所を表します。知覚動詞と共に使われることもあります。
(例)・後ろのドアから、静かに入ってください。
・窓から、子どもの声が聞こえます。
5. 手段/Means
原料や構成要素を表します。
(例)・このワインは、スペイン北部のブドウから作られています。
・このチームは9人のメンバーから、構成されています。
■教え方のコツ
学習者が戸惑うのが、原料を表す「から」と材料を表す「で」の使い分け。この違いは日本語教員試験など資格試験でも狙われやすく、日本語教師としてはしっかりおさえておきたいポイントです。
□原料「から」:元の形がなくなっている。
(例)・米から日本酒を作ります。(米の形がなくなっている。)
・木から紙を作ります。(木の形がなくなっている。)
□材料「で」:元の形がそのままだったり、ある程度、残っていたりする。
(例)・米でパエリアを作ります。(米の形は残っている。)
・木でイスを作ります。(木の素材感は残っている。)
まとめ
初級クラスでもすぐに教える「カラ格」と「デ格」ですが、学習者がつまずくポイントは、ある程度決まっているように感じます。「教え方のコツ」でご紹介した点などをしっかりおさえて、自信を持って教壇に立ちたいものですね。この記事がみなさんの指導のお役に立てば幸いです。
参考
大阪YWCA, 氏原 庸子, 清島 千春, 井関 幸, 影島 充紀, 佐伯 玲子 (2023)『くらべてわかるてにをは日本語助詞辞典』Jリサーチ出版
日本語記述文法研究会編 (2009)『現代日本語文法2 第3部格と構文 第4部ヴォイス』くろしお出版

アクションリサーチとは、日本語教育では、どのようにアクションリサーチが使われているか
この記事ではアクションリサーチに焦点を当て、その一般的な意味、言語教育での応用方法、具体例、そして日本語教育における効果について解説します。







