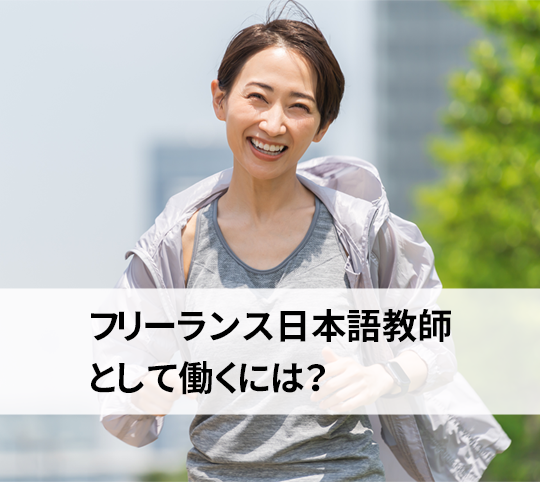「〇抜き言葉」「〇入れ言葉」いくつ知っていますか?
概要
日本語教育に携わっていない方でも「〇抜き言葉」と言ったら「ら抜き言葉」が頭に浮かぶのではないでしょうか。
今回は「ら抜き言葉」を含め、〇抜き言葉、〇入れ言葉と呼ばれている言葉遣いについてまとめました。
ら抜き言葉
まず「ら抜き言葉」とは、
「食べられる」→「食べれる」
「来られる」→「来れる」
のような本来「ら」が入るべきところに「ら」の抜けた言葉のことで、話し言葉で使われることが多いです。
昭和初期から現れ、戦後に増加したと言われています。
ただ小林多喜二の『蟹工船』や川端康成の『雪国』でも「ら抜き言葉」の記載があることから、一般的ではないにしろ、当時から書き言葉としても使用されていたようです。
「~られる」を使う表現には可能・受身・自発・尊敬がありますが、「ら抜き言葉」は、可能の意味で使用される傾向にあります。
特にⅡグループ動詞(一段活用)と「来ます」(カ行変格活用)の動詞のみに出現し、Ⅰグループ(五段活用)と「~します」といった(サ行変格活用)の動詞には、ら抜き言葉の出現は見られません。
それには文法上の理由があります。
Ⅰグループ動詞の「走る」「読む」といった動詞には「走れる」「読める」といった可能動詞には、受身や尊敬を表す「走られる」「読まれる」と明確に違いがありますが、Ⅱグループ動詞や「来ます」といった動詞には、いずれも「見られます」「来られます」と違いがなく、前後の文脈によってどの意味になるのか判断しなければなりません。
以上のことから、可能と受身や尊敬を明確に分けるような表現が広まった可能性があるようです。
文化庁の国語審議会が平成7年に行った報告によると、
1)「ら抜き言葉」を可能の意味に限定して用いることで、受身・自発・尊敬(見られる)と区別することは合理的であるという考え方
2)五段活用の動詞における可能動詞(読める、持てる等)と同様に可能動詞形と認めようとする考え方
3)「ら抜き言葉」の増加は可能表現の体系的な変化であり、話し言葉では認めてもよいのではないかという考え方
があると記載があります。
また、北陸から中部にかけての地域及び北海道などでは「ら抜き言葉」を多く使う地域もあるようです。
現時点においては、共通語として誤用だと扱われている「ら抜き言葉」ですが、正用に向けて多様な考え方が出てきているように、今もなお議論が進められている様子がわかりますね。
れ入れ言葉
れ入れ言葉は
1)「話せる」→「話せれる」
2)「見られる」→「見れる」→「見れれる」
1)のⅠグループ(五段活用)の可能動詞や、2)いわゆる「ら抜き言葉」と言われているⅡグループ(一段活用)の可能動詞に不要な「れ」を入れた言葉で、れ足す(レタス)言葉とも呼ばれています。
特に2)は可能表現を繰り返していることから、二重可能表現とも言われています。
「ら抜き言葉」と同じく可能表現に関する言葉で、可能と受身、自発、尊敬とは区別したいという潜在的な意識から発生したのかもしれません。
例えば、Ⅰグループで使用する「行く」を受身、自発、尊敬の意味で活用する場合「れる」を接続して「行かれる」になりますが、可能の意味であっても文法的に正しい形です。
ですがⅠグループ動詞には可能動詞があり、「行く」の場合には「行ける」があるため、語幹は「行け」に上記同様「れる」を接続した結果、「行けれる」といった誤用表現が生まれたようです。
い抜き言葉
「い抜き言葉」は、
「走っている」→「走ってる」
「使っている」→「使ってる」
のように補助動詞として使用される「~ている」から、文字通り「い」の抜けた言い方です。
概ね話し言葉で使用されることが多く、カジュアルな場面での使用頻度が高い言葉で、教科書においても会話例で掲載されています。
すでに使用頻度も高く違和感なく日常会話で使っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ビジネス文書や論文などでは適切ではないといえますが、広まり方でいえば「い抜き言葉」は、誤用とまではいえないかもしれませんね。
さ入れ言葉
「さ入れ言葉」はいくつかの表現で出現することが確認されており、
1)「休ませていただく」→「休まさせていただく」
「使わせていただく」→「使わさせていただく」
のような謙譲表現や
2)「少なすぎる」→「少なさすぎる」
「知らなすぎる」「知らなさすぎる」
といった程度を表す表現、また
3)「見せてください」→「見させてください」
といった動詞「見る」の派生形「見せる」の意味で使用する場面で見受けられます。
1)では、本来Ⅱグループ(下二段活用)やⅢグループ(カ行変格活用・サ行変格)の活用であれば正しい「さ」がⅠグループ(五段活用)の活用で不要な形で現れています。
正しくは、
Ⅱグループ「借ります」→「借りさせていただく」
Ⅲグループ「発表します」→「発表させていただく」
ですね。
2)では、形容詞「少ない」や動詞の否定形「知らない」を活用させ、程度を表す「すぎる」を組み合わせた表現で、本来であれば、
「多い」→「多すぎる」
「飲まない」→「飲まなすぎる」
と「さ」が不要な活用ですが、
形容詞「ない」と「すぎる」を組み合わせる場合、な「さ」すぎるのように「さ」を入れるため、この活用と混同して「さ入れ言葉」が生まれたようです。
3)では「見させる」という活用そのものに問題はなく、文法上正しいのですが、
「何か物などを人が見えるように示すという意味」で「見せる」を使用したいにも関わらず、使役の「見させる」を使用している場合は、人によって違和感があるのかもしれません。
3)は文法上問題ありませんが、1)2)の例でいえば「さ入れ言葉」は明らかな誤用ということになります。
日本語教育の現場ではどう扱う?
それでは実際の教育現場では、どのように扱ったら良いのでしょうか。
学習者が見聞きするという点において、「い抜き言葉」は教科書でも触れる機会があり、指導するべきか迷うでしょう。
鈴木(2007)によれば、学習者の理解と使用という二つの側面を組み合わせて取り入れていくことが大切だと述べています。
また、まずは理解することが必要であり、次に学習者自身が使用する練習が必要となるという視点からみれば、「い抜きことば」は理解も使用も必要なのではないかという見解のようです。
日本語の教科書にも使用されていることから、カジュアルな会話を扱う際には「い抜き言葉」について取り入れたほうがよさそうです。
一方共通語としては誤用として扱われている「ら抜き言葉」「れ入れ言葉」「さ入れ言葉」は、現時点で取り入れる必要性はないといえますね。
まとめ
皆さんは、○抜き言葉、○入れ言葉をいくつ知っていましたか?
一般的には少ないとはいえ、以上にあげた表現を、話し言葉として日常的に使用される方もいるようです。
外国人に日本語を指導する身としては、「ら抜き言葉」などの誤用表現を使う日本人が増えていくと学習者は混乱するだろうなと思ったりもします。
とはいえ歴史を見ると、元は誤用表現であった言葉が今では正しいとされてきたものもあるようです。
学習者がひとたび教室を出たら、そこには教室で学んだ日本語だけでなく生きた日本語があふれています。
誤用は誤用として、できる限り正しい日本語を教えつつも、時とともに移り行く言葉を扱う日本語教師としては、言葉のゆれを理解しながら、学習者に寄り添った指導を心がけたいものです。
参考文献/引用
井上史雄(2007)『変わる方言 動く標準語』筑摩書房
柿木 重宜(2003)『なぜ言葉は変わるのか: 日本語学と言語学へのプロローグ』ナカニシヤ出版
倉島 節尚(2018)『見て読んでよくわかる!日本語の歴史4 昭和後期から現在 変わり続ける日本語』筑摩書房
小松英雄(2013)『日本語はなぜ変化するか』笠間書院
鈴木 睦(2010)「変わりゆく日本語と日本語教育の今」『JOURNAL CAJLE』11, 10-22 https://www.cajle.ca/wp-content/uploads/2022/10/CAJLE-Vol-11.10-22.pdf
中山緑朗、飯田晴巳、陳力衛、木村義之、木村一(2009)『みんなの日本語事典-言葉の疑問・不思議に答える』明治書院
文化庁(1995)「新しい時代に応じた国語施策について(審議経過報告)」(参照I言葉遣いに関すること 4その他(1)語彙・語法等の問題 アいわゆる「ら抜き言葉」) https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kakuki/20/tosin03/index.html
毎日ことばplus(2023)「見せて/見させての使い分け」毎日新聞 https://salon.mainichi-kotoba.jp/archives/177988

学習ストラテジーで日本語学習をより楽しく効果的に!
「外国語教師が知っておかなければならない」でお馴染みの学習ストラテジー。もちろん、日本語教師だって知っておかなきゃです。この記事では、言語学習を効果的で楽しくする学習ストラテジーをわかりやすく解説いたします!