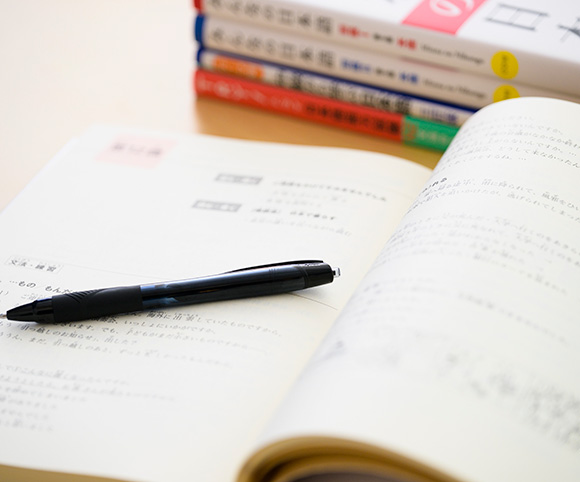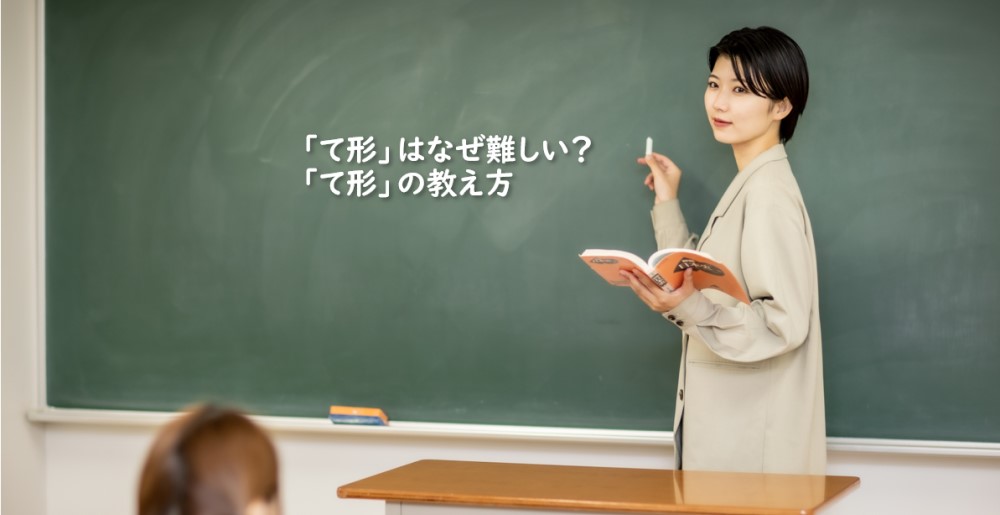
「て形」はなぜ難しい?「て形」の教え方
【『て形』とは】
「て形」とはその名の通り、「見る」に対する「見て」、「行く」に対する「行って」、「食べる」に対する「食べて」など、「~て」に接続した動詞の活用形のことを言います。これは小中学校の国語で言うところの「連用形」+接続助詞「て」にあたるものですが、日本語教育ではわかりやすくまとめて「て形」と呼んでいます。初級では動詞の色々な活用形を学習しますが、その中でも「て形」は、多くの教科書で一番最初に出てくる重要な文法項目です。
「て形」が重要だと言われるのには、
・文と文とつなげる一番簡単な形だから
・いろいろな文型に接続することができるから
・その後に習う他の活用形を覚える際の基礎になるから
といった理由があります。一つずつ見ていきましょう。
まず、て形が使えると、2つ以上の動詞の文を繋げることができます。たとえば、「顔を洗います。そして、朝ごはんを食べます」→「顔を洗って、朝ごはんを食べます」。一文で短く、自然な言い方になります。また、て形は様々な文型に接続して使えます。「て形」を使った初級の文型には、「~てください(依頼)」「~てもいいですか(許可を求める)」「~てはいけません(禁止)」などがあります。
それまで学習者が習っているのは「~ます。」という形だけですが、これらの文法が使えるようになると、「見ます、お願いします」→「見てください」、「見ます、いいですか」→「見てもいいですか」、
「見ます、いけません」→「見てはいけません」など、使える表現の幅がぐっと広がり、「片言」の日本語から「機能」を持った表現へと、一歩先へ進むことができるのです。
そして、この「て形」は、その後に出てくるほかの活用形を学ぶ際の基礎にもなります。例えば、過去を表す「た形」。これは「見て」→「見た」、「泳いで」→「泳いだ」のように「て」→「た」、「で」→「だ」に変えるだけ。て形がしっかり身についていれば、学習者の覚える負担が少なくなります。
【なぜ「て形」が難しいのか?】
初級の第一関門とも言われる「て形」ですが、その難しさは、活用のルールの複雑さにあります。一言で「て形」と言っても、バリエーションがあります。
シャワーを浴びて、新宿に行って、映画を見て、ご飯を食べて、お酒を飲んで、うちに帰って、音楽を聞いて・・。
ざっといくつか動詞を挙げてみましたが、「って」「んで」「いで」など色々な形があるのが分かります。こうした音の違いは、歴史の中で生じた「音便化」によるものです。例えば「書きます」は「書きて」がイ音便化し、現在は「書いて」という形になっています。しかし、「いきます」は「生きます」なら「いきて」、「行きます」なら「いって」となるように、「き」がつく全ての語に同じルールが当てはまるわけでもありません。
音の変化には規則的なものだけでなく例外的なものもあります。学習者はそれらを一から覚えていく必要があるため、学習者には負担が大きいです。もちろん、教師もこうした活用のルールを知っておかなければいけません。
【「て形」導入のポイント① 動詞のグループ分けと活用ルール】
て形の導入でまず押さえなければならない内容は「動詞のグループ分け」「活用の仕方」「例外・間違えやすいもの」の3つです。
小中学校の国語では、動詞を「五段活用」「一段活用」「サ行変格活用」「カ行変格活用」のように分類しますが、日本語教育では、これを学習者にとってわかりやすいように
「書きます」「会います」などの五段動詞→『Ⅰグループ』、
「寝ます」「教えます」などの一段動詞→『Ⅱグループ』
「来ます」「します」「勉強します」などの変格活用の動詞→『Ⅲグループ』
という3つのグループに分けています。
【グループの見分け方】
まず、「~ます」の前の音に注目します。
マスの前がイ段であればⅠグループ(書きます 読みます 会います など)、
マスの前がエ段であればⅡグループ(教えます 食べます 寝ます など)です。
ただし例外があり、「見ます」「います」「起きます」「借ります」「(バスを)降ります」などの動詞はマスの前がイ段ですがⅡグループです。
変格活用である「来ます」「します」はⅢグループになりますが、派生語である「持ってきます」や「名詞+します(勉強します、練習しますなど)」も同様で、このⅢグループになります。
次は活用のルールです。て形の作り方には、「ます形」から作るものと「辞書形」から作るものがありますが、多くの教科書では最初に「ます形」を導入しているため、ここでは「ます形」から「て形」を作る方法について解説したいと思います。まずは活用が簡単なものから見ていきましょう。
【Ⅱグループ】
「ます」をとって「て」をつけます。
例 食べます→食べて 寝ます→寝て、見ます→見て
簡単なので、覚えやすいですね。
【Ⅲグループ】
「来ます」「します」の二つです。活用は「来ます」→「来て」、「します」→「して」となります。
2つだけなので、そのまま覚えてもらいましょう。
複合動詞や「名詞+します」の動詞は、
「持って来ます」→「持って来て」「勉強します」→「勉強して」のように、後ろの部分を活用します。
【Ⅰグループ】
Ⅰグループの活用は、音便化があるため複雑になっています。まず、「ます」の直前の音に注目します。
マスの前が「い」「ち」「り」→「って」
例:会います→会って、待ちます→待って、乗ります→乗って
マスの前が「み」「び」「に」→「んで」
例:読みます→読んで、遊びます→遊んで、死にます→死んで
マスの前が「き」→「いて」、「ぎ」→「いで」、「し」→「して」
例:聞きます→聞いて、泳ぎます→泳いで、話します→話して
※ただし「行きます」は例外で、「行って」になります。
実際の授業では、まずグループごとにルールを説明し、活用の練習をおこない、その後で「~てもいいですか」などの文型を使った文を作る練習をしていきます。
【て形導入のポイント② 分かりやすく教える】
- 混乱の少ない順番で導入すること
前述したとおり、活用が複雑なのはⅠグループの動詞です。そのため、実際の授業では、「活用が簡単なⅡグループ」、「数が少なく、覚えるだけでいいⅢグループ」、「複雑なⅠグループ」の順に導入することが多いです。
- 教師が一方的に説明せず、学習者との対話をしながら理解してもらうこと
講義のように先生だけが話してしまうと冗長になりやすく、学習者も分からないまま進んでしまったり、分かったつもりになってしまうことがあります。導入段階から、学習者とのやりとりをしながら進めましょう。
例
T:おしえます。みせます。ねます。これはなんですか?
S:ぜんぶEですか?
T:そうです。マスの前は、「え」ですね。これは、2グループです。
教師が初めから答えを言うのではなく、学習者に問いかけて気づいてもらうのが大切です。
【「て形」をしっかり身に着けてもらうために】
「て形」は活用の基本でありながら、上級になっても間違えやすい項目です。定着には時間がかかるものと心得て、丁寧に、繰り返し練習していきましょう。学習者が「て形」の活用を簡単に覚えられるよう、歌で教える先生もいるようです。動画サイトなどで「て形の歌」と検索すると、「ロンドン橋」や「むすんでひらいて」などの有名な童謡のメロディに乗せて「て形」の活用を覚える替え歌が出てくるので、探してみてください。
【まとめ】
この記事では、て形とは何か、そして「て形」を教える際に気を付けたいポイントなどについてお伝えしてきました。これから日本語教師を目指している方もいらっしゃると思いますが、「て形」は就職試験の際の模擬授業などでも出やすい項目ですので、ぜひじっくり復習してみてくださいね。
同じく教えるのが難しい日本語文法に、「は」と「が」があります。
こちらは、熊切先生が解説を頂いています。「うなぎ文」に新提案? 「は」と「が」の基本を解説!も参考にしてみてください。
【参考文献】
スリーエーネットワーク編著、『みんなの日本語Ⅰ 第2版』(2014)、スリーエーネットワーク
スリーエーネットワーク編著、『みんなの日本語Ⅰ 教え方の手引き』(2008)、スリーエーネットワーク
ヒューマンアカデミー編著、『日本語教育能力検定試験用語集』(2016)、株式会社翔泳社
原沢伊都夫著、『考えて、解いて、学ぶ 日本語教育の文法』、スリーエーネットワーク
『初級第一難関「て形」 学習者にわかりやすいと言われた「~てください」の文法導入を伝授』、Sensee Media
https://sensee.jp/media/teaching/begginer-te-gata-te-kudasai-grammer/

第1回・日本語教員試験を受験、第2回目に向けて出来ること
日本語教員試験について、実際に受験した感想をお伝えします。今回、受験したのは応用試験のみでしたので、こちらを中心に話題を進めていくことになります。応用試験は、聴解試験と読解試験の2つから成り立っており、主に日本語教育能力検定試験の試験ⅡとⅢがベースになっています。授業現場で遭遇するであろう課題の解決や事態の改善等について、理論化された知識と紐づけて出題されているというのがおおよその見方です。教育能力検定試験時代からの難所であった、聴解の問題をどのように突破するかが鍵となりそうです。
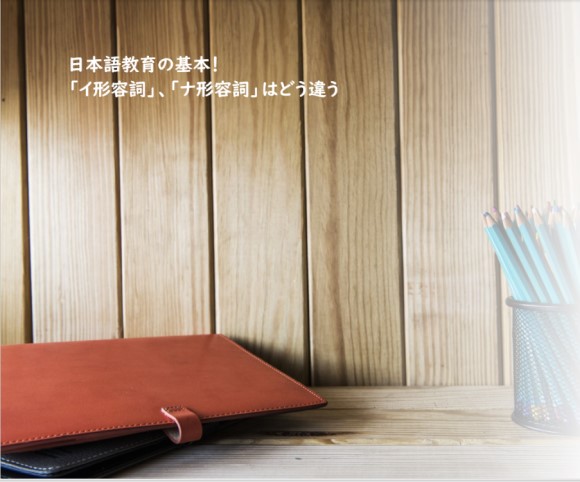
日本語教育の基本! 「イ形容詞」と「ナ形容詞」はどう違う?
「富士山がキレクテ感動しました。」 日本語教師ならば、この発話のおかしな理由をすぐに説明してくれることでしょう。この記事では、日本語教育の基本中の基本ともいえる「イ形容詞」と「ナ形容詞」の違いについて説明します。