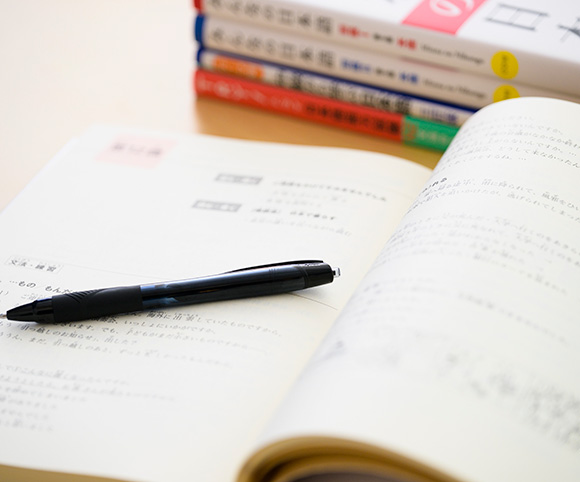【日本語教師向け】「は」と「が」の違いはどうやって教えるの?
概要
今回は日本語教師の方に向けて、よく違いが問われる「は」と「が」の違い、そしてその教え方について解説していきます。自分が普段何気なく使っている助詞も、分析してみると「そんな使い分けをしていたのか」と新たな発見があるかもしれません。ぜひ最後までお読みください。
助詞とは
日本語の特徴の一つである「助詞」。当たり前と思って使っていても、いざ質問されると意外と説明するのが難しく、あたふたしてしまうこともありますね。ここでは、改めてこの「助詞」とは何なのかについて考えてみましょう。
文の作り方は言語によってさまざまです。
言語学には、異なる言語の共通点や差異を分析する「言語類型論」なるものがあり、その中でも特に「単語の組み立て方」に基づいて言語を分析する「形態的類型論」というものがあります。
この形態的類型論では、言語は「膠着語」「孤立語」「屈折語」「抱合語」の4つに分類されます。
中国語などは、それぞれの単語が独立しており、単語の並べ方によって文の意味が決まる「孤立語」、英語などはchild→childrenのような形の変化がある「屈折語」、アイヌ語などは文を作る時に複数の単語を並べるのではなく、それぞれの要素がくっついて一つのことばのようになる「抱合語」と言われています。
では日本語は何かというと、独立した意味のある語彙(自立語)に、文法的な機能のある要素(機能語)を付け加えて文を作る「膠着語(こうちゃくご)」であるとされています。機能語というのは、それ単独では意味を成さないものの、自立語とくっつくことによって、ことばの主述関係や位置づけを示す文法的な要素のことです。
日本語では、「私は学校に行く」のように、私・学校・行くという自立語に、「は」や「に」という助詞をつけて文を作りますね。これが機能語と呼ばれるものです。
一方、中国語で「私は学校に行く」は「我去学校」と言います。我=私、去=行く、学校=学校と、それぞれの独立したことばを並べて文を作ります。
中国語のように機能語がない言語では語順がとても重要になりますが、日本語のような膠着語では、助詞が正しく使われていれば、語順が変わっても大きく意味は変わりません。
「私は学校に行く」「学校に私は行く」「私は行く、学校に」など、順番を入れ替えてみても「誰が何をするのか」という全体的な意味は同じです。
上のように語順を入れ替えると文の中で強調される部分が変わり、文の印象はそれぞれ異なるものにはなります。しかし、動作主や動作の内容が変わるわけではないため、語順に関して言えば日本語は柔軟な言語だと言えます。
「は」と「が」の役割の違い
助詞は学習者にとって頭を悩ませる部分の一つですが、中でもよく問題とされるのが、「は」と「が」の違いです。
「私は田中です」のような使い方を見ると、「は」は一見「主語」のように見えますが、厳密にはそうではありません。主語のような役割をすることもありますが、「お昼はもう食べました」「明日はテストがあります」のように、主格(動作主や主体)ではない使い方もありますね。
日本語教育文法では、「は」は主題を示す助詞として扱われます。何かを話題として取り上げて焦点を当てる働きを持つため、「取り立て助詞」と呼ぶこともあります。
例えば、
A:「はじめまして、田中です。神奈川在住で、日本語教師をしております。趣味はゴルフで・・・」
B:「へえ、ゴルフはいつからされてるんですか?」
このやりとりでは、Bさんは「あなたはいつからゴルフを・・」ではなく、「ゴルフはいつから」と聞いています。これは相手から得た情報の中で「ゴルフ」という部分を取り出し、新たな話題(=主題)として提示して返しているわけですね。
既に相手が自分自身のことを話していると分かっている状況ですから、ことさらに「あなた/田中さん」を話題にして「あなたは/田中さんはいつからゴルフをしていますか」と聞くよりも、言及したい内容を直接主題にして「ゴルフはいつから・・」と聞いたほうが自然です。
「は」と「が」の基本的な機能について整理しましょう。
「は」・・取り立て助詞
1)主題を表す
例:「夏はかき氷がおいしい」→主題=夏
2)対比を表す
例:「和菓子は好きなんだけど、チョコレートは苦手なんだよね」
→「和菓子」対「チョコレート」の対比)
特に否定文は、肯定文と対比されるものとしてのニュアンスがあるため、比較対象が明示されていなくても、「は」が使われることが多いです。
例:「ちょっとお酒は苦手なんです(=その他の、アルコールのない飲み物なら飲めるという含意)」)
「が」・・格助詞
1)主格を表す
動作主や状態の主格として機能する。
例:
犬が庭を走り回っている。(「走り回る」の動作主)
(今日は晴れていて)空気がきれいだ。(な形容詞「きれいだ」の主格)
また、以下の条件下では必ず「が」が使われます。
a. 副詞節の中
○「もしも願いがかなうなら」
×「もしも願いはかなうなら」
b. 従属節の中
○「(私は)先生が書いた本を読んだ」
×「(私は)先生は書いた本を読んだ」
c. 疑問詞の直後
○「誰が山田さんですか」
×「誰は山田さんですか」
2)状態の対象を表す
「好き」「きらい」などの状態を表す形容詞について、目的語のような役割を果たします。「アニメが好きです」は、本来は「私は(主格)」「アニメが(目的語)」「好きです(「好き」という状態を表す形容詞、述語にあたる)」です。
日本語文法の書籍では、よく「象は鼻が長い」という文が引き合いに出されます。
「はが構文」とも呼ばれるこの「AはBがC」の形では、Aは主語ではなく、話題の範囲(主題)を示しています。「A(象)に関して言えば、B(鼻)がC(長い)」という意味で、述語のC(長い)の主語はB(鼻)ですね。「象という動物は、鼻が長い」のであって、「象が長い」わけではありません。
例文で比較してみよう!
基本的な機能について確認しましたが、「は」と「が」どちらを使っても文法的には問題ない文も多いです。ただ、どちらを使うかによってニュアンスが変わってきます。
例えば、
1)私は田中です
2)私が田中です
それぞれ、どのような場面で使いますか?
前者は「私」を主題にしている言い方で、初めて会う人に自己紹介をするときの言い方ですね。一方で後者は、「他の人ではなく、私だ」と言いたいときの表現で、例えば、「どなたが田中さんですか」という疑問文への返事だと考えることができます。
こちらはどうでしょうか。歴史探訪などの番組で、ナレーターが読んでいるのを想像してみてください。
3)これはナポレオンが着ていた衣服です
4)これがナポレオンが着ていた衣服です
前者はそれまでの話題と変わって、新しい話題として衣服を紹介している様子。いろいろな遺品を紹介する中で、その一つとして「衣服」が出てきた場面が想像できるかと思います。
これに対して後者は、「これが、先ほども話した、ナポレオンが着ていた衣服です」というように、既に話題になっている「衣服」について掘り下げているように聞こえます。既に前の話で「衣服」について触れられており、前情報が与えられた上で実物を見せられているような印象です。
もうひとつ、こちらの有名な一節はどうでしょうか。
5)月が綺麗ですね
6)月は綺麗ですね
夏目漱石が英語の ”I love you”を邦訳した際に「月が綺麗ですね」という日本語にしたという逸話から引用してきたものですが、なぜ「月が」なのでしょうか。もし「月『は』綺麗ですね」と言ったら・・?
大変なことになりそうです。
この「月が綺麗ですね」というのは「あなたといると、月が一層美しく見える」という意図だと推察されますが、これを「月は綺麗だ」に変えてしまうと、比較や対比の意味合いが生まれます。すると「月だけが美しい(=それ以外は美しくない)」という意味になってしまい、相手を怒らせかねません。
「が」を「は」に変えるだけで印象が変わってしまうことは、やり取りの中でもよく起こります。
よく先生に「宿題はやりましたか」と聞かれて「はい、宿題はやりました」という学生がいます。本人はただ、教師が言った文をそのまま使って「はい」と答えているつもりなのですが、母語話者には「宿題に限って言えば、やった」と限定しているように聞こえてしまいます。
宿題について話していることは明白なので、単純に「宿題は」と繰り返す必要はありません。かといって「はい、宿題をやりました」というのもこれまた変です。「宿題はやりましたか」は本来「宿題をやりましたか」という文の目的語「宿題」を主題化したものですから、やはり「を」を使っても主題を繰り返すことになり、違和感を生みます。
「何をやったか」を聞かれている場合は「~を」が必要ですが、ここでは「やったかどうか」だけを聞いているので、「はい、やりました」「いいえ、やっていません」という動詞の部分だけで十分だというわけです。
学習者が混乱する前にチェック!授業で教えるときのポイントをご紹介
上記で説明してきたことは母語話者向けの解説ですので、学習者にそのまま伝える必要はありません。プライベートレッスンなど、媒介語を使って詳細な解説を希望する学習者の場合は別ですが、クラスレッスンなどでは一般的に、教師がポイントを絞って導入していきます。
【初級で助詞を扱う際のポイント】
・直説法の初級授業では、無理に理屈で説明しない
・助詞は用法が多いので、まずは「ここだけは」という用法に絞る
・提示する例文をよく吟味する(導入している文型と違う使い方の文が混ざっていないか。)
言葉の説明に頼れない初級において、理解しやすい文脈を作ることは特に大切です。
たくさんの例文や場面を用意し、それぞれの基礎的な用法を理解してもらうようにしましょう。
まずは、
・「は」の説明では「主語です」と言わない。「AはBですが、CはDです」「はが構文」などの導入で、「は」の主題・対比の概念を理解させる
・必ず「が」になるもの(副詞節・従属節、「~が好きです」、疑問詞疑問文など)、必ず「は」になるもの(自己紹介)を確実に覚えて使えるようにする
といった点を押さえられるようにしましょう。
「は」の使用法を学習した後、学習者が会話の中で何を取り立てるべきかを見極められるようになるには時間がかかります。「単なる存在文」と「取り立ての文」がどう違うのかは引っ掛かりやすいポイントです。
たとえば「~に~があります(存在の文)」と「~は~にあります(取り立ての文)」の違いの説明では、
(机の上にスマホを置いておき、指さして)
「先生、その机の上にスマホがあります。」「あ、本当ですね。だれのスマホですか?」「あ、わたしのです。」
「いま、『机の上にスマホがあります』。だれのですか?どうしてここにありますか?わかりません。ただ、机を見ました。あ、スマホがあります。『机の上にスマホがあります』。」
~~~~~
(会話例を見せる)
A:「私のスマホがありませんね・・どこですか?」
B:「タイさんのスマホですか?どこですか?うーん、あ!ありました!タイさんのスマホは、机の上にあります!」
「今、タイさんのスマホがありません。どこですか?タイさんのスマホについて話しています。タイさんのスマホはどこにありますか?『タイさんのスマホは、机の上にあります。』」
このように、すでに前の文で話した何かを主題にして次の文を繋げる例を出すと分かりやすいです。
まとめ
いかがでしたか?
今回は「は」と「が」の違いについて検討してきました。助詞の学習では、母語話者が感覚的に身に着けていることを改めて問われることが多いように感じます。
既に日本語教師として教壇に立っていらっしゃる方、これから日本語教師を目指される方も、自分がどのように日本語を使っているか振り返りながら、考えていきましょう!
参考
庵功雄、高梨信乃、中西久美子、山田敏弘(2000)「初級を教える人のための 日本語文法ハンドブック」スリーエーネットワーク
市川保子(2005)「初級日本語文法と教え方のポイント」スリーエーネットワーク
国家試験対策が必要な方へ
TCJ日本語教師養成講座では、日本語教員試験の学習に特化したeラーニング教材を開発しました。
令和6年度日本語教員試験での合格率(当社調べ)
・基礎、応用試験 合格率44% (全国平均8.7%)
・応用試験のみ 合格率71%(全国平均 60.8%)
試験ルートの合格率が全国平均の約5倍となっています。
【こんな方におススメ】
・試験ルートで登録・日本語教員の資格取得を検討している方
・現在日本語教師として活躍中で経過措置に国家資格への移行が必要な方
・養成講座受講中で国家試験対策に不安がある方
詳しくは公式サイトでご確認ください。↓のリンクをクリック。
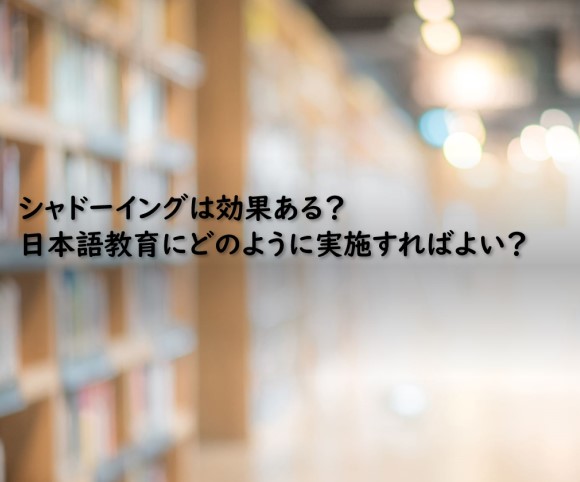
シャドーイングは効果ある?日本語教育にどのように実施すればよい?
シャドーイングは、音声を聞きながら同時に発生する練習です。 日本では英語学習の際に実施した人は多いのではないでしょうか? 日本語学習においても同様に効果的であるため、日本語教育の現場 において、どのようシャドーイングを導入していくかを解説します。