

実践研修とは?
概要
今回は、日本語教師になるために必要な教育実習である「実践研修」についてお伝えします。実践研修とはどのようなものなのか、どのように受講するのか、そしてどんな内容なのか、概要を知ってイメージを掴みましょう。
実践研修とは?
みなさんは、日本語教師になるための要件に「実践研修」というものがあることをご存じでしょうか。
学校の先生を目指す学生が教育実習を行うことは、多くの方がご存じだと思います。
日本語を母語としない人々に日本語を教える「日本語教師」の資格は、「国語」の教員免許とは異なります。しかし、教壇に立つ仕事ですので、他の教育職と同様に教育実習を受けなければなりません。
日本語教師の資格は「登録日本語教員」という国家資格で、日本語教員試験と呼ばれる筆記試験とともに、「実践研修」という教壇に立つための実習を受けることが必須になっています。この「実践研修」が、いわゆる教育実習にあたるものです。
登録日本語教員の資格を取得するには、
1)日本語学校や大学などが提供する養成講座に通って試験を受験する方法
2)独学で勉強して資格試験を受験する方法
の2つがあります。
これまでの制度では、日本語教師は国家資格ではなく民間資格でした。就職の際には「420時間養成講座修了」「大学の主専攻・副専攻修了」「日本語教育能力検定試験合格」のいずれかによって日本語教師資格が認められ、模擬授業や教壇実習は必須ではありませんでした。
しかし2024年の「日本語教育機関認定法」の制定によって日本語教師の国家資格化が決まり、「日本語教員試験」という国家試験が制定されました。国家資格「登録日本語教員」を取得するには、この国家試験に合格したうえで、実践研修を受講し、模擬授業と教壇実習を行うことが必須となったのです。
旧制度で日本語教師の資格を取得した現職者は経過措置として一定の条件を満たせば実践研修が免除となる場合がありますが、それ以外は基本的には実践研修の受講・修了が必須です。
養成講座であれば基本的にはその講座の中で実践研修を行いますが、独学で学ぶ場合は、日本語教員試験に合格したあと、「登録実践研修機関」と呼ばれる、文科省に登録を受けた教育機関に行って同様の研修を受けることになります。
「実践研修」では、まず受講生同士での演習(模擬授業)をおこない、そのあと実際の学生を相手にした実践(教壇実習)を行います。
日本語教師の模擬授業・教壇実習は、決められた時間の中で、指定された文法項目についての授業を行うというもの。導入する項目についての説明や練習問題、ペアワークなどの活動を、本番さながらの環境で行います。
ここで「模擬授業では英語で説明ができないといけないの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。たしかに英語話者や特定の国の学習者をターゲットにした教育を展開する一部の教育機関では、就職試験の際に外国語の能力が問われることがありますし、教師の外国語の能力が強みになることは間違いありません。
しかし、実践研修の段階で大切なことは、日本語の専門的な知識をいかに分かりやすく教えるかを考えること、どの言語圏の学習者にも適用できる基本的な教授スキルを体得することです。日本語教師の養成講座や実践研修では「直接法」という、日本語で日本語を教える方法を採用していますので、基本的に外国語のスキルは問われません。
何のために実践研修をする必要があるのか?
日本語教師になるために必要な知識やスキルは多岐に渡ります。日本語教員試験の基礎試験では、日本語や日本語教育に関する理論を学びます。言語学的な知識はもちろん、教育や心理に関する理論、異文化コミュニケーションや外交関係などについても扱います。
しかし、どの業界でも言えることですが、知識だけで現場に立つことはできません。理論と現場の橋渡しをし、現場に立つための実践的なトレーニングをして初めて教壇に立つことができるのです。
実践研修を通して、実際の授業づくりの流れを一通り経験することで、日本語教師としての仕事を体感することができます。実際にやってみると自分の得手不得手や課題が見え、担当講師や他の受講生からの客観的なフィードバックを得ることもできます。資格取得のためだけでなく、その先で現場に出る際の土台にもなる重要なプロセスだと言えます。
・就職の際にも模擬授業が課される
実践研修を修了して登録日本語教員の資格を取得すると、日本語学校などの日本語教育機関で、日本語教師の職に応募できるようになります。多くの教育機関では就職試験の際に、書類選考・面接と並んで模擬授業が課されます。内容や時間は会社や学校によって様々ですが、面接日の約1週間前に模擬授業の内容が知らされ、指定された項目について20分程度の模擬授業を用意していくのが一般的なようです。
就職試験の模擬授業では、その企業・学校の社員や専任講師が学生役となって模擬授業を評価します。専任講師は学生の躓きやすいポイントやよく突っ込まれるポイントを熟知していますから、鋭い質問や指摘がなされることも。そうした質問に臨機応変に対応できるかどうかなども見られます。事前の実践研修で日本語の文法項目や授業デザインについてしっかり理解しておかなければ、就職試験の模擬授業をパスすることはできません。
模擬授業・教壇実習は何回するの?一回当たりの担当時間は?
文科省では、「実践研修の指導時間は、45単位時間(1単位時間は45分以上。大学の単位に換算すると1単位)以上」と定められています。つまり時間に換算すると約33時間。週4時間ほど受講すれば約8週(約2ヶ月)程度で修了する内容です。実践研修は、日本語教員試験に合格すれば、任意の時期に受講できます。
実践研修は、以下のような流れで進みます。
(1)オリエンテーション
(2)授業見学
(3)担当する授業内容の決定
(4)各自準備(並行して他の受講生の模擬授業の学生役となり意見や質問を行う)
(5)実際に講師や受講生の前で模擬授業を行う→振り返り
(6)実際の学生の前で教壇実習を行う
(7)講師や学生からのフィードバックと振り返り
(8)全体のまとめ
まずはオリエンテーションでコースの内容について説明を受け、実際の授業見学に入ります。どのように授業がおこなわれているのか、生の現場が見られるチャンスです。授業見学ではレポートの提出が求められることもあります。
その後、各自模擬授業で担当する項目を決め、教材分析や教案作成などの準備に入ります。使用する教科書や項目は学校によっても異なりますが、一般的には「みんなの日本語」などの代表的な教科書から初級の重要な項目を当てられる事が多いようです。学校によっては初級~上級まで幅広いレベルで複数回の模擬授業を行います。
模擬授業では、担当の講師や他の受講生が学生役となり、実際の授業の流れを再現します。授業さながらの実践ですから、学生役から想定外の質問を受けて答えるという練習も含まれます。
発表のあとは講師や他の受講生からフィードバックをもらい、このプロセスを全員分回していくという流れになります。教室での模擬授業を行ったら、いよいよ教壇実習。実際の学生を相手に授業を行います。
ここで行う模擬授業・教壇実習は、個人レッスンではなくクラス指導です。文科省の発表では、教壇実習は「5人以上の生徒に対して同時に行われる日本語教育の授業の補助を行う」、「受講者1人につき45分以上の授業の補助を単独で2回以上行う」とあります。ここで言う「補助」とは授業の補佐のことではなく、実際の授業のように講師の立場で一人で授業を運営するという意味です。
まとめると、「クラス指導での教壇実習を、1人あたり45分以上、最低2回はおこなう」ということになります。
模擬授業(受講生同士での練習)の回数や時間は養成講座によっても異なります。一般的には10分~45分ほどの模擬授業を数回から数十回程度行い、教壇実習(実際に学生を相手に行う実習)は45分を2回以上行うものと考えておき、詳細は自分が検討している養成講座の担当者に確認するようにしましょう。
模擬授業の準備には時間がかかる?
模擬授業も教壇実習も本番を想定した練習ですので、準備が不可欠です。
しかし初めての模擬授業・教壇実習では、何をどれぐらい準備しなければいけないのか、初めは塩梅が難しいところ。
模擬授業の準備ではどのようなことが必要になるのでしょうか。一例を紹介します。
1)教材の分析
レベル・クラスの目的、学生が今までに習っている内容の確認。使う教科書の構成や練習の内容を見て、授業のゴールを決めます。
2)担当する項目についての情報収集
何を教えるか、導入の場面や例文を考える、導入項目に合った練習・クラス活動を考える、想定質問と答えを用意するなど
3)教案作成
授業の流れを考え、実施する内容や話す内容を時系列で台本に起こす作業です。
特に初級などで直接法の授業を行う場合は、学生が知っている語彙や文法だけを使って分かりやすく説明する「語彙コントロール」や「ティーチャートーク」の技術も必要です。突然の質問にあわててしまい、ネイティブの口調で説明してしまった結果、学生が全く理解できなかった・・・という事も良く起こります。どのような言い方で説明をするのか(あるいは何を説明「しない」のか)、ある程度の流れを決めておくと安心です。
4)教材作成
授業に必要なパワーポイント、プリント、実物などの用意をします。
その場で板書をする場合は、どこにどのような順番で何を書くのか、おおまかな板書計画をしておきます。
5)練習
作成した教案と教材を使って、実際に時間を測ってやってみます。
頭の中で考えているよりも、実際にやってみると「ここはこうしたほうがいいかも」という部分がわかると思います。
意外と見落としやすいのが、自分の立ち位置や動線、そして機材の使い方です。
前に立つ教師の姿勢や動作は案外目につくもの。次は何をするんだっけ・・・と黒板の前をウロウロしないよう、学生にとって見えやすい位置を考えておくと安心です。
また、最近ではパワーポイントなどの資料をモニターで表示する形式が主流になってきています。模擬授業当日になって学校の機材を使ってみたら、機器が合わなかったり、文字化けやフォーマットのずれで表示できなかった、データが消えていた・・・などと慌てることのないよう、データのバックアップや接続機器の確認をしておくのがおすすめです。
人にもよりますが、初めての模擬授業では、多めに見積もって実際の授業時間の3~5倍ほど時間がかかると思っておきましょう。仕事と並行して日本語教員試験の資格取得を目指す場合は時間の確保が難しい場合もあると思います。余裕をもってスケジュールを組み、早めに準備に取り掛かりましょう。
実際に現場に出るといくつもの授業をこなすことになります。授業報告や宿題の採点など、授業以外の業務もありますから、あまり準備に時間をかけられません。ただ、経験を積めば教材のストックも増え、どこに比重を置けばよいか分かってくるので、授業準備の時間は短縮できます。
模擬授業の段階では、まず授業作りの一通りの流れを掴むという気持ちで、焦らずに取り組むと良いのではないかと思います。
まとめ
今回は日本語教員になるための実践研修について解説してきました。
「人前で授業などしたことがないが、教壇に立てるのだろうか」
「外国人に日本語を教えるためにどういうノウハウがあるのだろうか」
「言葉が通じない学生にうまく伝わる授業ができるか心配・・・」
こうした疑問や不安は、日本語教師を目指すとき誰もが感じ得るものだと思います。
TCJの養成講座では、実際の留学生を相手に授業を経験することができます。TCJに所属している学生ですので、教壇実習の際には、学生のことをよく知る講師やスタッフから指導を受けることも可能です。
実践研修対策をお考えの方はぜひ、TCJの養成講座をご検討ください。
参考・引用
文化庁「登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関に関する省令等の案について」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93998101_01.pdf
文部科学省「登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリキュラム」
https://www.mext.go.jp/content/20240321-ope_dev02-000034812_4.pdf
国家試験対策が必要な方へ
TCJ日本語教師養成講座では、日本語教員試験の学習に特化したeラーニング教材を開発しました。
令和6年度日本語教員試験での合格率(当社調べ)
・基礎、応用試験 合格率44% (全国平均8.7%)
・応用試験のみ 合格率71%(全国平均 60.8%)
試験ルートの合格率が全国平均の約5倍となっています。
【こんな方におススメ】
・試験ルートで登録・日本語教員の資格取得を検討している方
・現在日本語教師として活躍中で経過措置に国家資格への移行が必要な方
・養成講座受講中で国家試験対策に不安がある方
詳しくは公式サイトでご確認ください。↓のリンクをクリック。
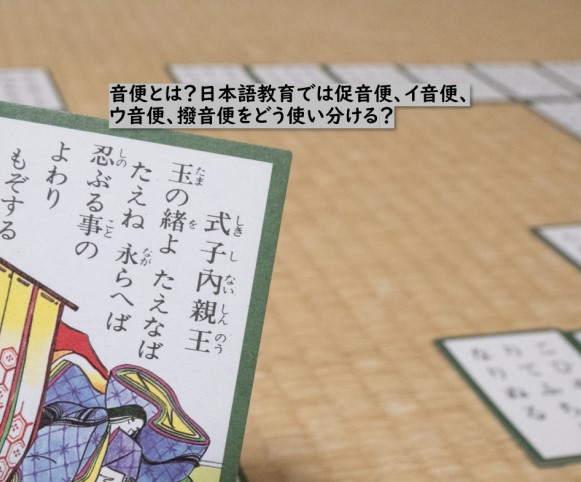
音便とは?日本語教育では促音便、イ音便、ウ音便、撥音便をどう使い分ける?
日本語には音便という変音現象があります。これは、いつ頃起こったのでしょうか。また、日本語学習者にとって、この現象はどう捉えられているのでしょうか。ここでは音便について、その歴史と現場での扱い方・留意点などをご紹介していきます。








