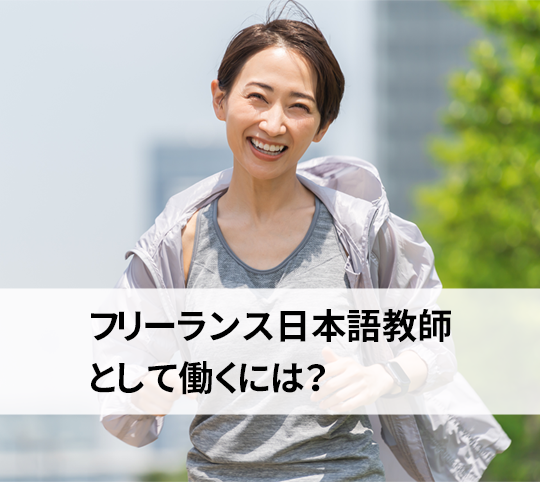日本語のアクセントとは?
概要
この記事では、日本語でのスムーズなコミュニケーションに欠かせない「アクセント」について取り上げます。アクセントは、現役の日本語教師にとってはもちろん、これから日本語教員試験に臨む方にとっても、避けては通れない重要項目。しっかりポイントをおさえていきましょう。
日本語のアクセントとは?
「アクセント」という言葉は、「この料理は、山椒の香りがいいアクセントになっている」のように日常生活の中でも使われますが、日本語教育における「アクセント」とは一体何でしょうか。国語辞典によると、アクセントとは「一つ一つの語について社会慣習的に決まっている、相対的な高低や強弱の配置」と定義されています。また、英語・ドイツ語などに見られる「強弱アクセント」と、日本語などに見られる「高低アクセント」との二種がある、と添えられています。
簡単に言うと、日本語のアクセントとは「一つの単語の中での高さの変化」だと言えます。
ここで一点注意していただきたいのが、「イントネーション」との違いです。アクセントが、一つ一つの単語の中での高さの変化を指すのに対して、イントネーションは、文レベルでの高さの変化を指します。単語レベルではありません。日常会話でも「あの人のイントネーション、ちょっと変じゃない?」などと話すことがありますが、もしそれが「単語レベル」での高低の違和感であれば、正確には「イントネーション」ではなく「アクセント」と言うべきでしょう。
ではなぜ、日本語教育においてアクセントが重要なのでしょうか。
それは、日本語には、アクセントの違いによって意味が変わる言葉が多く存在しているから。初級レベルで導入する「はし」という言葉を使って、具体的に見てみましょう。
■ 橋:は•し(低 高)
■ 箸:は•し(高 低)
このように、同じ「はし」という音であっても、高い低いが異なることで、言葉の意味が完全に変わってしまいます。正確なコミュニケーションには、正しいアクセントが欠かせないのです。
日本語アクセントの特徴と地域差 ~東京式と京阪式の違い~
日本語のアクセントには、大きく2つの特徴があります。
・1拍目と2拍目で、高低が異なる。
・単語の中で一度下がったら、二度と上がらない。
では、具体的に見てみましょう。
■ バイク:ば•い•く(高 低 低)
■ 飛行機:ひ•こ•う•き(低 高 低 低)
■ ヘリコプター:へ•り•こ•ぷ•た•あ(低 高 高 低 低 低)
バイクでは、1拍目が「高」、2拍目が「低」、飛行機とヘリコプターでは、1拍目が「低」、2拍目が「高」となっています。確かに1拍目と2拍目で高低が異なります。
またいずれも「高→低」と下がった後は「低」が続いており、その後、上がっていないことがわかります。
これらは日本語のアクセントの重要な特徴ですが、なんと、そのルールをくつがえす存在があるのです。それが地域によるアクセントの違いです。日本語はアクセントの地域差が大きい言語だと言われており、日本語研究の第一人者である金田一春彦先生によると、日本には「東京式」や「京阪式」を代表とする、アクセントのグループが存在します。
■東京式アクセント:東京、関東を中心に、北海道や東北の一部、中国地方や九州の一部で見られるアクセント。標準的な日本語として、テレビの全国放送や教科書の音声教材などに用いられている。
■京阪式アクセント:京都、大阪を中心に、関西や四国の一部で使用されているアクセント。
注意していただきたいのが、京阪式アクセントは、東京式アクセントと高低が異なったり、日本語のアクセントの特徴である「1拍目と2拍目の高低が異なる」というルールが当てはまらないケースがある、ということ。具体的に「あめ」という言葉を使って見てみましょう。
■ 雨(あめ)
東京式:あ•め(高 低)|京阪式:あ•め(低 高)
■ 飴(あめ)
東京式:あ•め(低 高)|京阪式:あ•め(高 高)
ご覧の通り、「雨」では、東京式と京阪式で、高低が逆になっています。また「飴」の京阪式アクセントでは、1拍目と2拍目で高低の差が見られません。
一般的な日本語教材では、東京式アクセントが採用されているため、京阪式アクセントの地域の学習者にとっては、日常生活の中で耳にするアクセントと、学習用教材で耳にするアクセントが異なる、という事態が起こりえるのです。
日本語教育におけるアクセント指導の現状
現在、多くの日本語教育機関で、アクセント指導があまり体系的に行われていないのが現状です。その理由には以下のようなものが考えられます。
■ 文法や語彙、会話練習などが優先されている
■ 教材にアクセントに関する情報が載っていない
■ 教師があまりアクセントを意識していない
私は現在、国際交流基金の教科書『まるごと』を使って指導することが多いのですが、この教科書では中級レベルになってはじめて、アクセントやイントネーションを扱うコーナーが登場します。
また、初級レベルから補助教材の中で、アクセント記号を表記している教科書もありますが、学習者がそれを十分に活用できているかどうかについては、疑問が残ります。
ただし、こうした状況があるからといって、アクセント指導が重要でないというわけではありません。大切なのは、教える側である教師自身がアクセントに敏感であることだと思います。
私自身は京都出身で、香川や広島に住んだ後、東京で10年以上暮らしてきました。学生時代は放送部で、アクセント辞典を片手に発音を研究していました。ですので、地域によるアクセントの違いや、自分が京阪式アクセントで単語を捉えやすいことをよく理解しています。そのため、教材の音声は必ず事前に確認するようにしています。
地域ごとのアクセントの違いは、文化の豊かさの表れですし、否定されるべきものではありません。ですが、アクセントによって意味が変わる言葉が存在する以上、日本語教師としては、学習者が混乱しないよう、自身が発する言葉に注意を払う必要はあるのではないでしょうか。特に教師の発音を模倣しながら、日本語のアクセントを習得する初級学習者に対しては、細心の注意が必要です。
私は授業では、学習者の混乱を避けるため、東京式アクセントを採用しています。ですが中級以上のクラスでは、ごく稀に京阪式アクセントで話すこともあります。そうすることで、学習者が日本語のアクセントの多様性に関心を持つきっかけにもなっています。
外国人学習者がつまずきやすいアクセントのポイント
母語話者が無意識に使っているアクセントは、外国人学習者にとっては習得しにくいものの一つです。特に以下の2点は、指導の際、注意したいポイントです。
■ 同音異義語
「あめ(飴、雨)」や「はし(橋、箸)」のように、音は同じでも意味が異なる言葉を「同音異義語」と言います。アクセント指導において、同音異義語は最重要ポイントです。高低を示しながら、しっかり音を聞かせましょう。初級レベルでも、以下のような同音異義語を指導します。
・にほん:日本、二本
・きた:来た、北
・かみ:紙、神、髪
・いま:今、居間
・はな:花、鼻
■アクセント変化のある単語
単語と単語が組み合わされることによって、アクセントが変化するケースにも注意しましょう。例えば「春休み(春+休み)」や「京都駅(京都+駅)」など、複数の単語から構成される「複合語」は、もともとの単語のアクセントが変化することがあります。
・春休み:は•る•や•す•み(低 高 高 低 低)↔︎春:は•る(高 低)|休み:や•す•み(低 高 低)
・京都駅:きょ•う•と•え•き(低 高 高 低 低)↔︎京都:きょ•う•と(高 低 低) 駅:えき(高 低)
この現象は複合語だけでなく、句や文を作ったときに現れることもあります。
・電話で話す:で•ん•わ•で•は•な•す(低 高 高 高 高 高 低 )↔︎電話:で•ん•わ•で(低 高 高 高)|話す:は•な•す(低 高 低 )
日本語教師にとって重要なことは、教師自身が事前に音声を確認しておくこと。そして、自身の発音に少しでも不安を感じた場合は、アクセント辞典などで調べることです。(OJADというオンラインの無料アクセント辞典などを活用するのも良いでしょう。)また授業中には、学習者にしっかりと音声を聞かせることも欠かせません。特に、どこで「高→低」の変化が生じているかに注目させると、アクセントが理解しやすいでしょう。
まとめ
日本語のアクセントは、語彙や文法に比べると優先順位が低くなりがちですが、正確なコミュニケーションのためには、初級から丁寧に指導する必要があります。現役の日本語教師はもちろん、これから日本語教師を目指す方は、まずは自分自身の発音に意識を向けるところから始めたいですね。この記事がみなさんの指導力アップにお役に立てれば幸いです。
参考
NHK放送文化研究所編 (2016)『日本語発音アクセント新辞典』NHK出版
金田一春彦監修 秋永一枝編 (2013)『新明解アクセント辞典』三省堂
田中真一, 窪薗晴夫 (1999)『日本語の発音教室 理論と練習』くろしお出版
国家試験対策が必要な方へ
TCJ日本語教師養成講座では、日本語教員試験の学習に特化したeラーニング教材を開発しました。
令和6年度日本語教員試験での合格率(当社調べ)
・基礎、応用試験 合格率44% (全国平均8.7%)
・応用試験のみ 合格率71%(全国平均 60.8%)
試験ルートの合格率が全国平均の約5倍となっています。
【こんな方におススメ】
・試験ルートで登録・日本語教員の資格取得を検討している方
・現在日本語教師として活躍中で経過措置に国家資格への移行が必要な方
・養成講座受講中で国家試験対策に不安がある方
詳しくは公式サイトでご確認ください。↓のリンクをクリック。