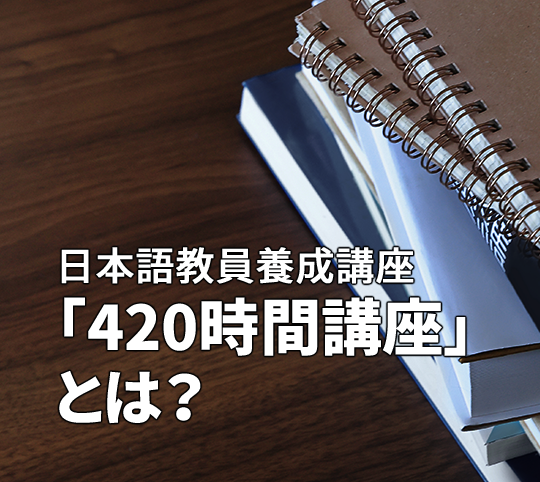日本語学習者への敬語の教え方ポイント|尊敬語と謙譲語の使い分け
この記事では、日本語学習者だけでなく、日本人でも苦手意識を持つ人が多い「敬語」について取り上げます。まずは敬語を理解するためにおさえるべき分類の仕方、そして尊敬語と謙譲語の具体的な指導ポイントについて、わかりやすくお伝えします。
敬語の5分類とは
敬語をマスターするためには、まずその種類をおさえる必要があります。文化庁が公表した「敬語の指針」に基づくと、敬語は以下の5つに分類されます。
①尊敬語
②謙譲語Ⅰ
③謙譲語Ⅱ(丁重語)
④丁寧語
⑤美化語
この「敬語の指針」は日本語教師必読の資料です。ですが、資料は約80ページに及び、日々の授業準備に追われる先生方や、日本語教員試験に向けて勉強中の方にとっては、ややボリュームがあるのも事実。そこで今回は、内容をかみ砕き、ポイントをご紹介します。
①尊敬語
■定義:相手や第三者の行為に敬意を表す。
■例:社長がいらっしゃいました。(社長の「来る」という行為に敬意)
先日、おっしゃっていた件ですが…。(相手の「言う」という行為に敬意)
→尊敬語は相手や第三者のアクションを立てる表現です。
②謙譲語Ⅰ
■定義:自分の行為をへりくだり、行為が向かう相手に敬意を表す。
■例:私が御社に伺います。(自分の「行く」という行為をへりくだる)
早速、拝見します。(自分の「見る」という行為をへりくだる)
→謙譲語Ⅰは自分のアクションを下げて、アクションが向かう先の相手を立てる表現です。
③謙譲語Ⅱ(丁重語)
■定義:自分の行為を丁重に述べる。行為の相手は特定されない。
■例:旅行でスペインに参ります。(自分の「行く」という行為を丁重に述べる)
山田花子と申します。(自分の「言う」という行為を丁重に述べる)
→謙譲語Ⅱは、アクションが向かう先ではなく、聞き手に丁重さを伝える表現です。
④丁寧語
■定義:話し手が聞き手に対して、丁寧に述べる。
■例:旅行でスペインに行きます。
それは本です。
→丁寧語は「です」「ます」を使った表現で、自分のことに限らず、幅広く使える表現です。
⑤美化語
■定義:ものごとを美化して述べる。
■例:お酒
ごはん
→美化語は「お」「ご」をつけて、言葉を美しく整える表現です。
■教え方のポイント
「お」「ご」がついているからと言って、全てが美化語ではありません!尊敬語や謙譲語の場合もあります。
・相手の行為や所有物につく場合→尊敬語(例)ご出席、先生のお名前
・自分の行為をへりくだり、相手に敬意を表す場合→謙譲語(例)先生へのお手紙
敬語指導のポイント
5種類の分類を確認してきましたが、敬語指導の要は何と言っても「尊敬語」と「謙譲語」。それぞれの働きを理解させ、使い分けができるように指導する必要があります。尊敬語と謙譲語の理解が曖昧だと「敬語を使ったつもりが逆効果だった」なんてことにもなりかねません。
指導の際は、次の2点にフォーカスしましょう。
1. だれのアクション?
2.かたち(文型)
では、尊敬語、謙譲語のポイントをそれぞれ、おさえていきましょう。
尊敬語の指導、まずはコレ!
■だれのアクション?
相手や第三者のアクション(例)社長が来た。→社長がいらっしゃった。
■ かたち(3パターン)
1.特別な形:いらっしゃる、召し上がる など
2.お〜になる:お帰りになります、お読みになります など
3.Vられる:行かれる、食べられる など
■ 教え方のポイント
①3つの形には丁寧度に差があります。「特別な形」が最も丁寧で、1→2→3の順で、丁寧度は下がります。
②特別な形の尊敬語は、新しい語彙としてインプットしましょう。まずは、以下の7つをしっかり教えましょう。
※みんなの日本語Ⅱ参照
・いらっしゃいます|行きます・来ます・います
・召し上がります |食べます・飲みます
・おっしゃいます |言います
・ご存じです |知っています
・ご覧になります |見ます
・なさいます |します
・くださいます |くれます
謙譲語の指導、まずはコレ!
■ だれのアクション?
自分のアクション。(例)私が見る。→私が拝見する。
■ かたち(2パターン)
1. 特別な形:伺う、拝見する など
2.お(ご)〜する:お伝えする、ご案内する など
■ 教え方のポイント
①「特別な形の謙譲語」のほうが、「お(ご)〜する」より丁寧です。
②「お〜する」は1グループ、2グループの動詞、「ご〜する」は3グループの動詞に使います。ただし、3グループには例外もあります。「約束する」「電話する」「掃除する」「洗濯する」などは「お〜する」となります。
③「謙譲語Ⅰ」と「謙譲語Ⅱ」を使い分けましょう。どちらも自分のアクションを下げますが「謙譲語Ⅰ」はアクションが相手に向かい、「謙譲語Ⅱ」ではアクションが相手に向かわず、聞き手に丁重さを表すだけです。なお「お(ご)〜する」は「謙譲語Ⅰ」に使います。
【誤】(社長との会話)実は私、来月ご結婚します。× <相手にアクションが向かわない>
【正】(社長との会話)実は私、来月結婚いたします。⚪︎ <謙譲語Ⅱ。聞き手である社長に丁重に話している。>
④特別な形の謙譲語も、新しい語彙としてインプットしましょう。教科書によっては、謙譲語ⅠとⅡを分けずに紹介しているケースも多いのですが、動詞によっては謙譲語ⅠとⅡで違いがあります。特に★は、検定試験対策としても、しっかりおさえてきましょう。
【謙譲語Ⅰ】
・いただきます |食べます・飲みます・もらいます
・拝見します |見ます
・伺います★ |聞きます・行きます・来ます
・お目にかかります|会います
・申し上げます★ |言います
・存じ上げます★ |知っています
【謙譲語Ⅱ】
・まいります★ |行きます・来ます
・おります |います
・いたします |します
・申します★ |言います
・存じております★|知っています
尊敬語と謙譲語を使い分け。学習者の誤用を訂正してみよう!
では、理解度チェックのために、学習者の誤用を訂正してみましょう。
【誤1】私が部長におっしゃった通り
→私が部長に申し上げました通り(アクションするのは私!→謙譲語Ⅰ)
【誤2】社長がこちらに伺いました。
→ 社長がこちらにいらっしゃいました。(アクションするのは社長!→尊敬語)
【誤3】お客様からのお手紙、嬉しくご覧になりました。
→お客様からのお手紙、嬉しく拝見しました。(アクションするのは私!→謙譲語Ⅰ)
【誤4】昨日、部長に申した通り
→昨日、部長に申し上げた通り(アクションが相手に向かっている!→謙譲語ⅡではなくⅠ)
【誤5】部長がお客様をご案内いたしました。
→部長がお客様をご案内なさいました。(アクションするのは部長!→尊敬語)
まとめ
日本人でも苦手意識を持つ人がいるぐらいの敬語ですが、ポイントさえしっかりおさえれば、指導は決して難しくありません。何より敬語は相手との関係を大切に考えているからこそ存在する言葉。私のクラスでは、敬語を最初に教えるときに「日本人の心だよ」「敬語が使えたら本当にかっこいいね」と言って、ポジティブなイメージと共に教えるようにしています。そうすると、少なくとも学習者は「敬語を実際に使ってみたい!」と思ってくれるようです。この記事が、みなさんの敬語への理解や現場での指導のお役に立てれば幸いです。
参考
文化庁(2007)「敬語の指針」https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/sokai/sokai_6/pdf/keigo_tousin.pdf
国家試験対策が必要な方へ
TCJ日本語教師養成講座では、日本語教員試験の学習に特化したeラーニング教材を開発しました。
令和6年度日本語教員試験での合格率(当社調べ)
・基礎、応用試験 合格率44% (全国平均8.7%)
・応用試験のみ 合格率71%(全国平均 60.8%)
試験ルートの合格率が全国平均の約5倍となっています。
【こんな方におススメ】
・試験ルートで登録・日本語教員の資格取得を検討している方
・現在日本語教師として活躍中で経過措置に国家資格への移行が必要な方
・養成講座受講中で国家試験対策に不安がある方
詳しくは公式サイトでご確認ください。↓のリンクをクリック。