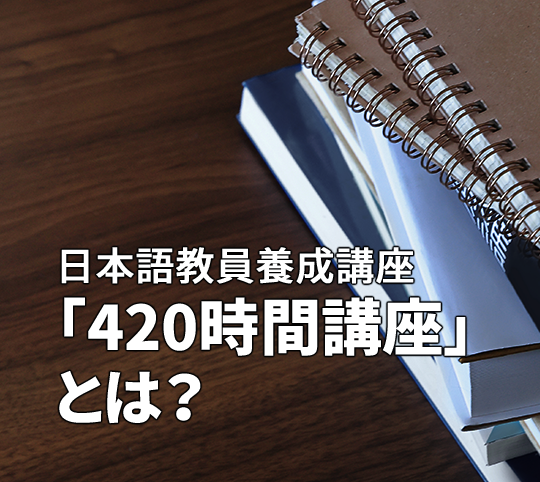生成AIとは?日本語教育での活用方法を紹介!
概要
IT技術の発展とともに教育現場のICT化が進み、日本語教育の分野でもIT技術が活用されるようになってきています。今回は、その中でもAI(人工知能)に注目し、言語教育の現場での活用について見ていきます。既に使ったことがある方にも、これから使い方を覚えたいという方にもご一読いただきたい内容となっています。
生成AIとは?
AIとはArtificial Intelligenceの略で、日本語では「人工知能」と訳されます。その中でも「生成AI」は、その名前の通り「何かを生成する、作り出すAI」で、既存のデータを学習して、文章や画像、音声、動画などの新しいコンテンツを作り出す人工知能です。
これまでのAIはデータの分析や分類を行うために利用されてきましたが、生成AIはデータを取り入れて分析するだけでなく、それらのデータに基づいて新しいものを創り出すことができるという点で異なります。
・生成AIの種類と活用方法
生成AIは大きく分けて4種類あります。
1)文章生成AI(ChatGPT、Gemini、Claudeなど)
自然言語処理技術を使って文章を作成することができるAIです。学習した文章の翻訳、要約などができるほか、チャットメッセージのようなやりとりをすることもできます。最近は企業のウェブサイトなどでもよく「チャットボックス」といって、質問したいことや困っていることを入力すると、問い合わせの窓口や商品の扱い方を教えてくれる自動の案内サービスがありますね。こうした顧客サービスでも、このようなAIが活用されています。
2) 画像生成AI(Stable Diffusion、Midjourney、DALL-Eなど)
テキストによる指示や既存の画像を基に、新しい画像を作ることができ、イラストの作成、写真の編集やチラシ、ロゴのデザインなどに活用できます。
3)動画生成AI(Runway Gen-2、Make-a-Videoなど)
文で指示をしたり画像を学習させたりすることによって、新しい動画を作成できます。映像制作、コンテンツの作成、広告などに使用可能です。
4) 音声・音楽生成AI(Suno AI、MusicLMなど)
読み込ませた文や文章を音声に変換したり、楽曲を生成したりできます。
ナレーションの作成や音楽制作などで活用できるAIです。
日本語教育でも活用できる?
教育現場でも生成AIの活用が進んでいます。日本語教育をはじめ、言語教育の現場でどのように活用されているのか、例を挙げてみていきましょう。
・教師による活用
1)翻訳
特に教師側が活用できるのはこの翻訳機能です。
・授業用の教材を作る時に、学習者の母語を使って補助的な説明を加えたい
・多言語で学校のお知らせを作成したい
などの場面で活用できます。
生成AIは、ただ訳すだけではなく、指示の仕方によって原文のニュアンスに近い文を作らせることが可能です。「テストのお知らせに使う、客観的で丁寧な文にしてください」「ビジネスで使う丁寧な言い方に」「カジュアルな言い方に」など、文体やニュアンスの指示もすることもできるため、ネイティブによる翻訳チェックができない場合でもある程度正確な翻訳が得られます。
2)例文や教材用の文章を作成する
学習者が文法や表現を正しく理解できるよう、教師はわかりやすい例文をたくさん作っておく必要があります。AIは自分が普段使わない文を提示してくれることもあるため、自分自身の例文の偏りを防ぐことにも役立ちます。
また、練習問題やテストなどで分量のある読解問題の文章を作成しなければならないときにもAIが使えます。「『環境』『分別』『汚染』『制度』『企業』という語彙を使った500字ぐらいの文を作ってください」のように、特定の語彙や文法表現を含めるよう指示することもできます。
ただ、AIで作った文章はやはり機械的で不自然な文章になってしまうので、あくまでもアイデアや雛形として使用するのがおすすめです。
3)イラスト教材を作成する
語彙や表現を導入する際にイラストでわかりやすく説明したいけれど、場面に合ったイラストが見つからない・・そのような時にも、AIを使って教材の内容に合ったイラストを作成することができます。
5)情報収集
生成AIは、インターネット上にあるあらゆる情報を一度に集めてまとめて提示してくれるというメリットもあります。一度に複数のサイトから関連情報を集めて表示させることが可能なので、情報集めが容易になります。例えば学習者の母語や文化に関して知りたいことがあったときや授業で扱う表現に関する過去の研究などを調べたいとき、自分で何十ものサイトを探さなくても、知りたい内容に沿ったサイトを引用して教えてくれます。
・学習者による活用
学習者の立場では、主に自主学習でAIが活用できます。
1)チャットや音声によるやり取りの練習
最近ではAIを活用した語学学習アプリも増えています。アプリに向かって話しかけると自動で音声を認識し、まるで人間のように返事をしてくれるという「会話機能」が注目を集めています。こうしたアプリは有料のものが多く、民間の企業が作っていることが多いです。しかし無料で使える生成AIでも、同じような使い方ができます。チャットメッセージなどで文章を入力すると、会話しているかのように返事をしてくれます。この機能を使って、やりとりの文章を書く・読む練習ができます。
2)自分の書いたものを添削してもらう
自分が書いた文章を添削してもらうという活用方法もあります。語彙表現の使い方が合っているか、失礼に当たらないかなどをある程度の精度で添削してもらうことが可能です。「○○場合の自然な言い方は?」などと指示すると、最適な表現を教えてくれます。
3)理解できない表現の解説や翻訳
言語学習の一環としてドラマや映画を見たりする人も多いと思いますが、字幕を見て文字通りに訳することはできても意味がよく分からない、どうしてこういう言い方をするの?と思うことがあると思います。
母語話者向けに作られた映画やドラマは、文学的・抽象的な表現や、その国の文化、慣習や宗教を知らないと理解できないジョークなどもたくさん出てきます。外国語として学ぶ立場では、そうした社会的な文脈を合わせて教えてもらえたら助かりますよね。そんなときも、そのシーンやセリフを文章で入力するだけで、AIが会話の意味を推測し、教えてくれます。文章が長いときには、その文章の写真を撮って読み込ませるだけで、該当する文章を文字起こしして解説してくれる機能もあります。
生成AIのリスク
AIは便利なツールですが、一方ではリスクもあります。
AIのリスクとしてまず考えられるのは、不正や情報漏洩、著作権などに関する問題です。
・学生が宿題や答案をAIで作成するなど、不正に使われる可能性がある
・個人情報や会社の機密に触れるような情報を学習させてしまうと、AIを通して情報が漏洩する可能性がある
こうした点は常に心に留めておかなければなりません。
教育現場においては、教師や学生がAIに個人情報や会社・学校に関する情報を学習させてしまい情報が洩れる、学生が宿題や試験をAIにやらせてしまうといった不正が起こる可能性もあります。
また、より日常的に考えられるのは、学生がAIを使って宿題やクラスの課題をやってくる、試験での不正をするというケースです。
自主学習の範囲で使用するのであればよいのですが、作文などをAIで作成してしまうと公平性の観点からも問題がありますし、何より本人のためになりません。
・普段と比べて、不自然に正答率が高い
・本人の実力と合わないような難解な文、機械的な正しすぎる文を書いている
こうした特徴から不正に気がつく先生は多いと思います。不正を防ぐためにも、普段からの学習者の様子に気を配るようにしましょう。
また、教育者として仕事でAIを使用する場面でも同様に、自分が活用している情報が正しいか、他者の権利を侵害するものでないかを考える視点を忘れてはいけません。
AIはあくまでも既存のデータを使って分析や生成をするものですから、元のデータが間違っていればAIが提示するものも当然間違った情報になってしまいます。日常的な検索程度であれば問題ないかもしれませんが、仕事で使用するという場合にはやはり一次情報にあたるべきでしょう。
基本的な注意事項として
・AIで生成したものをまるごと外に向けて発表しない
・不正にAIやAIで作成した文章・画像・音源を使用しない
・個人情報や会社の情報を入力しない、させない
などの点に気をつけ、情報利用の意識を持って利用しましょう。
私も実際に、外国語学習や教材作りでChatGPTを活用しています。情報処理の速度や精度は目を見張るものがありますが、同時にその手軽さに少し恐れも感じます。
AIで作成した正しい文章よりも、その人が自分で書いた文の方が、多少間違っていたとしても温かみが残ることもあります。
自分でできないところをツールを使って補うという気持ちで、技術を活用していきたいですね。
まとめ
今回は生成AIとその活用について見て来ました。
生成AIは、使い方を守れば授業に大いに活用でき、教室活動の幅も広がる新しいツールです。ここで紹介した以外にも、色々な活用例があると思います。ぜひ職場や仲間で新しい使い方を共有して、引き出しを増やしていきましょう!
国家試験対策が必要な方へ
TCJ日本語教師養成講座では、日本語教員試験の学習に特化したeラーニング教材を開発しました。
令和6年度日本語教員試験での合格率(当社調べ)
・基礎、応用試験 合格率44% (全国平均8.7%)
・応用試験のみ 合格率71%(全国平均 60.8%)
試験ルートの合格率が全国平均の約5倍となっています。
【こんな方におススメ】
・試験ルートで登録・日本語教員の資格取得を検討している方
・現在日本語教師として活躍中で経過措置に国家資格への移行が必要な方
・養成講座受講中で国家試験対策に不安がある方
詳しくは公式サイトでご確認ください。↓のリンクをクリック。

ピア・ラーニングって何?日本語教育現場における活用方法も紹介
この記事では、 「そもそもピア・ラーニングとはなんだろう?」という方や、 「養成講座で聞いたことのある言葉のような気がするけど詳しくは分からない」という方へ、 ピア・ラーニングの意味や、実践例についてまとめました。 用語の意味理解の促進や、実際のクラス活動にお役立ていただけたら嬉しいです。

「やさしい日本語」とは
普段何気なく使っている日本語ですが、外国人にとっては大変難しく感じる場面があります。 同じ意味を指す言葉例えば「昼ご飯」という言葉ですが、他にも昼食やランチなど色々な表現があります。 このように日本語には無数の言い方があり、それを無意識に選別して使っているため、どういう表現が簡単なのかを 瞬時に判断ができないのです。 本記事では、やさしい日本語について解説します。