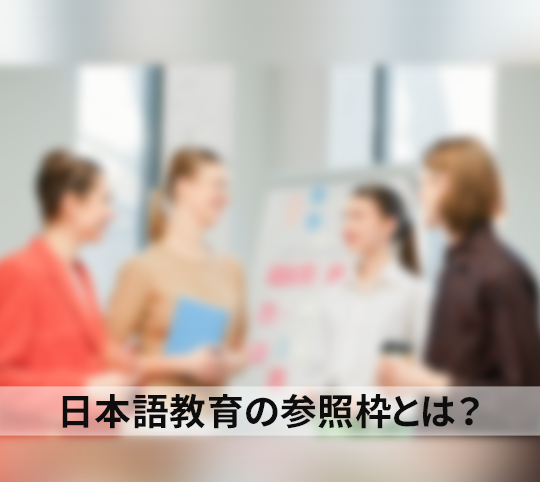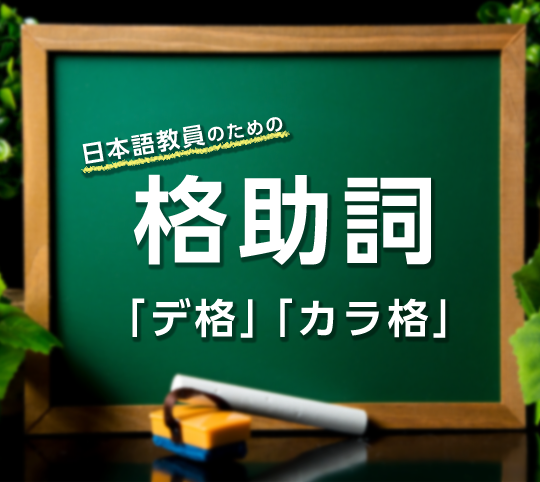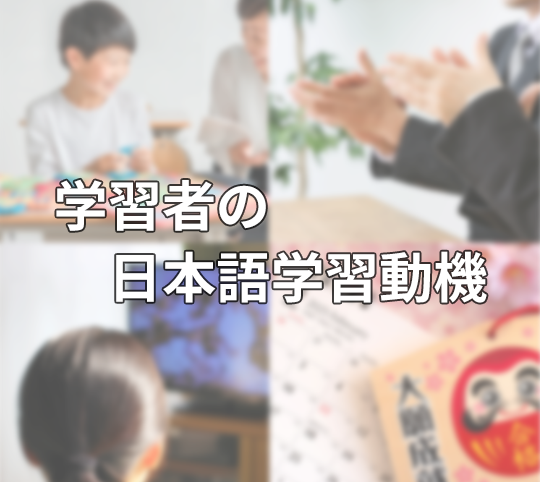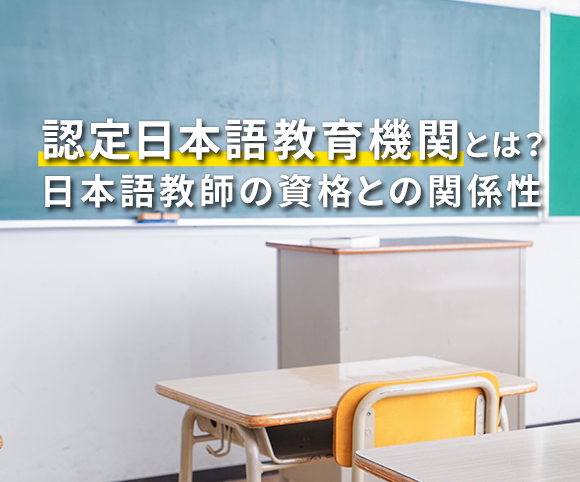TCJコラム

【日本語教員試験対策】「日本語教育の参照枠」の「全体的な尺度」とは?日本語能力の6レベルを分かりやすくご紹介!
日本語のレベルを判断する際の基準として役立つ「日本語教育の参照枠」の中から、最もおおまかな尺度である「全体的な尺度」について解説します。「初級」「中級」などと言っても、レベルの定義は実はあいまい。そんなときに活用できるのが、今回解説する「全体的な尺度」です。「日本語教員試験」にも出てくる重要キーワードで、教師デビューした後も活用できるものですので、理解を深めてみてください。